
「六本木未来大学」第22回 Whateverさん講義レポート【後編】
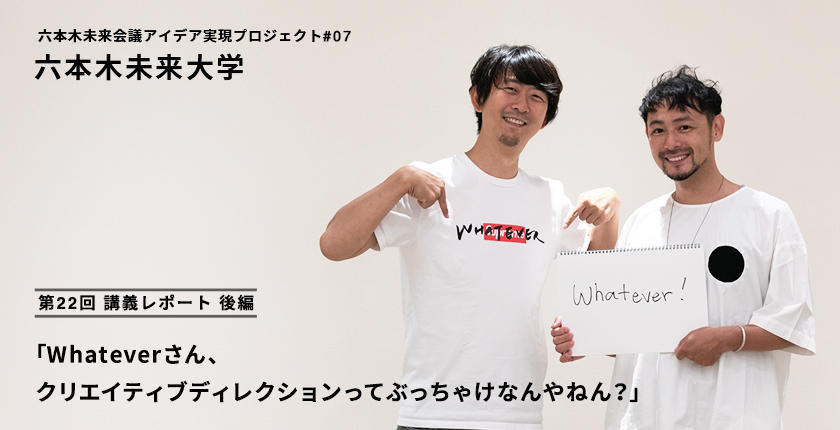
第22回 講義レポート後編「Whateverさん、クリエイティブディレクションってぶっちゃけなんやねん?」
六本木未来大学 第22回
Whateverの「クリエイティブディレクションのルール」
- #1
- 個人のモチベーションを最大限にサポートする
- #2
- 企画と制作を横断し、「考えてつくれる」チームにする
- #3
- 指揮者のように、スペシャリストを選ぶ
- #4
- アイデアを出した人にもクレジットをつける
- #5
- プロジェクトのフローを可視化する
- #6
- 直球と変化球と暴投、3パターンで提案してみる
- #7
- フィージビリティー検証を徹底する
- #8
- 想像力+補完力で言語やルールの違いを埋める
- #9
- 出したアイデアに固執せず、柔軟性を持つ
- #10
- 実現するためには、あの手この手すべてやる
- #11
- プロジェクトをベストな品質で実現することに責任を持つ

企画の解像度を上げる、徹底した検証。
会場からの質問で「企画の段階で実現可能性の検証をどのくらいしているか」と具体的な問いが出され、企画から制作における検証の重要性についての話になりました。
川村フィージビリティー(実現可能性)については、おそらく他の会社よりも検証して提案しています。アイデアを気に入ってもらっても、それがイメージ通りに実現できないと、めちゃくちゃがっかりするので、絶対にできないアイデアを提案するのは避けます。その代わり、7割はつくれるよねと判れば、たとえ"暴投"的な企画であっても提案するし、僕らならつくれますよとクライアントに言えるんです。それはやはり、企画する人間とつくる人間が最初から一緒に関わっているからなんですね。提案フェーズの次に細かい実験を重ねていく。このことが結果的にクライアントからの信頼につながっていると思います。
富永頼まれていることがどういうものなのかを検証するためにも、ちょっと違う感覚、少し異なる角度から提案してみることはとても重要。その検証をすることで、最終的に企画自体の解像度が上がります。
【クリエイティブディレクションのルール#7】
フィージビリティー検証を徹底する
言語もルールも異なる環境で壁を壊していく。
NHK総合で放送されたドキュメンタリー番組「復活の日」。タレントの出川哲朗さんが8年前(2011年)に亡くなったお母さんとバーチャルで再会するという前代未聞の企画では、テレビ制作の現場という「クリエイティブディレクター」が存在しない環境で、どのように言語やルールの違いを埋めていくかが重要になりました。

富永テレビの現場には、プロデューサーと監督がいて、監督が演出を考えています。彼らは基本的に頭の中に撮りたい画があって、それに沿って撮影していくのですが、今回のケースはリアルな撮影現場とバーチャルな撮影現場が同居していて。スタジオの横にモーションキャプチャールームをつくり、演者の動きをリアルタイムでレンダリングして、スタジオのモニター上にフィードバッグしているんです。なので、タイミングを合わせて交互にディレクションしていく必要があり、それぞれの役割を横断して設計することが求められました。
川村やったことのないことを実現しようという気持ちは、テレビサイドも僕らも同じでした。ただ、映像や照明など、いろんな分野のプロフェッショナルがいたけれど、撮影とテクノロジーを横断して設計する役割というのは存在していなかったんです。だからそこを橋渡しするために、僕らが壁をぶち壊しまくってましたね。
富永こういう横断的な仕事をする時にクリエイティブで大切なことは「想像力+補完力」です。想像力というのは、自分で想像する力だけど、補完力というのは、専門領域の人同士の溝を埋める力みたいなものです。専門領域の人は、それぞれのパートに関しては完璧。ただ、それぞれのパートで理解度の違いが生じた時に、ストレスが溜まったり、無駄な時間が必要になったり、お互いに対する不理解ゆえに衝突が起きます。その際に、不理解を補正する知識と説明力が必要になります。
例えば、カメラマンとモーションキャプチャーチームの間には、生で写っている人と、スクリーンに映し出されている人の間に生じる、微妙なFPS(フレームレート)の違いがあったりして。ライティングの部分でも、リアルにある照明に対してCG側での光の当たり方の整合性を検証する力が必要になる。この時に、それぞれのプロフェッショナルに対して、補正値を伝える必要があります。めっちゃ細かいけれど、CGの世界とリアルの世界では、微妙に単位が違ったりする。ミリ単位で言う人とメートル単位で言う人の通訳になったりする必要もある。こういう、リアルとバーチャルを行き来する知識量と説明力が、最終的な仕上がりに影響を与えるかと思います。
【クリエイティブディレクションのルール#8】
想像力+補完力で言語やルールの違いを埋める

答えはひとつじゃない。柔軟に対応することで新しい道を切り開く。
最後の事例はMaxMaraの「I LOVE MAX MARA」。富永さんがプロデューサー、川村さんがクリエイティブディレクターとして関わり、阪急百貨店で開催される展示会全体のクリエイティブディレクションを手がけました。ただ、実現までにはいくつかのハードルがあったそうです。

川村当初のアイデアは、巨大なコートの中に入って内側にプロジェクションマッピングをするというものでした。でも、建物の中に巨大な建造物(コート)をつくるには建築基準法や消防法の壁にぶち当たったんです。しかしそこで完全に諦めてしまうと、そこに至るまでに積み上げたプロセスが無駄になってしまうので、コアとなるビッグアイデアを崩さずに、うまいピボットをして着地点を見つけるために企画を調整していきました。
富永ビッグアイデアが出た時に、それに固執するクリエイティブディレクターは多いけれど、本当に大事なのは柔軟性です。このケースのように、突飛なアイデアを思いついた時こそ、本当に実現できるのか話し合いながら実現性を探り、いざとなったら別の角度のアイデアを出し続けられる柔軟さがクリエイティブディレクターには必要だと思います。川村は本当に無茶を言うんですけど、最終的には柔軟で「だったらこうしたらどうでしょう」という引き出しがものすごく多いんです。
川村答えはひとつじゃないですし、そもそも答えがあるかどうかもわからない。みんなが驚くようなアイデアを高いクオリティで実現できるかどうかは、アイデアの発想そのものだけではなくて、それをどう組み立てて、どう実現していくかなど、様々なレイヤーの話があるんです。究極的にクリエイティブディレクターは、最終的な「実現の責任者」なんだと思いますね。
【クリエイティブディレクションのルール#9】
出したアイデアに固執せず、柔軟性を持つ

「何でもやる」ことへのジレンマと覚悟。
事例を通して、Whateverの具体的なクリエイションや、富永さんと川村さんそれぞれが考えるクリエイティブディレクションが明らかとなりました。最後は、会場からの質問に応答することに。
会場クリエイティブディレクターにとって重要なスキルは何ですか。
川村それはもちろん多岐にわたりますが、クリエイティブディレクターは高いレベルで「実現」させるための総責任者だと思うので、そのためにできる、あの手この手はすべてやる。たとえ企画を立てる力がなくとも、例えば、他人のアイデアでも「これは今まで実施されたことがない」と判断できたり、より正しい課題を発見できたり、現場スタッフの才能を引き出して育てられたりすれば、それは素晴らしいスキルだと思います。俯瞰的にプロジェクト全体を見られるのが、プロのクリエイティブディレクターですね。
富永重複しますが、役割はひとつではないということです。どんなに優秀な指揮者でも、誰も演奏してくれなかったらメロディーが奏でられない。チームワークの中で適切なメロディーを奏でられることが大事です。なので、チームのモチベーションを上げるためにも、それぞれ違う進み方・感じ方を補完して統一をはかることは重要ですね。僕自身は、ペース配分は人それぞれに任せるようなやり方です。それでも絶対にズレは生じてくるので、ズレが生じた時にしっかりと中継地点で判断することも重要な役割だと思います。
会場自社のブランディングについてはどう考えていますか。また、ブランディングには合わない依頼が来なくなってしまうなどの恐れはありますか。
川村この質問をした人は鋭い。事業領域は、本当はズバッと言えた方がいいんです。アプリの専門ですとか、ARが得意ですとか。「何でもやります」というと、逆に仕事が来にくいというジレンマはあります。Whateverの仕事は尖鋭化するのが難しいし、逆に何でもやるのが楽しい。だからそこはあえて覚悟を持って、そう言っています。
富永Whateverは「クリエイティブスタジオ」と呼んでいるのですが、立ち上げ時は「アイディエーションスタジオ」と名乗ろうと考えたこともあります。アイデアを大事にしていることを伝えたかったからなのですが、ただ、アイデアだけ考えて手を動かさない人だと思われては困る。考えたものに対してきちんと手を動かしてクラフトまでやり通せるということを伝える上で、「クリエイティブスタジオ」と言った方がしっくりくると思いました。それが今のところ僕たちのブランディングかなと思っています。
【クリエイティブディレクションのルール#10】
実現するためには、あの手この手すべてやる

クリエイティブディレクターはプロジェクトの全責任を持つ人。
最後の質問は「クリエイティブディレクターとプロデューサーの違い」について。2人の役割の違いや関係性ならではの視点から答えを探ります。
富永両者の違いについては、プロデューサーは「プロジェクトをベストな形で実現することの最終責任者」、クリエイティブディレクターは「プロジェクトをベストな品質で実現することの最終責任者」だと捉えています。どちらもある程度プロジェクトを俯瞰する視点は必要ですが、微妙に寄りと引きが違うんだと思います。僕自身はビジネス全体をゴールさせる点に重きを置いていますね。
僕はもともとクリエイティブディレクターになりたいと思っていたのですが、川村に出会って、もう少し広い領域で闘わないと敵わないなと考えたんです。というのも川村は、1ピクセル単位で細かく指示するようなディレクションをしていて、これがクラフトを突き進めるディレクターなのかと。その時はもう、クリエイティブディレクターとは一生名乗らないと思っていたほどです(笑)。
川村僕も以前はクリエイティブディレクターとプロデューサーの両方をやらざるを得なかったけれど、プロデューサーとしては富永には絶対に敵わない。今、一緒にやることでお互いの領域を分けながら、両方を見るということができています。その上で、クリエイティブディレクターとはプロジェクトのすべてのクオリティに対して責任を持つ人、総責任者として立つ人だと思っています。成功しても、失敗しても、その人の名前でジャッジされますから。
富永ただ、全員がクリエイティブディレクターを目指す必要はなくて、クリエイティブにもいろいろな側面や役割があるし、むしろ職人気質の人はその道を極めたらいいと思います。チームというのはそのためにあって、専門性と多様性の中で道を自由に選べるのが現代なんじゃないかな。
川村クリエイティブディレクションとは何かという問いに対しても、一言では答えられません。ただ、今日お話したクリエイティブディレクションのいろいろな側面の中で、みなさんにとってひとつでも「解」があればと思います。
【クリエイティブディレクションのルール#11】
プロジェクトをベストな品質で実現することに責任を持つ
数々の事例を通して紹介されたWhateverのクリエイティブディレクション。いずれにも共通しているのは、企画を実現させるためにあらゆる可能性を考慮する姿勢「Whatever(=何でも)」でした。今回は、大胆なプロジェクトの成功を支えてきたWhateverの確かな検証の積み重ねとクリエイティブに実直に向き合う姿勢が垣間見える貴重な講義となりました。
RELATED ARTICLE関連記事




























