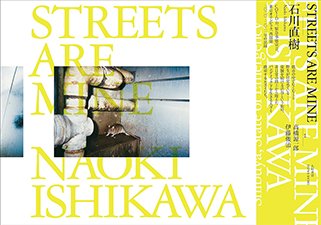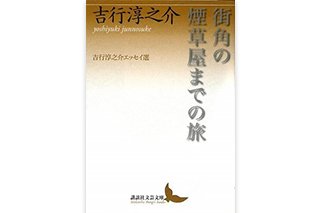INTERVIEW
155
Naoki Ishikawa / Photographer
石川直樹写真家
Naoki Ishikawa / Photographer
自分だけの尺度で街の新しい地図をつくってみる【前編】
常に未知な何かと出会えるように感覚を開いておく。
雑然とした群衆に紛れることの安心感。
六本木は、僕にとって案外馴染みのある街なんです。国立新美術館の展示を見るために足を運ぶことも多いですし、昔、西麻布にあったプロラボに毎日のように通ってフィルムの現像やプリントをしていた時期もあります。今は乃木坂にある別のラボによく行きますが、その時も六本木駅から歩いたりして。それから、六本木交差点近くのルノアールで仕事をすると、すごくはかどるんですよ。いろいろな職種の人がいろいろなことを話している、その会話がちょうどいいBGMになって、「みんな生きているなあ」とどこか安心する(笑)。海外にいる時はたくさんいる雑多な人々の中に溶け込んでいるけど、生まれ育った東京だと顔馴染みの人や行きつけの店とかがあるじゃないですか。すると、どうしても他人に気づかれるから、雑然とした場所で群衆の中にいることに逆に安心感を覚えるんです。
その昔、東京に雪が降った日、六本木の交差点を行き交う人をひたすら撮影したこともありました。どんな人が来るか、どんな動きをするかも読めない、そういう自分の意志ではコントロールできない状況が好きなんです。コロナ禍中は、2年間ずっと渋谷でネズミの写真を撮っていたのですが、まさにネズミも動きが読めないから面白かった。それらの写真は、『STREETS ARE MINE』という1冊にまとめましたが、六本木のネズミにもちょっと興味はあります(笑)。僕は思い通りにならないものに惹かれるし、偶然に出会いたいという思いが強い。写真って、そういう意図しないものを呼び寄せてしまうメディアでありますよね。
STREETS ARE MINE
2020年から2021年にかけて、石川さんが撮影した東京の街を記録。COVID19や緊急事態宣言、東京オリンピック、再開発......と、目まぐるしく変化する時代を捉えた写真集。カミュの『ペスト』に着想を得て渋谷の街の撮影を始め、非日常の路上を舞台にパンデミック下を生きる人々と、跳梁するネズミたちを捉えた。
想像を超えた出会いに遭遇したい。
偶然を大切にするのは、旅も同じ。旅は、人だけじゃなく、様々なモノや風景や歴史や文化と出会い、発見することだと思っています。自分にとっての未知の存在に出会い、身体で理解していきたい、と常に考えています。今の時代は分からないことがあると、スマホですぐ検索をして知ったつもりになっちゃうじゃないですか。でも僕は、自分の想像を超えたものに出会い、手触りを確かめながら自分の実感として咀嚼していく、世界のことを理解していくということを死ぬまで続けたい。それが、旅の本質じゃないかと思うんです。だから、旅先ではいつも「何でも見てみよう」という気持ちでいます。そこに行く大きな目的はあったとしても、そこにしがみつくわけじゃない。とにかく街の隅から隅まであらゆるものを見て、何かに反応して写真を撮りたいんです。
コロナ禍中はなかなか旅に出られず、山に登ることもできなかったのですが、2022年はダウラギリ、カンチェンジュンガ、K2、ブロードピーク、2023年はアンナプルナ、ナンガパルバット、ガッシャ―ブルムⅠ峰と、各年4つの山に登頂しました。自分の中で"チョロQ現象"って呼んでいるんですけど(笑)、2年間ずっとゼンマイが巻かれていて、それがコロナ禍が終わってポンッと勢いよく飛び出した感じで。高所登山を知らない方からすると、短い期間にそんなに高い山にいっぱい登るなんて、大変だって思うじゃないですか。でも、身体が高地に一度順応すると、連続で登った方が楽なんですよ。1年に1回の遠征だと、そのたびに順応しなきゃいけないけど、順応した状態なら山に着いてから案外サクサクと登れます。

旅人は常に異邦人。自分の価値観を持ち込まない。
頂上で「〇〇の山の頂上に立つことができて嬉しいです」などと言いながら自撮りした動画があるんですが、友人に見せると「嬉しそうに見えないね」って、よく言われるんです。僕の中ではめちゃくちゃ喜びを感じているのに、どうやら伝わりづらいみたいで(笑)。僕自身の表情では伝えられないかもしれませんが、ヒマラヤの8,000mを越える山々って本当にすごいんですよ。あれは遠くからじゃなく、ぜひ間近で一度見てもらいたい。簡単ではないかもしれませんが、できるなら標高5,000mのベースキャンプあたりから見てもらいたいなあ、といつも思います。K2やアンナプルナを間近で見ると、「なんだ、この巨大な塊は!」、「これが山なのか⁉」って大きな衝撃を受けると思います。
エベレスト遠征などのスタート地点になる街、ネパールのカトマンズは僕が世界で一番好きなところです。街も人で賑わっていて、いろんな国の料理が食べられるし、人も犬もみんな好き勝手に生きている感じがいいんですよ。雑然としていて、路地の一つひとつに人の生き方が垣間見えるのも好きです。
そうやって異文化の街へ行った際、現地で大切にするのは"郷に入っては郷に従え"の姿勢。旅人は常に異邦人で、向こうのコミュニティーに入らせてもらう立場なので、できる限りそこにいる人を尊重したい。だから、現地の文化に触れて、理解しようとする姿勢は、重要ですね。例えば、以前行った太平洋の小さな島では、みんながふんどしで生活していたので自分も同じようにふんどしで過ごし、その土地の人たちが食べているものを食べていた。それはアフガニスタンに行っても北極圏に行っても同じです。自分の価値観や常識を、頑なに持ち込むことは決してしないようにしています。
知っているつもりになっていないか?
旅もそうですが、新鮮な発見を得るためには、"知っているつもりにならない"ことが大切だと思います。先ほども少し話しましたが、何でもスマホで検索して分かったと思ってしまうと、周りに興味がなくなってしまう。例えば、今、僕の目の前にあるペットボトルには水が入っていて、その隣にあるのが紙切れで、それらが乗っているのが机ですよね。僕はこれらを分かっているつもりになっているから、何も反応をしない。しないというより、反応しようがない。でも、この水や紙、机などを初めて見た赤ちゃんは、「これは何だろう」と触ってみたり、舐めてみたり、紙を破ってみたりしながら世界を理解していく。そうやって反応できることは、すごく幸せなことなんじゃないか、とも思います。
年を重ねると、「今年も1年早かった」なんてよく言うじゃないですか。でも、それを言う人の多くはサラリーマンなどの大人たちで、子どもは一切言わない。ルーティンワークを続けている大人は、気づきや発見が少ないし、まわりの新しいことに関心をもたないから、時間が矢のように過ぎ去っていくんだと思います。一番の理想は、常に生まれたばかりのような状態で、世界と向き合うこと。でも、現実的にそれはすごく難しい。年を取っていくとみんなあらゆることを知っているつもりになって、反応しなくなってしまう。それを避けるためには、「知っているつもりにならない」ということを、頭の中に常に留め置くしかないんでしょうね。
みんな自分だけの街の地図を持っている。
海外から戻ってくると、旅先と東京に戻ってきた時との距離の感覚の違いが面白いなあ、と思います。山に登る時って、ベースキャンプまでものすごく長い距離を歩くんですよ。10kmくらいなんて平気で歩いているはず。その感覚で行くと、東京で生活している間、電車やバスに乗らなくても全部徒歩で行けちゃうなって思うんですよ。でも結局、都内にいるとそんなに歩きもしない。これって、その場その場でやっぱり身体感覚が変化しているんでしょうね。
僕の場合、旅先では歩いて動ける範囲から、街のスケールを把握している感じがあります。地図は情報量が多くて眺めるのが大好きなんですが、実際は異なる縮尺の自分だけの地図みたいなものを、みんなそれぞれが持っていると思うんです。例えば、僕が17歳の頃にインドに行った時、道に迷って現地のおばあちゃんに「ここに行きたいんだけど」って助けを求めたら、地図を書いてくれたんです。でも、その地図の通りに歩いているのに、全然目的地に着けなくて。なぜかと言ったら、それはおばあちゃんの記憶の地図だったから。要は通い慣れたよく知っている道はすごく大きく、短く書かれていて、逆に知らない道は細く、長めに書かれていた。実際の距離感や道の大きさと違うから、そりゃたどり着けないですよね(笑)。
インドのおばあちゃんのように、みんなもなんとなく自分の縮尺や馴染みの道なんかで街を把握しているでしょう。子どもだったら、この路地を入ったところに変なキーホルダーが落ちていたとか、あの公園に行くと野良犬がいるから近づかない、みたいな地図がある。小説家の吉行淳之介は、『街角の煙草屋までの旅』というエッセイを書いていますが、近所の煙草屋まで行くのも旅と捉えていた。そういう人それぞれの縮尺で捉えた世界って、すごく面白いですよね。人だけじゃなく、犬には犬の世界があるでしょうし、虫には虫の世界がある。僕は歩きながら、自分が反応したもの全部を写真に撮っているけど、それらが、自分が歩いた世界の地図になればいいな、と思っています。僕の写真は、石川直樹の地図そのものなんだ、と。
街角の煙草屋までの旅
「家から一歩外に出れば旅だ」と考えるヘンリー・ミラーに共感し、街角の煙草屋まで行くのも旅だと考えて、自分の住む都会を歩き回る。角度を変えて見えてくる旅の意味や風景を、吉行淳之介氏の豊かな感性と想像力で綴ったエッセイ。
撮影場所:国立新美術館
RELATED ARTICLE関連記事