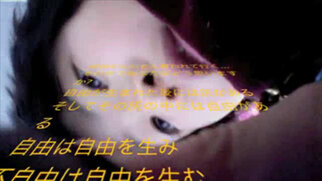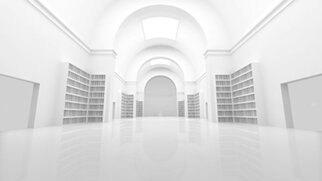INTERVIEW
127
Torajiro Aida / Artist
会田寅次郎芸術家
Torajiro Aida / Artist
『文化のインフラとなる、ゲーム図書館を』【前編】
あらゆるクリエイションに繋がるゲームを遊び尽くす場所。
update_2021.05.19
photo_yoshikuni nakagawa / text_akiko miyaura
ディスプレイの中の言葉が、現実世界の問題を知るきっかけになる。
親の影響もあってか、幼い頃からコンピューターがおもちゃという感覚で、小1くらいの時には、古本屋で買ったホームページ制作の本に夢中になっていました。それがテクノロジーやプログラミングに興味を持ったきっかけでしたね。ちゃんと作品として発表したという意味では、2015年の《TANTATATAN》がはじめて。もちろん今は「作品をつくっている」という感覚ではありますが、僕の場合、わりと自分のためにつくっている部分もあって。アーティストかエンジニアかみたいな肩書きを問われると、答えるのが難しいんです。作品のベースにはゲームで遊んでいる体験があって、そういう意味では現実から別の世界を探究する、"遊び人"というのがしっくりくるかも(笑)。
《TANTATATAN》
世界そのものをつくろうとの試みで、Chim↑Pom等若いアーティストらと3歳~11歳までの子どもの映像をまとめた。東京都現代美術館で2015年に開催された『おとなもこどもも考える ここは誰の場所?』で上演された、寅次郎さんの構想、制作総指揮による映像作品。
© Torajiro Aida
今回『Media Ambition Tokyo 2021(MAT2021)』で展示している《ero 法令検索》もゲーム的な要素を持った作品。その名の通り、日本の法令をコンセプトにしています。通常法令、法律は紙に印刷されていますが、その文面って白と黒だけじゃないですか。それだと無機質で、面白みがない。例えば、グーテンベルグの聖書みたいな昔の印刷物って、挿絵や色でデコレーションされているんですよね。それと同じようにいろんな色をつけて、楽しくしたら面白いんじゃないかというところから、今回の作品に繋がっていきました。
Media Ambition Tokyo 2021
中村勇吾、落合陽一、チームラボなどのアーティストが参加し、最先端のテクノロジーカルチャーを実験的なアプローチで都市実装するショーケース。コロナ禍において「この瞬間を次の時代へ橋渡しするために意識を通わせ、想像し、新たな羅針盤を創造する。Media Ambition Tokyoが描く暗中模索が、次のバトンとなるように」との思いで9回目となる2021年度の展覧会を開催する。2021年6月8日(火)まで、六本木ヒルズ 森タワー 52階の東京シティビューにて開催。
イベント詳細はこちら
《ero 法令検索》
日本の法令全文に、挿絵や色を加えた異空間を漂う体験ができる作品。関係する法律を10個程度まとめて並び替え、ランダムにモニターに表示。空間を移動するためのツールでもある足元のコントローラーは、「20年ほど前の既製品。今回のために中古を買って作品の一部に使った」そう。背景には加工でぼやけさせた政治家の顔を入れ、本人がアレンジした『君が代』のトラックをゲーム音のように流すなど、細部まで自身で手掛けている。
© Torajiro Aida
《ero 法令検索》はインタラクティブな作品で、足で踏むマット状のコントローラーを操作すると、目の前のディスプレイ内の空間を歩いて移動している体感を得ることができます。挿絵や色、絵文字を加えた法律の文面が映し出されるので、色のある空間を探索しているような感覚を味わえます。
ディスプレイの見た目は、グラフっぽくしているんです。文面に同じ単語が現れると、単語同士を線で結び付けるというルールをつくっていて。単語が10個、20個と線で繋がると、精密なグラフのようになっていく。線もシンプルな直線では変化がないので、自分で書いた抽象的な絵を取り込んで線として表示していますが、やがて雲のような形になっていくのがすごく面白いんです。
法律は、あらゆる事象を扱っているもの。そう考えると、辞書みたいなものだと思うんです。作品を通じて、法律の中にある単語に出合うことで、現実世界の問題に気づくきっかけになればいいなという思いもあります。辞書を無作為にパッと開いた時に、たまたま知らない単語に出合うように、偶然出合った法律上の言葉が考えるきっかけになればいいな、と。
テクノロジーは、もっと民主的に解放できるはず。
法律ってどこか技術っぽくないですか? 専門家にしか分からないスペシフィックなものにもかかわらず、あらゆるものと繋がっている。それが"科学技術"のようだな、と僕は思っているんですけど、科学技術であるテクノロジーって、まだまだ解放されていないというか、民主的じゃないところがあると感じるんですね。だからこそ、そこをアートとして見せたいなとも思うんです。
今回もそうですが、作品のコンセプトは基本思いつき(笑)。とはいえ、何かしら日常で感じていることが、ヒントになっているとは思います。例えば、今回は大学生活での実感がきっかけのひとつ。僕が通う早稲田大学は大きな大学なので、さまざまな仕組みがシステマティックになっているんです。何か手続きをしようと思ったら、ひとつの事務所で完結できるわけじゃなくて、それぞれ部署が分かれている。
インターネット上の手続きも官僚的なシステムになっていて、そこが不便でもありました。さらにコロナ禍で人との関わりがないので、追い打ちをかけるように官僚主義的なものにネガティブな感情が湧いてきて。そこで、法律というコンセプトでやってみようと今回の構想に辿り着いたんです。

時間感覚の違い、ゲーム的視点で都市を見てみる。
日常がインスピレーションになるという意味では、街もそのひとつかもしれません。普段は自転車で通学しているんですけど、自転車に乗っている時と、歩いている時の時間の感覚って違いませんか? ふと自転車を降りて、ふらっと歩いてみると全然世界が違って見える。そういう時間の移り変わりは、普段から考えているかもしれないですね。
自転車で走っていると、東京の街って「こんな急な坂で大丈夫なのかな」って思うことがあるんですよ。大通りでも高低差が激しく、近道をしようと脇道に入るとさらに地獄(笑)。45度の傾斜じゃないかと思うほど急な坂道が出てきて、自転車で登るのはかなり大変です。でも、その断崖絶壁な感じが東京っぽさでもある気がします。
リアルな街も好きですが、ゲームの中の空間も好きですね。中でも、『Cypher』というゲームはすごく衝撃的でした。バーチャルの美術館のような空間があって、壁に書かれた暗号を解いていくのですが、その暗号が美術館のタイトルやキャプションのように見えるんです。暗号は、誰もクリアできないんじゃないかというくらい難解で。でも、その空間が楽しくて、たまにふらっと覗きたくなります。
あと、ゲームに関して自分でも不思議なのが、夢の中では現実とゲームの世界の境界線がなくなること。画面は二次元なのに、キーボードを叩く自分の手は映らず、心で「上!」と思ったらキャラクターが上に動くみたいな。そんな夢をよく見ます。考えてみると、ゲームと現実に境界線を引くのって難しくないですか? もちろん自分が今いる世界が現実だと認識しているけれど、ゲームをしている時はゲームが現実。僕は日常の4割くらいゲームの中で過ごしている感覚があって、どこからがリアルで、どこからがゲームかという感覚もないのかもしれません。
グラフで表される、数学的な視点からこぼれ落ちるもの。
もうひとつ、世の中の見方として僕の中ではグラフがキーになっています。今の世の中って大体はグラフで表せるんじゃないかと思っていて。いわゆる棒グラフとか線グラフではなくて、バスや電車の路線図のような形式で、様々なものを連結させて関連性を表すグラフ理論的なもの。例えば宇宙なら、宇宙には銀河団があって、銀河団には銀河があってと、入れ子の構造を表すことができる。実際の宇宙は空間なので、形としては平面のグラフとは違うけれど、人間はそうやって物事を認識するんですよね。
ただ、グラフには落とし穴もあって。「人間は二つに分かれます」、「男と女です」とグラフで示せるけど、果たして男と女に分けてもいいのかという疑問は残ります。実際に多種多様な人がいるわけで、二つの性では表せないこともある。でも、数学的な視点ではこれとこれは同じだから、この違いは無視していいという思考になります。酷な話ですが、それが人間の理解の仕方。そうやって微妙な違いを覆い隠してしまうことが、技術の危険性にもなると思うんです。完全な形を理解するには、人間は不完全。テクノロジーを扱う上で、それを頭に入れておくことは重要なことだと思います。
それに、大体のことは表せるとはいえ、単にグラフを見せられたところで面白くはないじゃないですか。それだと現実世界に働きかける力は弱い。そこで重要になるのが、いかに現実世界にあるものと結びつけるか。僕の大きなテーマとはまさに、現実世界と技術をどう繋げるかということであり、繋げる方法のひとつがアートだと思っています。アートのイメージを使って、まったく違うもの同士を結びつけることで、テクノロジーの前提知識がない人でも、ひとつ理解が進むと思うんです。
RELATED ARTICLE関連記事