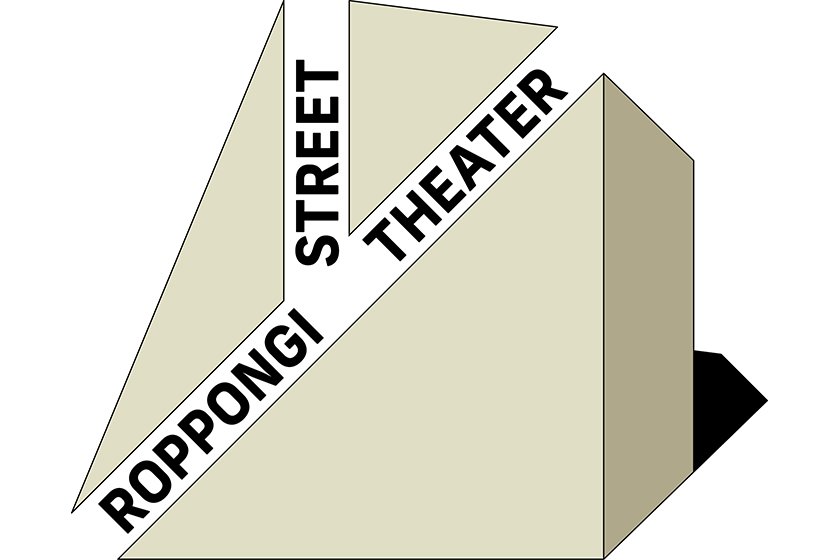「ROPPONGI STREET THEATER」第6回 PROJECT REPORT「流動的な場所で響く異色の音色」
六本木の街なかにある建築やアートを舞台に変身させる「ROPPONGI STREET THEATER」。劇場内で見ることの多いパフォーミングアーツが、誰でも楽しむことのできるパブリックスペースに飛び出し、建築・アートとパフォーマー、そして、観客をつなぎます。
第6回目となる今回は、『六本木アートナイト2024』のプログラムとして、音楽家の蓮沼執太さんとのコラボレーションが実現。9月27日(金)には、蓮沼さんがコンダクトする、現代版フィルハーモニック・ポップ・オーケストラ「蓮沼執太フィル」が、東京ミッドタウンの《キャノピー・スクエア》を舞台に大規模なパフォーマンスを行いました。また、翌日に行われた、「蓮沼執太チーム」による安田侃の彫刻《妙夢》での演奏も、その場所だからこそ表現できる音楽との共鳴、そして音の響きが誕生しました。
過去のROPPONGI STREET THEATERの様子はこちら


©Kanade Hamamoto
この場所だからこそ、生まれた音の響き。
2024年9月27日、「蓮沼執太フィル」のパフォーマンスをひと目見ようと集まった多くの観客が、開演前から東京ミッドタウン《キャノピー・スクエア》に設置された特設ステージを囲んでいました。
東京ミッドタウンの4つの建物に囲まれ、ガラスの天蓋で覆われた《キャノピー・スクエア》について、蓮沼さんは「1,800枚の全部違う形のガラスが連なって、ひとつの屋根になっていますが、我々フィルのメンバーも全員バラバラで、音楽するときだけひとつになる。そういう類似性みたいなのがあると、合わさったときに大きな力になるんですよね。それに、蓮沼執太フィルの音楽的にも、アンサンブルというスタイルが合う場所だなと思いました」と話します。
キャノピー・スクエア
森をイメージした柱に支えられた大きな屋根。地上25メートルの高さにある街のシンボルのひとつ。約1,800枚のガラスが使用され、一枚一枚全て異なる形状でつくられている。設計を手掛けたのは、大英博物館のグレートコートも手掛けた、建築構造設計事務所ビューロ・ハッポルド。
「この場所は、まず、足元の素材が固いので、硬音の反射が特徴的で、楽器も中域と高域が硬くなるんです。それに天蓋が高い分、すごくエコーがあって響くんですよ。当日の昼に行った公開リハーサルでも、マリンバなんかは特にいい音が出ていましたし、ドラムもカッコ良く響いていて、個人的に好きな音像でした」

時計の針が開演の18時を指すと会場は大きな拍手に迎えられ、フィルのメンバーが姿を現します。ドラムやマリンバなどの打楽器、サックスやフルートなどの管楽器、バイオリンやギター、ベースといった弦楽器を手に、蓮沼さんのキーボードを中心に円を描くように着席。「みなさん、こんばんは。1時間くらいライブしたいと思いますので、楽しんでください」と蓮沼さんが語りかけると、カウントと同時にゆったりとした心地よい生演奏が東京ミッドタウンに響き渡りました。

第6回ROPPONGI STREET THEATER
2024年9月27日、『六本木アートナイト2024』のプログラムとして、東京ミッドタウンにある建築《キャノピー・スクエア》を舞台に、音楽家の蓮沼執太率いる蓮沼執太フィルがライブパフォーマンスを実現。翌9月28日には、安田侃による彫刻作品《妙夢》とのコラボレーションパフォーマンスを行った。
https://6mirai.tokyo-midtown.com/event/rst_06/
蓮沼執太フィル
2010年に結成し、蓮沼執太がコンダクトする、現代版フィルハーモニック・ポップ・オーケストラ。2014年にアルバム『時が奏でる』、2018年に『アントロポセン』をリリース。11月には新メンバー10名を追加した26名の「蓮沼執太フルフィル」を始動させ、2023年にはアルバム『symphil』をリリースした。また、2019年にはフジロックフェスティバルへの出演、⽇⽐⾕野外⼤⾳楽堂で公演。2021年には、Bunkamuraのオーチャードホールにて『○→○』を公演し、「Eco Echo」リリースツアーを行った。2023年には東京オペラシティコンサートホール:タケミツメモリアルにて『ミュージック・トゥデイ』を開催。
メンバー:蓮沼執太、石塚周太、イトケン、大谷能生、尾嶋優、音無史哉、葛西敏彦、K-Ta、小林うてな、ゴンドウトモヒコ、斉藤亮輔、千葉広樹、手島絵里子、宮地夏海、三浦千明
さまざまな楽器の音が徐々に重なり、音のひと粒ひと粒を際立たせるような鍵盤やギター、フルートの美しいメロディーラインなどが響き、再びフィナーレに向かって加速していくーー。メリハリのあるサウンドと楽曲構成で、オープニング曲の『Triooo - VOL』から一気に観客を音楽の世界に引き込みました。

次に、蓮沼さんの透明感のあるボーカルで始まる『ONEMAN』が披露されました。軽快なリズムを刻むドラム、マリンバの優しい響きに、自然と体を揺らす観客。さらに、蓮沼さんが5拍子を刻みフィルをコンダクトすると、『Zero Concerto』のイントロの幻想的な音が徐々に立ち上がっていきます。ちょうど開演頃に降り始めた静かな雨と相まり、優しい柔らかな響きが空間を優しく包みました。
「普段から、僕がこだわっているのは「響き」です。多くの楽器は、出せる音域って決まっているじゃないですか。その中で旋律やリズムを追求するのもいいのですが、楽器からどうやって外へ出て音になり、衰退していくかが気になって。たとえば、フィルのように演奏者が複数人いるときは、どういうふうに響きが重なったり、バラバラに音を出したりするのか興味があるんです。特にライブ・パフォーマンスは視覚的要素が強いからこそ、響きが重要だと考えてます。もし変な顔をしながらドラムを叩いている人がいたら、やっぱり目がいってしまいますよね(笑)。響きはそういう視覚的なものとは真逆で、情報が少なく些細なもの。だから、こだわらないと音楽的にならないんです」
こだわった響きたちに導かれるように、曲を重ねるごとに大きくなる観客の輪。通りかかりの人々や、ガレリア3階の「IDÉE CAFÉ PARC」のテラスからステージをのぞき込む人など、さまざまな角度からフィルに視線が注がれます。そんな《キャノピー・スクエア》の場所性について、蓮沼さんは「人が立ち止まる場所ではなく、常に流動的な感じで面白いですよね。パブリックな場所なので、たくさんの視線を感じるし、だからこその特別感や緊張感もありました」と話します。

「そこに我々の身体と楽器があるだけで、居合わせた人は物質的に『なんだ、なんだ?』となるはず。音楽になっていないのに、音楽的な意味性みたいなものが生まれるというか。さらに音を出すと、目には見えないけれど、波動や空気振動で音が聞こえてきて、かつ演奏することで体が動いてパフォーミングになる。我々は生きていて、音が出せて、動いていて、物質性もある」
パブリックスペースで奏でる音が、街の一部になる。
『Meeting Place』が始まると、蓮沼さんはイスから立ち上がり、フュージョンされたような自由な音に合わせて体を揺らし始めました。ぐるりと辺りを見回し、人々の雰囲気を感じ取っているようにも見えます。
「パフォーマンス中に観客の表情や雰囲気を見たりします。それこそ、ライブハウスでパフォーマンスしていた昔から、観客の表情をよく見るようにしていました。だからといって何かを変えるわけではないんですが(笑)、聴く人一人一人、違う状況を作れる環境がベストだと思っているので、こういう感じで、今この環境にいるんだろうなと確認する作業みたいなものです。やっぱり聴く人がいないと、音楽は結ばれない。音を出している人が一番というわけではなく、聴く人あっての音楽ということを大事にしています」

また、「ROPPONGI STREET THEATER」はパブリックスペースに飛び出し、建築、アートとパフォーマー、観客を繋ぐことがテーマ。《キャノピー・スクエア》という建築物とのコラボレーションについて、「この空間で音を出すだけで、自然とコラボレーションになる」と考えていたと彼は言います。
「頭でっかちにコンセプトを考えるのではなく、街の一部になれるといいな、という思いで演奏していました。シンプルに自分の作ったものが、街で流れているような感覚。そういう音楽って、都市には必要だと思うんです。ただ流すのではなく、演奏する位置や、見られ方も考えました。今回は円形になってのパフォーマンスだったので、場所によっていろんな見方ができ、音の聞こえ方も変わります。しもてに行けばホーンの音を、かみてで聞くとマリンバの音が強く聞こえるかもしれない。つくっている身としては、そういう視覚と聴覚の関係性だとか、環境みたいなものを踏まえて、どう届けられるかを考えていました」

余白のある楽曲が、フィルをしらない人たちを引き寄せる。
ライブ中盤に差し掛かるころには、他人同士である観客に一体感が生まれていました。蓮沼さんは「ただ演奏を見てもらうだけでなく、《キャノピー・スクエア》という空間で演奏する出来事をつくっている感じなんです。もちろん何をするかも大切ですけど、フィルという環境があって、それをどう空間やシチュエーションにインストールしてくかが大事」と話していましたが、その「出来事」を共有しながら輪を囲み、同じ体験をすることで生まれたつながりが、今回のイベントにありました。
パフォーマンスは、ポップな爽快さを感じさせる『SoulOsci』へ。徐々に音が複雑に交わり、曲の終盤には意図的に奏でられたハウリングが不思議な空気感を漂わせます。観客の感動が伝わる拍手のあと、一瞬の静寂を経て蓮沼さんの温かな歌声で『テレポート』が始まりました。跳ねるようなホーンとバイオリンの柔らかな旋律、マリンバの軽やかなリフが続く中、だんだんと音の体積が増していきます。荘厳な旋律と力強いホーンの音から始まり、4つ打ちのリズムが響く『起点』は、語るようなボーカルとユニークなギターの音の掛け合いも印象的。今回の選曲は、「昔の曲が少し多め」と、蓮沼さん。

「《キャノピー・スクエア》での響きや空間性を意識したとき、僕らのレパートリーの中でも、昔の曲のほうが合うなと思ったんです。というのも、最近の曲はいろんな要素が詰まっているけれど、昔の曲はちょっとコンポジションのすき間が多いんですよ。こういうパブリックな場でのパフォーマンスは、情報量の多いドーンとした塊みたいな音楽より、少しすき間がある曲のほうが余白があって、知らない人でも入りやすいと思うんです」
そして、次の楽曲『NEW』の前に蓮沼さんはさっと立ち上がり、ギターの斉藤亮輔さんにトーンチャイムを手渡し。軽快なリズムに乗せ、トーンチャイムの音色を鳴らすパフォーミングで観客を引き込みます。いよいよ、ラストソング『Eco Echo』へ。蓮沼執太フィルらしさをより存分に感じられる、ユーフォニアムと雅楽器の笙、そして電子楽器とアナログ楽器の響きなど、異色の音で締め括られました。

ふと会場を見渡すと、すき間がなく人がひしめき合っている状態に。メンバーがはけることができず、「出られなくなっちゃったので、アンコールやります!」と蓮沼さんが茶目っ気たっぷりに伝えると、会場から拍手とともに喜びの歓声が上がりました。最後に披露したのは、『Earphone & Headphone in my Head - PLAY0』。アンサンブルの魅力を濃縮した、ポジティブなエネルギーを感じる楽曲が最後に披露されました。メンバーが去るまで、長い長い拍手が続きます。東京ミッドタウンの一角に突如現れた異世界がパッと消えたように人々が散り、《キャノピー・スクエア》はライブの余韻を残しながらも、非日常から日常に戻っていきます。

アート作品をつくるためのレコーディングから、音楽制作への道のり。
これまでも、さまざまなパブリックスペースでパフォーマンスを行ってきた蓮沼さん。過去の取り組みの中でも「Ginza Sony Park」でゲリラ的に行ったライブは、記憶に残っているもののひとつだと言います。
「本当に予告なしに、ゲリラ的に蓮沼執太フィルのライブをしたんです。いきなり始まることも、僕らを知らない通りがかりの人がいるという状況も、面白い体験でした。あと、その場でつくられる生の音って、やっぱりいいものだなと思うんです。今は録音技術が進んで、お店とかでもレコーディングされた音がBGMとして流れているじゃないですか。それも悪くないけど、その場でつくられる生の音を聴くほうが、きっと心にも体にもいいと思うんです」
「音楽にはプロとかアマチュアの概念は無いと思っています。街で演奏している弾き語りのミュージシャンにもそういえるでしょう。だから、どんどんストリートに出てやった方がいいと思いますよ。僕の場合、作品をつくるために音をレコーディングし始めたのがきっかけで、音楽の演奏が活動のスタートではないんです。そういう意味では今、21_21 DESIGN SIGHTでやっている『ゴミうんち展』に出展している作品のほうが、僕の原点といえます」
『ゴミうんち展』
身の回りから宇宙までを見渡し、さまざまな「ゴミうんち」を扱う。ゴミうんちという新しい概念をきっかけに、人工物のデザインも同じようにできないのかと考えた本展は、世界の循環に向き合う実験の場でもある。21_21 DESIGN SIGHTギャラリー1&2にて、2024年9月27日(金)から2025年2月16日(日)まで開催中。
『ゴミうんち展』には、本展覧会ディレクターであり、21_21 DESIGN SIGHTの館長でもある佐藤卓さんが縁となり、企画から参加することになったそう。蓮沼さんは、もう一人のディレクター・文化人類学者の竹村眞一さんのファンであったため、「今回、ご一緒させていただけて、すごく光栄」だと笑顔を見せます。
「僕の作品《pooploop un-compositions》は、今まで取り組んできたインスタレーションに、循環という今回の『ゴミうんち展』のテーマを取り入れてつくりました。会場内に散らばった4つの作品から成り立っている《pooploop un-compositions》は、樹木が水を吸い上げる音や、東京ミッドタウン内のゴミ箱を奏でた音が鳴ったり、消えたりしていて。4つ全部を合わせて、ひとつの音、響きとして届くようになっています」
楽器ではないものに触れて音を出すことが、もともと得意だという蓮沼さん。今の蓮沼執太チームや蓮沼執太フィルのスタイルにたどり着くまでには、長い道のりがあったそうです。
蓮沼執太チーム
2008年の『POP OOGA』のリリースパーティのために結成された、5人編成のバンド。蓮沼執太フィルの母体でもあり、メンバーは蓮沼執太、石塚周太(G)、斉藤亮輔(G)、イトケン(Dr)、Jimanica(Dr)。
©Kanade Hamamoto
「今となっては作曲をして楽器で音楽を奏で、歌も歌っていますけど、いきなりこの形になったわけではなくて。たとえば、パフォーマンスをするごとに、ここでこうすると、こんな音になるんだ、と失敗や発見をしては経験値を重ね、次は自分の歌を入れるといいかもしれない、とトライをしたり。その連続で自然と領域が広がって、今のチームやフィルという形につながっていきました」

チームとフィルは、単純にスケール感が違うだけでなく、音楽の楽しみ方も異なると言います。
「フィルぐらいの人数になると、完全にスコアがあって合奏してるので、即興的な要素は少ないです。それに対して、チームは人数が少ない分、もう少し自由にセッション的にやれるんですよね。たとえば、フィルの曲をチームでやるときに、スコアを見ないようにして、ハンドサインだけで演奏を進めたり。その自由さを楽しんでやれるのがチームなんです。一方、いろんな人が集まりいろんなジャンルが入った音楽をやる楽しさを得られるのはフィル。ジャズ畑の人もいれば、もともとクラシカルな音楽をやっている人もいます」
人が演奏する生の音は、脳内や体の栄養になる。
作曲や演奏といった音楽的な活動と、アート作品をつくること。それぞれのインスピレーションは、どんなインプットから生まれるのかも気になります。
「どちらも、インスピレーションの元は同じかもしれません。インスピレーションの種って、いたるところにあるじゃないですか。音でいうのであれば、たまたま入った会議室のクーラーの音が良かったとか、コンサートの音が良かったとか。いろんな場面でインプットってできると思うんです。でも、インプットとアウトプットの考えは以前と比べ変化したかもしれないです。昔はインプットもアウトプットも同じだと思っていましたが、最近は何かをつくっているときはインプットするより、"枯れるまで"出し切るようになりました。僕の場合、ゴールを決めてそこへ向けて何かをつくるのではなく、都度形を変えて、どこに行くかわからないみたいなクリエイションを楽しんでいるんです。だから、全部出し切って、よし、やった! と感じられたときが完成なんです。すると、次なる何かがまたやってきて、次のクリエイションに進もう、となるんですよ」
パブリックスペースにおける音楽について、蓮沼さんはどんなことを感じているのでしょうか。

「最近は、環境音楽と呼ばれる音楽ジャンルが再評価されたりしていて、アンビエントには敏感な方も増えていると思います。パブリックスペースの音に関しては、もう少し根本的なこと変えないと、味気ないものになってしまうんじゃないかとも感じています。街中にストリートピアノを置けばいいっていう話でもないし、どこかでレコーディングした水の音を無作為に流せばいいということでもない。結局、それは本物ではありません。そういう表面的なことより、都市は都市なりに嘘のない本物を目指すほうがいいんじゃないかな。街では、視覚がどうしても優先されがちで、聴覚は後回しになってしまいますよね。本当はパブリックスペースのアートくらい音や音楽が優先されてもいいのでは、と思います。それこそ、『ROPPONGI STREET THEATER』のようにパブリックな場で行われるイベントは意味がありますよね。発表会みたいなかしこまった場だとハードルが上がってしまうので、たまたま通りかかって偶然出会うくらいがちょうどいい。それこそ、公開リハーサルくらい力が抜けた自由さで、生演奏に触れられるとよりいいんじゃないかと感じています」
音楽の未来、そして、都市がよりクリエイティブになるために、音楽をどのように取り入れ、活用していくのか。蓮沼さんは、生の音へのこだわりを語ります。
「地域に根付いた音って、あるじゃないですか。たとえば、京都の祇園祭の練習をしているときに聞こえてくる音って、僕は通りがかりに耳にするだけでも気持ちが盛り上がるんです。そうやって自然発生的に生まれたあるべきものが、どんどんなくなっているけれど、六本木に来れば六本木らしい音、銀座に行ったら銀座らしい音が聞こえてくるみたいな、個性が出るといいなとは思います。現代は都市の音が均質化されていて、どこに行ってもほぼ同じ音が聞こえてきますよね。昔は夜の池の音を聞きに行って、「いい音だね」なんて言って楽しんだり、リラックスしたりしていたと思うんです。自然を感じられる場所では、森の音とか海の音といった音の情報がすごく多いけど、ことさら都市はそういう要素が削ぎ落とされ、ノイズに溢れていて音環境としては厳しいと感じます。ただ、幸い人間の耳は意識的なので、自分の聞きたい音を聞くことができる。自然の音に触れにくい都市であれば、人間が演奏している生の音を意識的に聞くのがいいんじゃないかなと思います。それって現代的な生活の中で、有機野菜とかビタミンを摂取する感覚と似ているのかもしれないですね」
ART & ARCHITECTURE TRIP
ROPPONGI STREET THEATERで舞台となったアート・建築に関連した、日本や世界で訪れたいスポットをご紹介するコラム。今回は、11月30日に蓮沼さんがライブを行う渋谷の「WWW」を紹介します。
今回のインタビューでも、キーワードとして出てきた「響き」。蓮沼さんが「とても好きな響きがする場所」のひとつとして挙げるのが、渋谷のライブハウス「WWW」です。もともと「ミニシアター・シネマライズ」として営業していた映画館が閉鎖したのち、跡地を改修してつくられたライブハウスで、音響や照明なども国内最高レベル。蓮沼さんの「響き」の正体を、ぜひ体感してみてください。公演タイトルの「SCP」(Sing、Club、Pianoの頭文字)をテーマにした3部構成で、「S」ではイトケンさん(Dr)と石塚周太さん(G, B)とのトリオ編成で歌モノを、「C」では立体音響の電子音によるクラブセット、「P」ではピアノソロの披露を予定しています。
住所:〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町13-17 シネマライズビル B1F
ABOUT ROPPONGI STREET THEATER
彫刻家 安田侃さんへのクリエイターインタビューでの「東京ミッドタウンのパブリックアート《意心帰》の周りでコンサートを」というアイデアからヒントを得たプロジェクト「ROPPONGI STREET THEATER」。
六本木の街なかにある建築やアートが舞台に変身。劇場内で見ることが多いパフォーミングアーツが、誰でも楽しむことのできるパブリックスペースに飛び出し、建築・アートとパフォーマー、そして、観客をつなぎます。
▼安田侃さん(彫刻家)インタビューはこちら:
クリエイターインタビュー #122
安田侃(彫刻家) https://6mirai.tokyo-midtown.com/interview/122_01/
RELATED ARTICLE関連記事