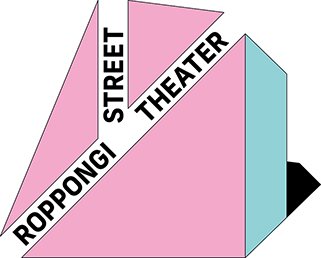「ROPPONGI STREET THEATER」第5回 PROJECT REPORT「電磁音楽とダンスによって織り成されるストリート劇場」
六本木の街なかにある建築やアートを舞台に変身させる「ROPPONGI STREET THEATER」。劇場内で見ることが多いパフォーミングアーツが、誰でも楽しむことのできるパブリックスペースに飛び出し、建築・アートとパフォーマー、そして観客をつなぎます。
第5回目となった今回は、ファッションとデザインの祭典「Tokyo Creative Salon」と連動し、彫刻作品《意心帰》を舞台に、熊川哲也さんが率いるK-BALLET TOKYO(旧K-BALLET COMPANY)とBunkamuraによる新たなダンスプロジェクト「K-BALLET Opto(Kバレエ・オプト)」とコラボレーション。2024年4月27日(土)から4月29日(月・祝)に上演予定のKバレエ・オプトによる最新作 『シンデレラの家』のエッセンスが凝縮された1日限りの特別パフォーマンスを実施しました。古物家電を新たな楽器へと蘇らせる稀代の音楽家、和田永が率いる楽団「エレクトロニコス・ファンタスティコス!」を中心に、日本を代表するダンサー酒井はな、そしてKバレエ・オプトのダンサーが彫刻作品《意心帰》を前に祝祭を繰り広げました。
過去のROPPONGI STREET THEATERの様子はこちら

日常を『ハッキング』して、その場所をステージに。
2024年3月23日。安田侃さんの彫刻作品《意心帰》をステージに登場したのは、和田永さんが主宰する楽団「エレクトロニコス・ファンタスティコス!」。役割を終えた電化製品を新たな電磁楽器へと蘇生させるオーケストラです。奏でられる音楽にあわせて、日本を代表するバレエダンサー酒井はなさんをはじめとするKバレエ・オプトのダンサーがダンスパフォーマンスを繰り広げます。
扇風機やブラウン管テレビなどの古びた電化製品が電磁楽器に生まれ変わり、祭囃子のような音楽が生み出されます。音色に吸い寄せられるように観客が集まってきました。《意心帰》が舞台装置に変身。ダンサーたちによる、即興的なダンスに観客も魅了されます。
ROPPONGI STREET THEATER #05
2024年3月23日、東京ミッドタウンにある安田侃さんによる彫刻作品《意心帰》を舞台に、和田永さんが率いる古物家電を新たな楽器へと蘇らせる楽団「エレクトロニコス・ファンタスティコス!」とダンサー酒井はなさん、Kバレエ・オプトによるコラボレーション・パフォーマンスが実現。
https://6mirai.tokyo-midtown.com/event/rst_05
K-BALLET Opto
K-BALLET TOKYOとBunkamuraが2022年に立ち上げた新プロジェクト。創立から四半世紀、芸術監督熊川哲也の下で豪華絢爛な古典バレエの全幕作品を生み出してきたK-BALLETが「芸術がいかに社会にその価値を還元していくか」という命題に応えるべく、今を生きる私たちが共感しうる"時代性のある新作"を届けるためにスタートした。本プロジェクトではK-BALLETのスターたちの出演をはじめ、世界の最前線をゆく振付家の起用や、他ジャンルのアーティストとのコラボレーションを意欲的に行うことで、ダンスのより多角的な魅力と深層を発見し、より多くの方々に鮮烈なライブ体験を提供していく。
© Hajime Watanabe
DIRECTOR/CHOREOGRAPHER:ジュゼッペ・スポッタ
振付家。 2002年にバレット・ディ・ローマに入団。2004年アテルバレットに参加。在籍中、当時の芸術監督マウロ・ビゴンゼッティの指導のもと、イリ・キリアン、オハッド・ナハリンらの作品を踊る。その後ドイツへ渡り、ゴーティエ・ダンスに入団。2010年ヘッセン州立バレエ団に入団、芸術監督のシュテファン・トスに感銘を受け、振付活動を始める。2011年トス振付『Blaubart』に出演後、ドイツで最高峰の芸術賞である「ファウスト」賞受賞。同年ハノーバー国際振付コンクール2位入賞。2019年よりMiRダンス・カンパニーゲルセンキルヒェンの芸術監督。ヨーロッパで最注目の若き俊英振付家。
© Nadir Bonazzi
PERFORMER:和田永
アーティスト、音楽家。大学在籍中より音楽と美術の領域で活動を開始。2009年よりOpen Reel Ensemble、Braun Tube Jazz Bandとして活動。2015年より古い電化製品から新たな「電磁楽器」を創作しオーケストラを形作るプロジェクト「エレクトロニコス・ファンタスティコス!」を始動、第68回芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞。現代アートの旗手として彼のパフォーマンスは常に注目を集めるが、今作では特に音楽家としてのずば抜けた閃きが発揮される機会となるに違いない。
© Florian Voggeneder
PERFORMER:酒井はな
ダンサー。93年牧阿佐美バレヱ団入団、18才で『くるみ割り人形』主役デビュー。97年開場とともに新国立劇場開場バレエ団に移り、柿落とし公演『眠れる森の美女』にて森下洋子、吉田都と競演。以降同団プリンシパルとして数々の初演を含む主演を務める。優れた表現力と高い技術に品格の備わった、日本を代表するバレエダンサー。クラシックバレエを中心にコンテンポラリーダンスやミュージカルにも出演。2013年島地保武と共にダンス・ユニットAltneu<アルトノイ>を立ち上げる。レパートリーは古典バレエから岡田利規等の現代作品まで幅広い。2009年芸術選奨文部科学大臣賞、2015年第35回ニムラ舞踊賞、2017年紫綬褒章、2018年第39回橘秋子賞特別賞、2020年東京新聞舞踊芸術賞受賞。
洗足学園音楽大学客員教授、DaBYゲストアーティスト。
© Tomohide Ikeya
パフォーマンスを行ってみて、和田さんは「儀式的」な印象を抱いたと言います。自身が探求するテーマと重なる部分があったとのこと。
「電化製品を楽器に蘇らせて演奏していく中で、ここ数年は『電磁囃子』というキーワードを探索しています。電気というテクノロジカルなものが、実は野生性を帯びているという点をテーマに掲げているんです。生活を便利にするために生まれた電化製品が使われなくなったときに、一種の妖怪になるというか。野性に戻って祭りが行われる、みたいな妄想があったんです」


踊りの起源が祈りや願いと深く結びついていることや、今回のように、観客が舞台を取り囲むようなフォーメーションから、酒井さんも「儀式的」というインスピレーションには共通して感じるものがあったと言います。さらに、初めて《意心帰》に触れたときには、お母さんのお腹の中のような感じがしたそう。振付の中で《意心帰》の穴の中に入るシーンもありましたが、そのときに酒井さんが見せていた穏やかな表情が印象的でした。
ART:《意心帰》
2006年に安田侃さんが制作した作品で、東京ミッドタウンのプラザB1Fに常設設置されている。数十億年の時を経て生まれた大理石を、滑らかな曲線で削り出し、太古の地球の息遣い、人間の温もりを表現している。
多くの人が行き交うパブリックスペースで行われるROPPONGI STREET THEATER。劇場で公演をするバレエの世界で活躍してきた酒井さんにとって、舞台や客席の境界がないパフォーマンスの場は新鮮に感じられたのではと思いきや、「視覚的にも感覚的にも違うと言えば違うのですが、同じと言えば同じ感じ」と意外な回答がありました。パフォーマンスを見守ったKバレエ・オプトのチーフ・プロデューサーであり、『シンデレラの家』の企画・構成を担当している東急文化村プロデューサーの高野泰樹さんも「僕も同じ感じがした」と話し、その理由は『異化作用』であると分析します。
「普段はあれだけあの場に馴染んでいる《意心帰》を、お2人のパフォーマンスによって違和感のある場所に変えてしまった。それこそが舞台だと思うんです。そして、普通の平場を舞台と同じような空間に変えたのは、和田さんとはなさんという役者の力だと思います」
その上で、今回のような企画の魅力といえば、『遭遇する』こと。事前に情報をキャッチしてやってくる人だけでなく、他の目的で街を歩いていたら今回のパフォーマンスに偶然出会ったという人もいます。そうした『遭遇』について、和田さんは自らをハッカーに例えます。
「僕はハッキングに近いと思ってやっています。グラフィティなんかも街をキャンバスにしますよね。みんなが行き来している日常空間に作品を突如出現させることにおいては、日常に非日常を注入するハッキングが行われる感覚です。そこに『ねじれ』が生まれるのが、すごく楽しいんですよ」
和田さんが演奏に使うのは、日常生活に馴染んだ電化製品。よく知っているはずのものが従来とは異なる用途で扱われる。すると、そこから未知の音楽が奏でられ、さらには、それに合わせてバレエダンサーが踊っている。そんな不思議な光景との『遭遇』は、日常を非日常に変えた「アート体験」となったのではないでしょうか。
エレクトロニコス・ファンタスティコス!
和田永さんを中心に、さまざまな人々が共創しながら、役割を終えた電化製品を新たな電磁楽器へと蘇生させ、徐々にオーケストラを形づくっていくプロジェクト。現在、東京・日立・京都・名古屋・秋田の国内5都市と、インターネット上にラボを立ち上げ、参加型アートプロジェクトとして100名近いメンバーとともに創作活動中。使い古されたテクノロジーから生まれる『電磁民族音楽』やその祭典を夢想しながら、日々ファンタジーを紡ぎ出していく。
https://www.electronicosfantasticos.com/
体から際限なく発見される、表現の可能性。


和田さんは古い電化製品による『電磁音楽』を追及する中で、『エレクトロニコス・ファンタスティコス!』と体のコラボレーションを熱望していたと言います。ブラウン管の静電気を手で拾って音を鳴らすなど、体を通して電気的な音を奏でられることを発見してからはテクノロジカルでシステマティックなものを、いかに自分の体に手繰り寄せることができるのか、という挑戦を続けてきました。

和田さんは言います。「パフォーマンス中、気づいたら、無我夢中でテレビをぶっ叩きまくっていました(笑)。同時にリズムに乗って体が動いてはいるものの、そこにもっと踊りがあるべきだと思っていたんです。音楽をやりながらも、何か足りない部分があると感じていて、それが今日は拡張された感がして、なんだかうれしくなってきて僕も踊っちゃいました」
電磁音楽で踊った酒井さんは、どのようなことを考えていたのでしょうか。
「パフォーマンスをする前は、電子音をどう感じて、どう踊ることができるのか、わからない部分もあったんです。でも、実際舞台にでてみると、すごく自然で、奏でられる音楽はすごく温かくて人間的。体から電気がでていることもあって、波長があって音を汲み取りやすいんです。音楽はもちろん、奏者の皆さんの存在にすごく助けてもらっている感じがありました」
電磁楽器
役割を終えた電化製品を蘇生させてできたものが「電磁楽器」。和田さんらの手によって生み出され、これまでにブラウン管テレビ、扇風機、換気扇、ビデオカメラ、エアコン、電話機などの数々の家電を楽器化。今回のパフォーマンスでは「ブラウン管ガムラン / ブラウン管ドラム」「扇風琴」「テレ線」「バーコードベース」「非常カンチキ」が使用された。
https://www.electronicosfantasticos.com/works/
ELECTRONICOS FANTASTICOS!発電磁行列
古来より伝わる日本の伝統的な火・水・風・土の祭りに次いで、現代においてなくてはならない「電」を奉る『発電磁行列』。あらゆる人々を巻き込み、音楽、アート、エンジニアリング、サイエンス、デザインが混ざり合う共創の真っ只中にある総勢約60名・全長約30mの一行が繰り広げる狂騒! これまでにキックオフミーティング、オープンラボでの創作過程の公開などを実施。2024年3月17日(日)には東京・東八潮緑道公園で新作パフォーマンスを披露。ブラウン管が轟き、扇風機が唸り、ネオンが鳴く。発電機の山車と練り歩く、電磁の祭りが開かれた。
https://www.electronicosfantasticos.com/news/240317/
© Mao Yamamoto
電磁音楽とバレエ、一見かけ離れているかのように思える表現方法の組み合わせですが、和田さんも酒井さんも口をそろえて「ナチュラルだった」とパフォーマンスを振り返ります。この2つが見事に共鳴した理由を、高野さんがある共通点に着目して語ります。

「はなさんと和田さんがやっていることは、実はすごく近いと思うんです。ダンサーは繰り返しの肉体的な鍛錬の上に表現が生まれていくものですよね。そして、和田さんたちの音楽も電気と言えど、ものすごく泥臭いんです。ただアンプに繋いで音が出るということではなくて、例えば扇風機の羽にレーザーで一つひとつ穴を開けていたり、回転速度で音を変えたり、本当に一から作っているんです。アウトプットとしてはすごくデジタルに見えるけれど、ある意味すごくアナログなんです」
使わなければ、体はどんどん鈍ってしまうもの。現状維持をすることさえ簡単ではない中で、酒井さんは常に自分の体と向き合い、表現の可能性を追及し続けています。
「楽器はチューニングしますが体も同じです。奏でられる体というのをいつも作っています。指先やまつ毛など私たちの体には様々なアイテムがあります。それぞれが多くのポテンシャルを含んでいるけど、意外と人間は体を使っていない。だから『こういうふうに意識したら、どういう感じになるのかな?』といろいろ試していくと、表現の可能性を際限なく体から発見できるんです」

『体の発見』。このキーワードは、和田さんの演奏にも深く通じるところがあるようです。
「世の中ではテクノロジーが進化していますが、例えばブラウン管テレビの演奏では、手の皮が分厚くなったりと体も変化する。そういう対話があるんです。それが今日のようにダンサーとの間にも対話が起こると、より呼吸と血流と電流がつながるんですよね」
追及を続ける先に、際限なく広がる表現の可能性。我々人間の体は、今後どのような表現の世界を切り拓いていけるのでしょうか。

「クラシック」と「コンテンポラリー」の両輪で挑戦を続ける。
Kバレエ・オプトは、BunkamuraとK-BALLET TOKYOが2022年に立ち上げたプロジェクトです。「芸術がいかに社会にその価値を還元していくか」という命題に応えるべく、時代性のある新作を上演しています。『白鳥の湖』や『くるみ割り人形』をはじめとする古典バレエの公演を続けつつ、現代作品の新作を積極的に発表するというのは、日本国内のバレエ団においては稀有なことであり、Kバレエ・オプトだからこそ成せるのだと高野さんは言います。
「クラシックバレエは、伝統を受け継いでいく形式の美。この形式美って、現代とのギャップがあればあるほど魅力が出てくるものだと思います。16世紀頃に生まれたバレエは、ルイ王朝で育まれ、そして時を経てソ連でほぼほぼ今のスタイルへと確立していきました。その時代に人々が感動した美しさを継承して、現代を生きる人々にも同じ感動を届けたいという思いがKバレエにはあります」
「その一方で、Kバレエ・オプトは何をするのか」と高野さんは続けます。「芸術の根源を探っていくと、やはり社会との呼応や社会からの要請というのがあると思います。時流だったり時代性だったり、その時々にしか発信できないものがある。今この瞬間に何でこれだけのお金や時間やエネルギーをかけて作るのか、というところを深く掘り下げてフォーカスした作品を同時にやっていく。バレエ団としての厚みが出ることはもちろん、ダンサーの経験としても、形式美と自分の体の探求という2つのアプローチができます。この両輪によって、より総合芸術たるものになっていくのではないかというK-BALLET TOKYOとBunkamuraオーチャードホールの芸術監督である熊川の考えの基、Kバレエ・オプトが始まりました」
K-BALLET TOKYO
1999年に熊川哲也さんがK-BALLET TOKYOの前身である『Kバレエ カンパニー』を設立。年間50公演以上10万人以上の集客を記録するなど、民間団体としての経営的自立、所属ダンサーの処遇改善といったプロフェッショナルバレエ団としての姿を提示し、日本のバレエ界に一石を投じた。2023年9月から『K-BALLET TOKYO』という新たな名称にて始動。グローバルシティ東京において、海外からも日本にバレエを観にくるような新たな文化交流を担う団体として活動を広げている。
https://www.k-ballet.co.jp/
© K-BALLET TOKYO
シンデレラの家
2024年4月27日(土)から29日(月・祝)に池袋の東京芸術劇場 プレイハウスで上演されるKバレエ・オプトによる第3弾公演。稀代の詩人、最果タヒさんによる書き下ろし詩集『シンデレラにはなれない』を原案に、ヤングケアラーのシンデレラを主人公にした新しい舞台作品。クリエイティブには各方面の最前線で活躍するクリエイターが集結し、ヨーロッパで活躍するジュゼッペ・スポッタさんが振付・演出を手掛ける他、衣裳を担当するのはジェンダーレスブランド『MIKAGE SHIN』をリードする気鋭デザイナーの進美影さん、メインビジュアルにはヒグチユウコさんの描きおろしイラストが採用されている。
© Hajime Watanabe
『シンデレラの家』では、和田さんの音楽がパーティーシーンを彩ります。辛い日常を抜け出したシンデレラにとって、パーティーはある種の魔法がかかった空間。その『魔法』をどのように表現して見せてくれるのか期待が膨らみます。

「自分たちは家電を使って演奏をしていて、家にある外在するものに魔術をかけているようなイメージがあります。主人公の内面にあるものを、どうオブジェクトと楽器と音楽と体で表現できるのか、まさにこれから作っていくところです」と話す和田さん。ダンサーと同じ舞台上で演奏を披露するということで、その空間の一部となりつつも、シンデレラの内面を映し出さなくてはなりません。その難しい挑戦を前に、「内と外の行き来をどう表現できるのか。そこをぜひやってみたいですね」と意気込みを語ってくれました。
一方、酒井さんはシンデレラの母親を演じます。
「育児に介護に仕事にと、ストレスでキリキリになっている母親役を演じます。彼女がやって来ると、みんながストレスを感じてしまうような......。そういった役を演じるのは初めてかもしれない。ものすごく強い刃を出さなければならないのが実は私にとってはすごく大変です。それから、家のボスとしていてほしいとも言われています。役作りにはすごくこだわっているので、思いっきり『はなさん怖かったな!』と言ってもらえたら正解かなと思っています。振付もパンチや重さがある動きなど、色々工夫をしていきたいです」

クラシックバレエを中心に活動してきた酒井さんですが、同時にコンテンポラリー作品やミュージカルなど、幅広い領域への挑戦も続けてきました。そうした古典の型からは逸脱した振付や作品に取り組む場合でも、クラシックバレエが常に自身の中心にあるのだと語ります。
「私にとってはクラシックがベースなので、拠り所であり軸なんです。このベースがあるからこそ、思いっきり外すことができる。だからその軸をなくしてしまうということは、私の中ではあまりないですね」
『クラシック』と『コンテンポラリー』。その言葉自体は対義語のように使われますが、実際は地続きのもの。継承と発見、どちらも歩みを止めずにいることが、より芸術を豊かにしていくのかもしれません。
いつもは静かに佇んでいる《意心帰》を、一瞬にして街の劇場に変えてしまった今回のパフォーマンス。チケットを持っていなくても街の中でアートや建築を体感できることやその偶然性にワクワクさせられること。誰にでも開かれたROPPOINGI STREET THEATERの魅力と意義を、再認識させられる機会となりました。
INFORMATION
Kバレエ ・オプトが、ヤングケアラーを主人公に新たな "シンデレラ" 像を描く――
家族との「愛」と「憎しみ」のはざまに生きる少女が見つけた愛の逆説と希望。
2024年4月27日(土)から4月29日(月・祝)
東京芸術劇場 プレイハウスにて上演
https://www.bunkamura.co.jp/orchard/lineup/24_opto_cinderella/
INFORMATION
Tokyo Creative Salon 2024
「東京クリエイティブサロン(Tokyo Creative Salon)」は、ファッションウィークとデザインウィークを同時開催する、世界にも類を見ないクリエイティブの祭典。「東京を世界一のクリエイティブシティにする」というビジョンのもと、東京を代表するエリアが共創し、2024年3月15日(金)から3月24日(日)にかけて実施した。今年は10のエリア(丸の内、日本橋、銀座、有楽町、赤坂、六本木、渋谷、原宿、新宿、羽田)で行い、ROPPONGI STREET THEATER #05は、六本木エリアのメインコンテンツとして開催された。
https://tokyo-creativesalon.com/
画像提供: TCS2024実行委員会
ART & ARCHITECTURE TRIP
押上・板橋・左近山の街並み
ROPPONGI STREET THEATERで舞台となったアート・建築に関連した、日本や世界で訪れたいスポットをご紹介するコラム。今回は『シンデレラの家』のロケハンのために巡った、押上・板橋・左近山といった下町をご紹介。
東京には六本木、新宿、渋谷など高層ビルが立ち並ぶ街が多い一方で、押上や板橋、左近山(神奈川県横浜市)などには、小さな家屋が密集していたり、数十年前に建てられた団地が現役で存在していたりと、ノスタルジーを感じることができる街並みが今も残っています。歩いていると聞こえてくる子どもたちの声や、漂ってくる夕飯の香りには、多くの方が懐かしさを感じるのではないでしょうか。散歩がてら、街を巡ってみるのはいかがでしょうか。
板橋(板橋駅)
住所:東京都北区滝野川7丁目4
押上(押上駅・スカイツリー前)
住所:東京都墨田区押上1丁目
左近山
神奈川県横浜市旭区の大字
ABOUT ROPPONGI STREET THEATER
彫刻家 安田侃さんへのクリエイターインタビューでの「東京ミッドタウンのパブリックアート《意心帰》の周りでコンサートを」というアイデアからヒントを得たプロジェクト「ROPPONGI STREET THEATER」。
六本木の街なかにある建築やアートが舞台に変身。劇場内で見ることが多いパフォーミングアーツが、誰でも楽しむことのできるパブリックスペースに飛び出し、建築・アートとパフォーマー、そして、観客をつなぎます。
▼安田侃さん(彫刻家)インタビューはこちら:
クリエイターインタビュー #122
安田侃(彫刻家) https://6mirai.tokyo-midtown.com/interview/122_01/
RELATED ARTICLE関連記事