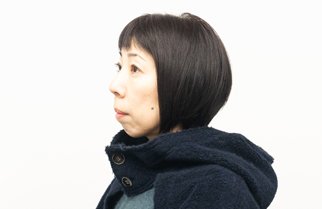PROJECT
六本木未来会議アイデア実現プロジェクト #15
「六本木、旅する美術教室」第13回 写真家川内倫子の「未来と協和する方法」【後編】
update_2024.02.21
photo_masashi takahashi / text_yoshiko kurata
六本木の美術館やギャラリーを舞台に繰り広げられる「六本木、旅する美術教室」。アートディレクター尾原史和さんがインタビューで語った「アートの受け手側の"考える力"は、教育的なところから変えていくべき」という提案を実現するべく、クリエイターやアーティストのみなさんに、その人ならではの美術館やアートの楽しみ方を教えていただきます。
第13回目の「旅する美術教室」の舞台は、麻布台ヒルズギャラリー開館記念として開催中の『オラファー・エリアソン展:相互に繋がりあう瞬間が協和する周期』。今回教室の先生を務めるのは、写真家の川内倫子さん。2022年には大規模個展『川内倫子:M/E 球体の上 無限の連なり』を開催しました。本展の企画を担当した德山拓一さんが案内役となり、オラファー・エリアソン氏が問いかける気候変動や自然環境の変化の中で世界とどう関わるか、そして未来とどのように向き合うのかといったテーマを探っていきます。
六本木、旅する美術教室 第13回
「未来と協和する方法」
- #1
- まずは直感で作品を楽しむ
- #2
- 子どもの心で世界を眺める
- #3
- 見方を変えて身近なものを捉える
- #4
- 自分自身の原点に立ち返る
- #5
- 直感と経験のバランス感覚を持つ
- #6
- 好きと嫌いの理由を探求する
- #7
- 無意識の先にある未来と出会う
共鳴する制作のプロセスとコンセプト。
展覧会の鑑賞を終え、作品の数々を振り返っていくと、川内さんとオラファーの間にある意外な共通点が見えてきました。
川内倫子すべて素晴らしかったのですが、自分で持っておきたいとまで思ったのは、流氷を溶かした作品《溶けゆく地球》。(前編で)"手の離し方"という話をしましたが、それが絶妙で。最小限だけど、しっかりと彼の視線が入っているし、バランスがすごくいい。シンプルで自然に委ねるというあり方があらわれていて、タイトルも素晴らしいです。
德山拓一ポエティックですよね。
川内もともとオラファーの作品のタイトルはいいなと思っていたのですが、こんなに詩人だったのかと、展覧会の最後のテキストを読んで感じました。今回は言葉にも胸を打たれて、なぜ彼の作品に惹かれるのかあらためて実感できる内容になりました。
徳山川内さんの作品とオラファーの作品は何か共鳴するところがあると思っていたのですが、想像していたよりも共通するところがあったんだという気づきがありました。それは制作時の姿勢だったり、時間の捉え方だったり。オラファーの過去のインタビューでは、時制がない庭のような空間を確保するのが、制作の中では重要だという話をしていたのと共鳴するところがあると思いましたね。
川内オラファーは、ずっと子どもの心を持ち続けていて、なおかつ数理的な計算から自身の視点を可視化する技術を持っている。そのバランスがすごいなと思って。子どもの目線だけでは、展覧会にあるような作品はつくれないじゃないですか。子どもの目線でいい写真は撮れても、作品にはできません。私もバランスはいつも悩んでいるところで、そのあたりを学ばせてもらったかな。
制作で言えば、自分自身が作品をつくり始めた頃、「あ、一度全部戻らないと」と思ったタイミングがありました。子どもの時に大事にしていたことが、成長していくにつれて世の中にある同調圧力を感じて、人に合わせることに一生懸命になってしまっていました。例えば高校生の時にルーズソックスが流行っていたら履いたり......。でもそういったことを全部捨てて戻らないと、物をつくれないことに気がついて愕然としたことがあって。
徳山話の筋からずれてしまうのですが、川内さんがルーズソックスを履いていたとおっしゃったのが、意外で(笑)。アーティストはその意外性も魅力のひとつですね。
川内大学で作品をつくる課程に入ったところで、アイデンティティという概念を授業で習って、これは小さな時に大事にしていた目線を取り戻さないといけないと思って。とは言っても、最初の作品ではセルフポートレートを撮ったりだとか、コラージュしたりだとか、わかりやすくつくっていました。ただ、そういう視覚的なことではないんだと気づいてから、精神的な部分に入って自分を取り戻すプロセスに入りました。そこから『うたたね』までは3、4年くらいですかね。
徳山『うたたね』では、ご自身の原点というだけではなく、人類や命の原点にまでテーマが広がっているじゃないですか。それはある意味で超個人というか、オラファーと通じるところですね。
川内そうですね。個人が入り口になっているところは、自分の目指すところでもあって。彼の場合はレイヤーがたくさん入ってくるんだけど、私はストレートになるべく近い距離でやろうとしている感じです。氷の作品に惹かれたのは、すごくインティメイト(親密)だったから。自分の手で氷を置くだけなのに、個と地球が繋がっていく感覚があり、素材とシンプルに向かい合っているところが、すごく好きなのかもしれません。これは好みの問題ですけどね。
徳山氷河から採ってきている氷なので、何万年も前のものでもあって、時間軸が詰まったものでもありますね。
川内すごくシンプルなのに、普遍性が入り込んでいることが、より一層胸を打たれます。
【未来と協和する方法#4】
自分自身の原点に立ち返る
いい展示は入った瞬間にわかる。
あらためて普段どのように展覧会を鑑賞しているか、お2人に伺ってみました。
川内展覧会は、はしごして見に行くことが多いです。ヒントになるものを持ち帰れたらという気持ちもあるし、自分が好きなのはなぜだろうと確認しながら見ています。
德山最近は月に3、4回、日本民芸館に通っています。見に行くと書籍からイメージしていたサイズ感と大体違うんですよ。2次的な情報ではわからないことがあるという気づきを、毎回楽しみにしています。
川内最近は東京オペラシティでの石川真生さんの展示が、ぐるっと壁を建てた構成だったのですが、偶然少し前に開催されていたデイヴィッド・ホックニーの展覧会も似た構成で、壮大な絵巻のようになっていました。そういうのを見つけては、流行っているのかな? と考えてみたり(笑)。POLA美術館の中山英之さんの会場設計を思い出す感じもありましたね。
石川真生 ―私に何ができるか―
東京オペラシティ アートギャラリーにて開催された写真家・石川真生による個展。新作「大琉球写真絵巻」を中心に展示。2023年10月13日(金)から2023年12月24日(日)まで開催された。
〈大琉球写真絵巻〉より 《沖縄でバイレイシャル(ミックスルーツ)として生きること》 2021
撮影:2021年4月24日、本部町営市場
德山東京都写真美術館で開催されていたホンマタカシさんの展覧会では、富士山の作品がすごくよかったです。
即興 ホンマタカシ
東京都写真美術館にて開催された写真家・ホンマタカシによる個展。「富士山の作品」は、《富嶽三十六景》に着想を得た「Thirty-Six Views of Mount Fuji」シリーズ。2023年10月6日(金)から2024年1月21日(日)まで開催された。
《mount FUJI 9/36》、〈Thirty-Six Views of Mount Fuji〉より 2016年 ©Takashi Homma Courtesy of TARO NASU
川内逆さにしてましたよね。ホンマさんらしいと思いました。会場構成もおもしろかったですし、随所にホンマさんのこだわりや疑いが詰め込まれていました。
德山川内さんもホンマさんも、オラファーもそうなのですが、いい展示だということが会場に入った瞬間にわかるんですよね。人間って自分たちが思っているよりも、ぱっと見の直感で受け取っているものが多いのだろうと思います。
川内経験が生きてくることもあると今は思いますね。作品だけではなくて、人を見た時に少しの時間の中でも、ちょっとした動きとか情報ってすごくあるじゃないですか。一方で、11面体の作品《呼吸のための空気》は、話を聞かないとわからない部分もある。ぎょっとした最初のインパクトと、そのあとに経緯を聞いてより想像が膨らむということもありますね。だからカタログを買って復習することもあります。
德山作品の背景やコンセプトは重要ですが、見た目も同じくらい重要ですね。
川内見えない部分を可視化していくとオラファーが言っていたことは、やっぱりバランス感覚なんですよね。いかに可視化していくか、その匙加減がアーティストそれぞれの個性になっていく。ものをつくり続けるのって大変じゃないですか。しかも120名のスタッフを食べさせながら、遊び心を持ち続けていくというのは、違う部分でも感動しますよね。
德山たぶんいいアーティストは、大小はあれど、どこかで挑戦をしているんですよね。挑戦があるから、過去の作品もまた別の視点で見ることができる。
川内そうですね。ひとつずつ殻を脱ぎ捨てていくように、作品がまた次の作品へ繋がっていくような、そういう連続がアーティストそれぞれにあるんでしょうね。それをふまえて見ていくと、また違う面白さがあると思います。
【未来と協和する方法#5】
直感と経験のバランス感覚を持つ

鑑賞は自分と向き合うツールになる。
昨今は展示空間内で撮影OKなど作品との距離はより身近に、さまざまな方法で触れられるようになってきました。これから美術展に足を運んだ際は、どんな展覧会の見方があるとより鑑賞が豊かになるのでしょうか。
川内子どもたちに見てもらうなら、固定観念のないところでまずどう思ったか、ファーストインプレッションを大事にしていくことが大事。それはすべてが正解だから。最初の感覚を持ち続けることは、どんな仕事をする時も必要になってきます。「これを言ったら褒められるかな」という気持ちがあったとしても、やっぱり最初の言葉の方が大事だと思うんですね。そこにその人のすべてが出るから。
德山子どもといつも見に行くのですが、5秒くらいで見終わっていて(笑)。何も見ていないのかなと思っていたら、意外とあの作品はこうだったと話してくれます。そんなふうに自分の趣味と違う人と見れば見るほど、多面的に捉えられるのではないかと思います。仲のいい人だけではなくて、年齢が異なる人や、あるいは、嫌な上司と見てみるとか(笑)。ご飯だったり、映画だったりを組み合わせると、足を運びやすくなりますよ。
川内すべてが好きな作品とは限らないから、なぜ自分はこの作品に惹かれないんだろうと考えることもできますよね。それはある意味で、鏡を見るようなことでもあって、自分自身と向き合うツールにもなる。日常生活からエスケープするには有効な手段でもあって、1周見てから好き嫌いの理由を考えていくと、新しい自分が見つかると思います。自分と向き合うことってもちろんすごくエネルギーがいるから、しんどいんですよ。でも嫌な部分が出てこないと、つるっとしたつまらないものが出来てしまうので、そこまで考えたいですね。
【未来と協和する方法#6】
好きと嫌いの理由を探求する
未来の捉え方はひとつではない。
美術教室の舞台となった展覧会『オラファー・エリアソン展:相互に繋がりあう瞬間が協和する周期』のキーワードである「繋がり」。実は川内さんのテーマとも深い結びつきがありました。今回、どんな「繋がり」が見えたのでしょうか。
川内2022年に開催したオペラシティでの個展(『川内倫子:M/E 球体の上 無限の連なり』)が、地球と自分の繋がりを考えるというテーマでした。球体は、地球であり、サイクルであり、そんなメタファーになっています。「無限の連なり」で言えば、オラファーの作品を見ていても、運動がずっと繋がっている感じだとか、形の繋がりだとか、時間も人もいろいろなものが繋がっている。そんなところが、私のテーマとほとんどイコールに近いものだなと感じました。
川内倫子:M/E 球体の上 無限の連なり
2022年に東京オペラシティ アートギャラリーにて開催された川内さんの個展。6年ぶりとなる大規模個展で、新作シリーズ「M/E」をはじめ、10年間の活動に焦点を当てた。会場デザインは中山英之建築設計事務所が担当。2022年10月8日(土)から2022年12月18日(日)まで開催。また、滋賀県立美術館にて2023年1月21日(土)から2023年3月26日(日)まで巡回展が開催された。
Untitled series by M/E 2020
德山オラファーと川内さんはメディアも違うし、主題も違うのですが、でも共通するものがあるなという直感があったので、話を聞いてみたいと思っていました。実際お伺いしてみると、やはり共通する部分があって同時に最終形のあらわれ方がまったく違うのが面白い。
川内オラファーの展覧会は何度も見ていたのですが、子どものような目線を持っていて、自然に対して密接な関係を持ってつくっているんだなということが再認識できました。垣根をあまり感じないというか、わかる人にわかればいいということではなく、身近な発想からつくっていることがわかってよかったです。
德山子どものような視点だとか、垣根のない感じは、僕にとっては川内さんの写真と繋がるところがあります。
川内恐縮なのですが、勝手に近しいものを感じるところはあります。自然との関係性は私も作品をつくる時のテーマとして取り組んでいます。オラファーは、ティモシー・モートンさんとの対談の中で「アートとは何かについて考えることと行為である」と話していて。対してティモシーさんは「アートとはある意味それ自体が未来である」という話をしていました。自分なりにそのことを捉えると、作品をつくる時にはなるべく無意識の中に入っていって対話していく状態を体現したいと思っているんですね。その無意識が、集合的な無意識に繋がっていくと、それはイコール宇宙に帰っていくことなのかなと思うんですよ。それって未来に帰っているとも言えるかもしれません。自分なりの解釈なのですが、そういう私がタッチしたい部分は、オラファーもそうなのかな、と。
德山未来については、オラファーが今回の展覧会のインタビューの中でも話していたので、まさに、ですね。
川内未来はいろいろな解釈の仕方があるのですが、無意識の先にタッチするというのは、ぐるっと1周するようでどこかに繋がっている感覚があります。未来というものの定義を疑うこともすごく自由な感覚ですよね。
德山無意識と未来というものを並べて考えているのは、近代的な時間の考え方からは離れていて、素晴らしいですね。
川内離れると発想が自由になるというか。現実と向き合って対話すること自体、アートだと思うのですが、どこに向かうのかと言えばたしかに未来へ向かっている感じがするんです。では未来とは何かと考えた時に、集合的無意識の中にあるんじゃないかな、と。
德山直線的な時間の先ではなくて、という。
川内そう考えると面白いなと作品を見ながら考えていました。ホースがぐるぐる回っているだけでも美しいと感じるのは、オラファー自身が人間として生きていて、そこに日常との会話があるからですよね。それは彼だけの感覚ではなくて、みんなの中にある美しさに繋がっているから、これだけ彼の作品が支持されるのだろうと思います。
德山川内さんの作品を見ながら、オラファーの作品の解説を聞いているような気持ちになりました。ありがとうございました。
【未来と協和する方法 #7】
無意識の先にある未来と出会う
オラファー・エリアソン氏のインタビューはこちら
information
『オラファー・エリアソン展:相互に繋がりあう瞬間が協和する周期』
会場:麻布台ヒルズギャラリー
会期:2023年11月24日(金)~2024年3月31日(日)
開館時間:
月水木日 10:00~19:00
火 10:00~17:00
金土祝前日10:00~20:00
展覧会情報:
>https://6mirai.tokyo-midtown.com/event/olafureliasson_ex/
RELATED ARTICLE関連記事