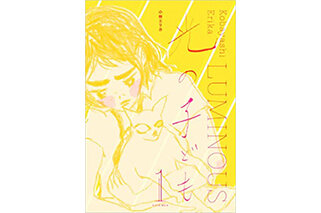PROJECT
六本木未来会議アイデア実現プロジェクト #15
「六本木、旅する美術教室」第9回 作家/漫画家 小林エリカの未来の鑑賞法【後編】
update_2022.02.22
photo_masashi takahashi / text_koh degawa
六本木の美術館やギャラリーを舞台に繰り広げられる「六本木、旅する美術教室」。アートディレクター尾原史和さんがインタビューで語った「アートの受け手側の"考える力"は、教育的なところから変えていくべき」という提案を実現するべく、クリエイターやアーティストのみなさんに、その人ならではの美術館やアートの楽しみ方を教えていただきます。
第9回目の先生は、作家、漫画家の小林エリカさん。21_21 DESIGN SIGHTで開催中の『2121年 Futures In-Sight』展のディレクターを務める松島倫明さんが案内役となり、展覧会が提示する「問い」と、各々の立場から導き出した「インサイト(視座・洞察)」を巡りながら、未来との向き合い方、引き受け方=鑑賞法を考えます。
六本木、旅する美術教室 第9回
「未来の鑑賞法」
- #1
- 私たちが歩んできた歴史から想像する
- #2
- たくさんの問いの中で遭難する
- #3
- 想像できなさを大事にする
- #4
- 未来の常識から現在を眺めてみる
- #5
- 過去にとっての未来を生きる
- #6
- 未来の一員になる
見た後に問いかけと、考える余地を残す展示。
展示を一通り鑑賞した後、「展示の一番最後にあるサウンドインスタレーションの中で、いろいろ考えていたんです」と感想を切り出した小林さん。
小林エリカたくさんの問いが溢れていて「なんだろうこれは!」と驚きながら見ていくうちに、自分自身の中にある問いは、自分自身にとっての未来はなんなんだろうと考えさせられました。展示って、展示物を見てアーティストたちの作品や意見に「なるほど」と思うことが多いですが、見た後に自分自身にも問いが残ったのが印象的です。
松島倫明それはとても嬉しいです。この展覧会は、たくさんの数の未来を考えてもらうことにこだわっていて、タイトルも「Future」ではなく「Futures」にしているんです。「複数形の未来」と言いながら例えば5つしか作品が展示されていなかったら、未来はその5個で決まってしまいますから。途方もない数の未来を目の前にすると、自分の中から答えを出せる余地があると思えるはずなんです。
小林ひとつの未来を提示して「こういう未来を目指しましょう」とするような万博と対極にあるというか。未来と言うとテクノロジーやひとつのビジョンを想像させるようなことが多いと思いますが、そうではない見せ方で未来を考えるきっかけが用意されている展覧会だと思いました。
過去に思いを巡らせると、現在が未来だと気づく。
松島小林さんの作品は、時間軸に関わるものが多いですよね。作品をつくる時、どこを起点にして考えていますか?
小林基本的に過去100年を振り返って、そこから未来100年を考えたいと思っています。例えば放射能と名付けられたものの歴史は120年くらい。そこから現在に至るまでを研究していると、過去の人が悩んだり、もっと未来に生まれたかったと言っていたりする場面に出会うんです。すると、過去の人にとっての未来を私は生きているんだ、と予言者になったかのような全能感を覚えます。そこから翻って、今度は今を生きる自分自身の行動や選択が未来を生きる人からはどんな風に見えるんだろう、という気持ちで作品をつくっています。
『光の子ども』
科学者マリ・キュリーが発見し、「わが子」と呼んだ放射性物質の歴史を、過去にタイムスリップをした光少年と、ネコのエルヴァンの目を通じて紐解いていく。"放射能"はいつ、どこから、どうやって、ここに来たのか。小林さんがコミックとして描いた、史実とフィクションを交えた物語。
松島「未来を生きている」という思考、すごく好きです。昔は王族や貴族しか見られなかった音楽や演劇を、ストリーミングで楽しむ未来を僕たちは生きている。過去から見れば想像がつかなかったり、偽物だと言われたりするものが現在では当たり前になっています。ということは、今僕らが仮想だと思っているデジタル空間やARも、未来では当たり前になっているのかもしれないですよね。
【未来の鑑賞法 #5】
過去にとっての未来を生きる
小林これまで未来について考えると、その未来の中に自分がいない感覚があったんです。未来は誰かがつくるものだと、どこか他人事みたいに捉えていました。この展示を見て、未来は今の自分がとる選択がつくっているのだと実感しています。今ここに生きている一人ひとりが未来をつくることに加担している。だから自分の選択が10年後の誰かを生かすことも殺すこともあることを忘れずにいたいな、と。
松島以前「渋滞があるんじゃなくて、あなたが渋滞なんだ」というフレーズを耳にしたことを思い出しました。 それと似ていますね。この展示をつくっている人たちもまた未来をつくる一員であるという態度で、それぞれの未来を展示しているんだな、と思い出させられます。
小林今って、みんな忙しいからすぐに正解を求めてしまう。未来についても「これが未来です」と言い切って欲しい気持ちが私にもある。けれど、迷い、心の中を見つめながら一人ひとりが未来をつくるんだ、ということを忘れずにともに進んでゆく、ということを実行しているのが、この展示の強さだと感じています。見切れないほどの数の問いを見ながら、それぞれに未来に答えを出している様子を見ていると、未来が誰かの手の中にあるものではなく、自分が決められるものなのだと気づかされます。
松島最初に鑑賞を始める時、「遭難するように」と言いました。未来に対して答えはひとつではないからこそ、ぜひ問いの中を彷徨って見てほしいです。
【未来の鑑賞法 #6】
未来の一員になる

多様な出来事を感じられる場所。
小林私にとって、美術館は正解を言わなくていい場所。作者にとっての正解も、鑑賞者にとっての正解もないから、自分の中にあるものと向き合えることが美術館に行く喜びなんです。
今回『2121年 Futures In-Sight』展を見て、未来に対するそれぞれの考えが何通りも展示されていることが嬉しかったし、自分の中に絶えず問いが生まれる楽しさを感じることができました。これだけ多くの問いに触れたので、実際の未来、10年後、20年後にも思い出すことがあるかもしれない。
松島僕も本や雑誌をつくっていて、20年前に見たものをふと思い出すことがあります。そして僕自身そういう本をつくれたら最高だなと思っています。その時にジャッジしなくても、世界観だけでも、敗北感だけでも、読み手がとりあえず持っておいてくれたらいい。
今回の展覧会は、その場所、その時間に身を置くという制約がさらに面白さをつくっていると思います。会場までの道のり、その日の天気、パネルを見上げながら文章を読むという身体感覚など、多様な出来事が感覚に刻まれるのは物理的なスペースでの展覧会ならではですよね。何か考え事をしたい時、未来を考える時、ふらっと来てくれたらいいなと思います。
information
「2121年 Futures In-Sight」展
会場:21_21 DESIGN SIGHT
2021年12月21日(火)~2022年5月8日(日)
開館時間:11:00~18:00(最終入館:17:30)※最新情報は展覧会サイトをご確認ください。
火曜日(5月3日は開館)
観覧料:一般 1,200円、大学生 800円、高校生 500円、中学生以下無料
展覧会サイト(URLをクリックすると外部サイトへ移動します):
>http://www.2121designsight.jp/program/2121/
RELATED ARTICLE関連記事