


『正しい問いが、六本木の未来を作る』【前編】
プログラミングやアルゴリズムは、この世界を理解するための言語でもある。
- JP / EN
オーストリアの地方都市リンツ。この街で1979年からスタートした『アルスエレクトロニカ・フェスティバル』は未来を体験できる芸術の祭典として、世界中のアーティストや研究者、企業から熱い視線が注がれている。同フェスティバルを主催するアルスエレクトロニカで1995年から総合芸術監督を務めるゲルフリート・ストッカー氏に、アートとテクノロジーを通じてひらかれていく六本木の未来、またこれからの時代に役立つ学びについて話を伺いました。
東京は地球で一番、面白い社会実験の場。
東京に初めて訪れたのは今から約20年前のことです。以来、毎年いろんな理由のもと訪れているのですが、私にとって東京は地球上で一番、面白い社会実験の場です。
世界的な都市と比較しても群を抜いて人口密度が高く、日本という国単位で見ても、そもそもこれだけ多くの人たちがこの街にピンポイントで集まっているという状況がすごいことで、都市の環境、人の技術や営みがそれぞれに調和しながら共存しあっている事実に、訪れる度にエキサイトしています。
一方で、東京は街全体が商業主義に溢れています。この点については個人的に課題視しているところもあって、例えば、渋谷駅前の交差点に立つと実感するのですが、周辺を囲むビル群やショッピングモールのほとんどが広告に埋もれています。そんな風景を見る度に、東京は街の公共空間がマーケティングと広告を得るための場所として保管されているんだなと思うんです。
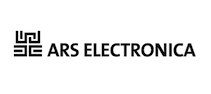
アルスエレクトロニカ
1979年、オーストリア・リンツで始動したアルスエレクトロニカは、毎年9月に開催される『アルスエレクトロニカ・フェスティバル』を始めとする4つの部門を通じて、デジタルアートとメディアカルチャーの分野で国際的拠点を築いてきた。他の3つの部門は、ミュージアムや教育の発信拠点であるアルスエレクトロニカセンター、メディアアート研究・開発機関としてのフューチャーラボ、世界中のアーティストとのネットワークを育成するプリ・アルスエレクトロニカがある。
公共空間の可能性が街をつくる。
街の公共空間をどのように使っていくのか。東京の人々はもっと自分たちで問うべきだと思います。なぜなら公共空間こそ、街の創造性と未来を育む場所になるからです。
毎年9月初旬にオーストリア・リンツ市で数日間開催される『アルスエレクトロニカ・フェスティバル』。私はこのフェスティバルのディレクターを務めていますが、広場や公園、市街地のショッピングモールなど、市内の公共空間を会場として活用します。パッケージしたものを美術館で展示するのではなく、人々の暮らしの現場である公共空間にそれを持ち込むこと。それによって多様な人々がアートやテクノロジーへのアクセシビリティを高めることができる。そしてそこに新しい対話が生まれていくのです。

Ars Electronica Tokyo Initiative Kick Off Forum
5月25日、ストッカー氏は東京ミッドタウンで行われた「Ars Electronica Tokyo Initiative Kick Off Forum」のために来日。「Ars Electronica Tokyo Initiative」とはアルスエレクトロニカと博報堂が、共同で活動を開始したイノベーション創出コミュニティ。Initiative(イニシアティブ)とは、先駆け、率先、第一歩という意味を持つ。「これからの東京、ひいては日本社会を良くする為に、我々は一体何が出来るのか」をミッションとし、企業・イノベーター・アーティスト等、様々なステークホルダーと未来社会を創り出すアイデアを共創し、社会への実装に向けて活動することを目的としている。(Credit: Ars Electronica Tokyo Initiative / Hitoshi Motomura)
リンツは人口20万人くらいの小さな街です。その小さな街で行われている活動は、大きな規模感を持つ街よりも伝わりやすいという良さがあります。アーティストもまた自分の内に閉じこもっているのではなく、アクターとして、社会の中でダイナミックに動き始める時代に入りつつあります。
このように、フェスティバルを通じて、市民が街の発展におけるアクティブなプレイヤーになっていく姿をたくさん見てきました。東京はどうでしょう? 守られたスペースを出て、街全体を舞台にしてみる。そこに東京の一つの可能性があるように思います。

完璧なものから、完璧ではないものへ。
テクノロジーと言えば、東京の高層ビル群は、実用的で機能的で、完璧に整備された構造がそこにあって、その下を通る地下鉄もまた完璧なタイムスケジュールで走っています。そんな働くためのインテグレートされた空間に身を置いていると、高層ビルや地下鉄こそ、東京のテクノロジーそのものであると実感します。これがマンハッタンの地下鉄だったらどうでしょう。100年前にタイムスリップしたような感覚になります。
東京は、まるでサイエンスフィクションのように整っていて、「社会実験の場」であり、「未来ラボ」でもあるんです。それが時として、東京がパーフェクトすぎると感じてしまう所以です。そしてそこに生きる人たちもまた、機械のような精密さで働いている。東京は今後、その完璧すぎるものからどう逃れていくのか、本能的に完璧ではない何かに向かおうとする側面がでてくるのではないかと思います。

オーストリア・リンツ市
人口約20万人、ウィーン、グラーツに次ぐ第三の都市で、オーストラリア最大の工業都市。アルスエレクトロニカを始めとしたクリエイティブとテクノロジーの力によって、産業、教育、雇用創出、多様性社会の実現などの地域社会の課題解決を実現した都市としても知られている。2009年には欧州文化首都に、また2014年にはユネスコ創造都市に選出された。(credit: Nicolas Ferrando, Lois Lammerhuber)
理屈や理論を超えたアートが存在する六本木。
完璧ではない何かに向かうとき、アートは非常に大きな役割を果たします。それは、アートに完璧はないから。アートは理屈や理論を超えたもので、エモーショナルな方法で人の人生や社会を探求する力を持っているからです。
としたときに、六本木ヒルズ、東京ミッドタウン、21_21 DESIGN SIGHT、国立新美術館......。アートやデザインを軸とした文化的な空間に満ちた六本木は、東京が持つべき新しい方向性が内包されている街なのではないでしょうか。20年前の六本木はクラブカルチャーを始めとするナイトライフのイメージが強くありましたが、この20年で街全体が大きく変貌していきました。
東京にくると必ず21_21 DESIGN SIGHTに立ち寄ります。「アスリート展」も観ましたし、日本のクリエイターは、本当に優秀で才能に溢れていますよね。
そもそも日本のクリエイターとアルスエレクトロニカとの関係性は長く、歴史も深いんです。1980年代に今は亡き冨田勲さんがパフォーマンスしてくれたことに始まり、坂本龍一さん、岩井俊雄さん、明和電機や、最近ではライゾマティクス、落合陽一さんらがプリ・アルスエレクトロニカの賞を受賞したり、活動に参加してくれたりしています。
冨田勲
1932年東京都生まれ。大学在学中から作曲家として活動を始め、TV、舞台、映画、CMなど多彩な分野で作編曲家として優れた作品を数多く残す。1970年頃よりシンセサイザーによる作編曲・演奏に着手。1982年「アルスエレクトロニカフェスティバル」に初参加。1984年に再び参加した際にはドナウ川両岸の地上・川面・上空一帯を使って超立体音響を構成し、8万人の聴衆を音宇宙に包み込む壮大なイヴェント「トミタ・サウンドクラウド」を催した。享年84歳。
新しい視点を生み出す存在として。
一方でアルスエレクトロニカとして東京、そして六本木でのプロジェクトも年々増えてきています。人とテクノロジーがどう共存していくのか、どう関係性を作れるのか、などのテーマが圧倒的に多いですね。今、クリエイターやアーティストに求められる専門性や役割が、時代とともに大きく変わってきています。
これまでは表面的にわかるものをデザインに落とし込んでいく傾向が強かったのですが、今、その落とし込む前の過程で生まれる問いや気づき、対話にこそ、クリエイターの役割や専門性が求められています。
つまり社会は今までにない視点を求めている、ということです。だからこそクリエイターはその視点を生み出し、人々がその視点を持って、主体的に行動できる仕組みを生み出す存在でなければならないのです。
RELATED ARTICLE関連記事



























