


『正しい問いが、六本木の未来を作る』【後編】
プログラミングやアルゴリズムは、この世界を理解するための言語でもある。
- JP / EN
オーストリアの地方都市リンツ。この街で1979年からスタートした『アルスエレクトロニカ・フェスティバル』は未来を体験できる芸術の祭典として、世界中のアーティストや研究者、企業から熱い視線が注がれている。同フェスティバルを主催するアルスエレクトロニカで1995年から総合芸術監督を務めるゲルフリート・ストッカー氏に、アートとテクノロジーを通じてひらかれていく六本木の未来、またこれからの時代に役立つ学びについて話を伺いました。
テクノロジーは日常生活に必要不可欠なもの。
このようにクリエイターの社会的役割や求められる専門性が変わってきている今、私たちひとりひとりの意識も変わっていくし、変わらなければならないと思います。
その背景には、リアルとバーチャル、アナログとデジタルが複合的に絡み合う社会になっていること、日々進化していくテクノロジーが自分たちの生活に必要不可欠になってきていることが挙げられます。テクノロジーをどう理解して、どう利用していくのか。利用していく意味、可能性も含めて、まるで粘土を練るように融合させながら考えていく意識こそが今必要なのです。
しかし現実はそううまくいきません。一般的にはテクノロジーに関する情報がかなり単純化されながらインパクトある物語だけが拡散しているからです。AI(人工知能)が地球のすべてをコントロールして、人類を乗っ取ってしまうんじゃないかと言われてしまっていることもその一例です。でも本来AIとは、人間らしさとは何かを考えることでもあるんです。そういった多様な視点を持つためには、「教育の力」が必要になってくるのではないでしょうか。
これからの時代の教育とは何か?
街の公共空間をどのように使っていくのか。東京の人々はもっと自分たちで問うべきだと思います。なぜなら公共空間こそ、街の創造性と未来を育む場所になるからです。
教育の本質とは、世界を知るためのもの、また現実に直面するために必要な知識を学ぶことだと思います。その上で、これからの教育は、地理や歴史といった個別の知識よりも、それらがどう関連しあって世界は作られてきたのか、多種多様な分野を一つの物語に繋げて考えられる視点や知恵を養うことが大切です。
今必要な知識として、プログラミングやアルゴリズムが欠かせないと思います。それは、何も将来エンジニアになるために必要なのではありません。プログラミングやアルゴリズムは、この世界を繋ぎ、理解するための言語のひとつで、それらを学ぶことは、これから必須となる世界を構成するテクノロジーを理解するためのツールとなるからです。
アルゴリズム
ある問題状況において、正解を引き出すための一定の手続きまたは思考方法のこと。その通りに実行すれば必ず特定の結論に達するというもので、数学の公式やコンピュータのプログラミングはアルゴリズムの代表といえる。 アルゴリズムと対置する概念として、必ずしも正解を保証しない方法であるヒューリスティックスが挙げられる。 出典|ナビゲートナビゲート ビジネス基本用語集について
教育の題材にするのは日常に身近なものでいいんです。例えばスマートフォン。簡単な操作の裏では実は目には見えない膨大な情報が飛び交っていることを知っていますか?またここ最近、Airbnbがインターネット上で頻繁にポップアップしていますがその理由を知っていますか?
最先端のテクノロジーは日々ファクトリーやラボから飛び出て、直接日常生活につながっているんです。それを知る手がかりがプログラミングやアルゴリズムにはあって、それを知ることによって、これから未来で起ころうとしていることに少しでも準備ができるし、柔軟に対応できるようになるのです。
実際にアルスエレクトロニカでは地元の学校や大学などにスタッフが出向いて教育プログラムを開発したり、授業を行ったりしています。ひょっとすると、この活動の中から明日のテクノロジーやクリエイターが生まれるかもしれない。その可能性を呼び起こすのもまた教育だと思います。

未来の美術館から未来の教室へ。
東京にはデザインやアートのための素敵なショウケースがたくさんあります。でもこれからの時代、アーティストを紹介したり、完成品を展示するだけではなく、その作品がどういう過程を経て出来上がったのか、そこにはどんな可能性と課題が含まれているのかをワークショップやプレゼンテーションを織り交ぜながら、もっと人々に体験してもらう場所が増えていくことが求められます。つまり街全体がエデュケーションセンターのような場所になっていけたら、未来に可能性が広がります。
そういった意味ではデザインとアートの街、六本木にはその可能性を秘めた場所がたくさんありますね。2010年にアルスエレクトロニカは、秋のデザインイベント「Tokyo Midtown DESIGN TOUCH 」 で作品展示をしましたが、まさに体験型デザインを目指しました。
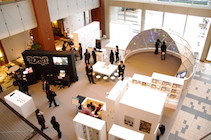
「Tokyo Midtown DESIGN TOUCH」
2007年「デザインを五感で楽しむ」をマスターコンセプトに始まったデザインイベント「Tokyo Midtown DESIGN TOUCH」。4回目の開催となった「Tokyo Midtown DESIGN TOUCH 2010」に参加したアルスエレクトロニカは、イベントのテーマ「未来への手ざわり」のもと、デザインとテクノロジーの融合から生まれた"未来"を感じられる作品を展示。会場には目の動きをトラッキングすることで画面上に絵を描き出す「The EyeWriter」や、世の中が抱える問題を来場者自身が発想し、反応し合うインスタレーション「Shadowgram」などを発表し作品に触れて楽しめる体感型デザインを集めた。
未来の美術館から未来の教室へ。それこそが六本木に点在する美術館やデザイン施設などの新しい役割ではないでしょうか。もちろんこれはアルスエレクトロニカ自体が果たさなくてはならない役割だとも思っています。
さきほど触れた、「公共空間の可能性」にも通じますが、休日になると東京ミッドタウンや六本木ヒルズの敷地内の広場を、多くの人がショッピングしながら通過していきます。この広場という公共空間の使い方はまだたくさんの可能性に満ちているのではないでしょうか。人々が新しい体験ができる場所としてちゃんと見せる機会とを、これからもアートやデザイン、テクノロジーを通じてもっと作っていって欲しいと思います。きっとポジティブな淀みがそこに生まれ、新しい六本木の顔になるはずです。
問いがあるから、答えが生まれる。
そもそもアートとは、デザインとは何か。語り出したら長くなってしまうのですが(笑)、それをあえて一言で言うと、アートは発見すること。そしてデザインはその発見を活用していく応用芸術だと思っています。
また、両者に共通していることは、「問い」です。正しい問いを立てることが、この世界を生きる上でもっとも重要なことでもあります。どのような課題設定をするのか、日々創造的な問いを立てようとするそのマインドセットこそが、世界に参加することを促していきますし、問いを他者と共有することで互いの違いを超えた対話が作り出されていくのです。そして人々が問いに向き合うためのスタート地点が、アートやデザイン、テクノロジーでもあるのです。問いがあるから、答えが生まれるのです。
取材を終えて......
AI、プログラミング、アルゴリズム、テクノロジー。言葉に馴染みはあっても、自分事として捉えるにはまだほど遠かったこれらのことが、ストッカーさんの話を聞いているうちにみるみる自分に近づいてきました。そして、リンツに行ってみたい!と。この街でアルスエレクトロニカを体感すれば、一気にいろんな問いが生まれてくる気がします。(edit_nanae_mizushima)
RELATED ARTICLE関連記事



























