
70 内藤廣 (建築家)
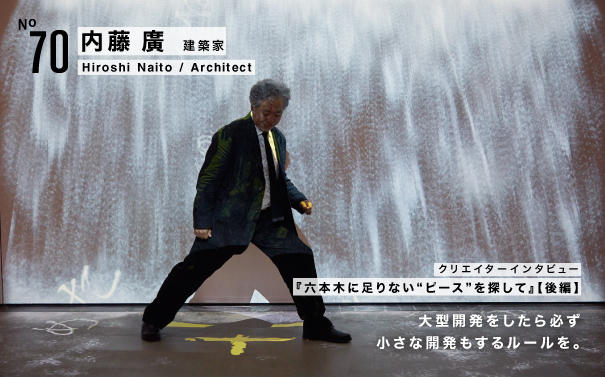
海の博物館、牧野富太郎記念館など数々の建築作品を手がけるかたわら、2001年から2011年まで東京大学大学院で教鞭をとった建築家の内藤廣さん。今回のインタビュー中には、伝説のレコードショップ「六本木WAVE」についての、衝撃の事実も。まずは、企画協力として参加している、21_21 DESIGN SIGHTで開催中の「土木展」についてのお話からどうぞ。
「WAVE」の名付け親、実は僕です。
六本木とは関係のない話ばかりをしていますが、なぜ僕がこの街について語る資格があるかというと、実は80年代初めに「六本木WAVE」の立ち上げに関わっていたから。西武グループがWAVEをつくるときのコミッティーに最年少で入って、内田繁さんをはじめとするメンバーたちと、この街についてああでもないこうでもないと議論をしていました。その後、WAVEができて、街の構造が変わりはじめて......みたいなことを、一応知っている人間なんです(笑)。
その頃、六本木交差点には外国人がたくさんいて、ネオンサインが光ってて、街はギラギラしていました。堤(清二)さんの言葉で今でも覚えているのは、「みんなが騒いでいる中で、黙るって目立ち方もあるよね」。だから、WAVEはサインもほとんど出さなかったし、百貨店物販の常識を変えようということで、床は板張りに。他にも、WAVEの裏通りの守り神として、アーティストの山口勝弘さんが、立体画像の「ホロニック地蔵」をつくったり、いろいろ面白いことをやりました。30年以上前のことです。
ちなみに、「WAVE」って名前をつけたのも僕なんです。当時流行していた「ニューウェーブ」とか音楽を連想させるということで提案したものの、役員会か何かでダメと言われてしまった。でも、ロゴを決めるときに、デザイナーの鬼澤邦さんが真ん中の二文字だけ色を変えたら、WE(私たち)の間にAV(オーディオビジュアル)が挟まっているのはいい、ということで決まりました。

六本木WAVE
1983年開店のレコードショップ。音楽をはじめさまざまな文化・流行の発信基地として愛された。六本木地区再開発に伴い、1999年に惜しまれつつ閉店。跡地は現在、六本木ヒルズ メトロハットとなっている。
都市とは、人間そのもの。
好きな街を聞かれると、僕は1990年代前半くらいまでのバルセロナと答えることが多いんです。なぜ90年代前半までかというと、オリンピックをやるということで、街をきれいにしてしまったんですね。メインストリートのランブラス通り沿いには「バリオ・ゴティコ」という世界遺産のゴシック地区があって、その反対側には「バリオ・チノ」という地中海最大ともいわれる"魔窟"がありました。あやしい人たちがたくさんいて、ひとりではとても歩けないような。
それは、都市の影の部分ですが、バルセロナという街に独特のパワーを与えていました。都市って、人間の思考とか欲望が映し出される、言ってみれば人間そのもの。我々が表と裏を持っているように、都市も表と裏を持っている。裏のない人間なんて、なんだかつまらないでしょう? でも都市計画とか再開発って、その影を消してしまうわけです。
六本木は、再開発の街になってしまった。
これは六本木にも通じるところがあって、六本木ヒルズ、国立新美術館、東京ミッドタウンができて、すっかり明るい街になってしまった。六本木って、再開発の街になっちゃったんだよね。
ちょっと前までは、もっとパワーのあるディープな街だったんですよ。テレ朝があって芸能人がいて、一本路地を入ると暗くてあやしくて、六本木交差点の周辺が日本の文化発信地になっていた。谷地にあって若者のサブカル系文化が生まれる渋谷とも違って、台地にある六本木は、もっとハイ(カルチャー)で深い。
そういうディープさって自然発生的にできたもので、つくろうと思ってもつくれません。実際、大型開発って投資と回収のゲームだから、そもそも自然発生的なものを受け入れにくい。ましてや未来を予感させるようなカルチャーなんてなかなか生まれないんです。

巨大プロジェクトだけで終わるか、「やっぱり六本木」となるか。
もちろん、大型開発が悪いかというとそうも言えない部分はあるけれど、歴史的な変遷もふまえて、次のステージを考える時期にようやくきたかな、と。六本木がこのまま巨大プロジェクトだけの街になって終わっていくのか、そのまわりに面白い街が広がっていて、何かといえば「やっぱり六本木行かなきゃ」って場所になれるのか、今はその分かれ道。
これから先、六本木をどんな街にしていくか、それこそ、この未来会議のようにみんなで考えていかなければいけないと思うんです。
僕がずっと関わっている渋谷もまさに同じ状況で、今やろうとしているのは、ストリート文化をサポートすること。渋谷には、かつて「渋谷ジァン・ジァン」という小劇場がありました。大きな商業施設と比べれば不動産価値なんかほぼないに等しいくらい小さな空間でしたが、本当に濃い文化を発信していた。渋谷の連中とは、そういう場所がまたできないか、っていう話をしています。
渋谷ジァン・ジァン
1969年から2000年まで、渋谷公園通り・山手教会地下にあった小劇場。デビュー前の井上陽水、荒井由実、中島みゆきなどが出演するなど、収容観客数200人未満ながら、音楽や演劇をはじめさまざまな文化を発信していた。
大型開発より中小の開発のほうがはるかに難しい。
渋谷はストリート文化、じゃあ六本木には何があればいいのかといえば、やっぱり「小さい粒」。大きい粒はもうつくったし、これから先も大型開発がいくつも予定されている。言葉は悪いけれど、大型開発は誰でもできます。もちろん地権者をまとめるのは大変だけど、あとはフロアの金勘定をやって積み上げればいいだけ。難しいのは中小の開発、そのほうがはるかに難易度が高いんです。
僕がずっと提案しているのは、たとえば東京ミッドタウンみたいな超高層を建てたら、ちょっと離れた場所に採算抜きで面白い場所をつくられなればいけない、というルール。(今、僕が食べているパスタに入っている)このグリーンピースくらいのものでいい。大したお金じゃないんだから、巨大開発をする代わりに投資してもいいんじゃないかって。
採算抜き、小さな"グリーンピース"をつくろう。
もしかするとライブハウスかもしれないし、ギャラリーかもしれない。常に最先端で一番とんがった文化が吹き出している場所があって、若い世代を惹きつける。すると、巨大な商業施設にやってきたお兄ちゃんやお姉ちゃんが、そこまでテロテロ歩く。イベントが終わったら飯を食わなくちゃいけないってことで、飲食店ができたり、超高層に入っても仕方ないと思っているIT系の企業が移ってきたり。街って本来、そうやってできていくんですよ。
個人的には六本木は、女の子ひとりでは歩けないみたいな裏通りが面白い。でも行政側はそんなことは言えないし、意図的にもつくれない。だから見て見ぬふりをして、なるべく排除しないのがいいですね。六本木には今、そんな裏通りとたくさんのグリーンピースがほしい。
今日は「土木的な視点から、未来の六本木についてのアイデアを」って言われていたんだけど、こんな話でいいんでしたっけ?(笑)
取材を終えて......
WAVEの話は、これまでのクリエイターインタビューにも何度も登場していますが、まさか名付け親に出会えるとは......。この日の取材は、「土木展」プレスプレビューの合間を縫って、ランチをとりながら。土木展の様子はブログでもレポートしています。ぜひご覧ください。(edit_kentaro inoue)
RELATED ARTICLE関連記事



























