


『六本木の街から、テキスタイルの理想の未来を描く』
5月になったら、街じゅうにこいのぼりをあげましょう。
マンダリンオリエンタル東京のテキスタイルデザインなどで知られ、ニューヨーク近代美術館(MoMA)をはじめ、世界中の22の美術館に作品が永久保存されている、世界的なテキスタイルデザイナー・須藤玲子さん。六本木歴なんと40年、まさにこの街を知り尽くした須藤さんに、編集部がお願いしたテーマは、「六本木をテキスタイルの街に変えるには?」。さて、その答えとは? 須藤さんおすすめの六本木のスポットにも注目です。
ずっと間近で見てきた、六本木の"豹変"ぶり。
私が六本木に来るようになったのは、まだ学生だった70年代のことですから、実はすごく関わりが長いんです。もちろん、その後のこの街の"豹変"ぶりはずっと間近で見てきたし、いろんなお店がなくなってしまったのは少しさみしくもあって、「あそこにあれ、あったのに」なんて、ため息をつくこともあります。
たとえば、ロアビルには手づくりの洋服を扱うお店や、輸入雑貨を扱うすてきなセレクトショップがあって、田舎から母が来るとよく連れていったりしていました。今のイメージからすると信じられないかもしれないけれど、すばらしいファッションビルだったんですよ。80年代になると、WAVEができて、そこで紹介されているワールドミュージックは最高だったし、地下1階のシネ・ヴィヴァンで小難しい映画を観て、「私ってもしかして文化的?」なんて気分に浸ったり。

ロアビル
外苑東通りを、六本木交差点から東京タワー方面に向かったところにある複合商業施設。1970年代に完成して以来、六本木のランドマーク的な存在としてもおなじみ。現在でも、飲食店などが数多く軒を連ねる。
テキスタイル関係でいえば、1972年にオープンしたタオル屋さん「ホットマン」。ここは東京の青梅でつくられているタオルを扱うお店。それを六本木という街が受け入れて、もちろん今でもそこにあるというのは、本当にすてきなこと。最近でこそ、今治タオルがものすごく脚光を浴びていますが、当時、まだ日本にそういう本格的なタオルをつくっているところはありませんでした。だから、ホットマンはもちろん、ソニープラザに行ってアメリカ製のタオルを買ったり、原宿のパレフランセにできた日本最初のマリメッコのお店にわざわざ行ったりしていたんです。
いまだに通っているのは、昔からあるお店ばかり。
1984年に「NUNO」という会社を設立したのも六本木だし、その前に7年ほどいた会社もやっぱり六本木で、この街はいつしか私にとって働く場所にもなりました。今では六本木ヒルズや東京ミッドタウンが六本木の顔になりましたが、いまだに通っているのは、昔からあるお店ばかり。

NUNO
1984年の設立には須藤氏も参加、同年六本木アクシスビルに本店をオープン。日本各地の伝統的な染織産地と新しい素材や技術をつなぎ、独創的な布づくりを行っている。世界各国の美術館での展示や、永久保存されている作品も多数。https://www.nuno.com/
たとえば、焼き鳥の「南蛮亭」とか、トーフステーキで有名な居酒屋「一億」とか。一億なんて、掘っ立て小屋みたいで、80年代と何も変わっていないんですよ。普通、お店ってリニューアルしてどんどんかっこよくなるものですが、それがない(笑)。ただ、すごくきれいに手入れがされている。みなさんも、あのあたりに行ってみると面白いですよ。
イベントごとがあれば「おつな寿司」だし、お菓子は「青野」の鶯もち。それから、六本木はライブハウスの街でもあったんですよね。「六本木ピットイン」「ケントス 六本木店」「バードランド」に「STB139 スイートベイジル」。ライブに行ったあとには必ず寄って、ハンバーガーをかじった「ザ・ハンバーガー・イン」も大好きでした。劇場あり、映画館あり、ライブハウスあり。もちろんなくなってしまったところも多いけれど、まだまだ80年代から続くお店が残っているのが、すごく六本木らしいなって思います。
きれいな場所でつくられるテキスタイルは、やっぱり美しい。
私は「断らない須藤玲子」と言われているくらい(笑)、展覧会や講演で、世界中のあちこちに行っています。その中でもやっぱり一番好きな街といえば京都、かな。理由は、そこで暮らす人たちの生活が、ものすごく整頓されているから。行くたびにいつも、京都人の中には何か貫かれているものがあるんだろうなと感じているし、日本人はそういう姿勢をもっと学ぶべきだとも思っています。
前に原研哉さんが言っていて面白いと思ったのが、「自転車のカゴにゴミがひとつ入っていると、そこにどんどんゴミが溜まっていく」という話。でも、京都にはそういうことがない気がします。もちろんそれは街の景観だけじゃなくて、機屋さんにもいえること。機屋さんって雑然としていることが多いんですが、京都の機屋さんはすごくきれい。京丹後とか京都の中心部から距離が離れたところでもそうなんです。
これはヨーロッパの片田舎でも感じることですが、質素だけど美しい。忙しくても豊かで、生活を楽しんでいる。やっぱりつくる場所がきれいだと、そこで生まれるテキスタイルもやっぱり本当に美しいんですね。だからといって、私の家がきれいか、うちの会社が整理整頓されているかというと、それはまた別の話なんですけれど(笑)。

織物の産地には、いつも機音が響いている。
今回、「六本木をテキスタイルの街にするには?」とたずねられて、正直「え、六本木をテキスタイルの街にしちゃうの!?」って驚いたんです。だって、テキスタイルの街にするなら、やっぱり機音がほしいじゃない? 京都にしても桐生にしても今治にしてもそうだけど、日本の織物の生産地を訪ねると、やっぱり街には機音がある。伝統工芸的な手織りの織物をつくっているところもそうだし、工場で大量生産をしているところもそう。基本的には、街に機音が響いているんです。
活気のある産地になると工場は24時間営業、真夜中に薄く明かりがついた工場から、糸を紡ぐ「シー、シー」という音が聞こえます。地方都市で、街灯もぽつりぽつりとしかない中で、機械だけが静かに動き続けている。虫の音に季節を感じるように、テキスタイルをやっている人間にとっては、それが落ち着くというか、「来たな」という感じがすごくあるんです。
逆に、産地に行って機音がしないと、「いったい何が起きたの!?」ってすごく不安になる。機が止まるイコール廃業みたいな、なんだか命が止まるような気がして。機械も生き物なので、1日2日はいいけれど、1週間か10日も止めると、布が織れなくなってしまいます。やっぱり生きている、動かしていることが重要。工場を動かすためには市場だって必要だし、流通やお店だって必要、まさに日本人が日本の生地をつくっていくというか。これは何の世界だって同じですよね。
テキスタイルの街は無理、でもメッカにはなれる。
ちょっと話が脱線してしまったけれど、六本木が未来、テキスタイルの産地になることは絶対に考えられないでしょう。だけど、「テキスタイルのメッカ」になら、なれるかもしれませんよね。たとえば冒頭で紹介したホットマンなんかは、その核になるお店。また、これは、六本木をメッカにするためのアイデアのひとつでもあるんですが、街じゅうに「こいのぼり」をあげるというのはどうでしょう?

ホットマン
創業は明治元年、50年以上にわたって東京・青梅でタオル製造を行う純日本製タオルブランド。細い糸を密度濃く織り上げ、秩父山系の伏流水を使って染色された、上質なタオルで知られる。1972年、六本木に直営1号店をオープン。
2008年、私たちは、アメリカのワシントンD.C.にあるジョン・F・ケネディ舞台芸術センターで開催された「Japan! Culture + Hyperculture」展という、日本を紹介する文化芸術イベントに招かれました。大きなギャラリーが3つあって、安藤忠雄さんと草間彌生さん、そして私たち「NUNO」が、会期中通して展示をすることになったんです。

「Japan! Culture + Hyperculture」展
2008年2月、アメリカのジョン・F・ケネディ舞台芸術センターで開催された、日本の文化・芸術を紹介する展覧会。写真は、"コイ カレント" インスタレーションの様子。その後、2014年5~8月にはパリのギメ東洋美術館でも、新たなテキスタイル20点ほどを加えて、同様のインスタレーションが行われた。
そのとき「日本のテキスタイルを見せてほしい」と頼まれて、つくったのがこいのぼり。せっかくなら、テキスタイルを通して日本の生活とか風習を伝えられないかと思って、直径1メートル、長さ3メートル、いろいろなテキスタイルを使ってつくった巨大なこいのぼりを60本くらい展示しました。こいのぼりといっても、いわゆる古典的なものじゃなくて、布を筒状にして口と尾っぽを小さくしただけの、すごく抽象化したもの。お客さんの反応はというと、みんな大喜び、というか大笑い。「なんで魚なの?」「なんでカープなの?」って(笑)。
たくさんのこいのぼりが風に揺れる風景を、六本木に。
六本木でも、5月になったら、街のみんなが参加して、こいのぼりをあげましょう。ルールは、それぞれのお店にある布や、その場所を象徴するようなものを使って、必ずこいのぼりを1匹つくること。織っても染めても絵を描いてもいいし、カーテンをそのまま使ったっていい。小さいのから大きいのまでいろんなサイズのものがあっていいし、真っ黒でも真っ白でも、とにかく難しく考えなくてOK。六本木には外国人も多いし、すごく面白いと思うの。
街じゅうにこいのぼりが泳いでいて、お菓子屋さんはこいのぼりのお菓子をつくったり、子どもたちが参加できるような、こいのぼりのワークショップをあちこちでやったり。東京ミッドタウンなんて、ちょうど吹き抜けがあって風が抜けるから、すごく気持ちいいはず。
花火って、見た人全員を幸せにしてくれるでしょう? 丸の内でやっていた「東京ミレナリオ」のようなライトアップももちろんドキドキする。でも、たくさんのこいのぼりが風に揺られている風景も、けっこううれしいよね。

日本の風土にあった素材、日本人の肌に一番近い素材ってなんだろう。
私が今、一番興味を持っているのは、日本の縞模様について。大好きなプロダクトデザイナーの竹原あき子さんが書いた『縞のミステリー』(光人社)などの文献を読むと、縞模様は江戸時代に木綿と一緒に入ってきたそう。欧米の縞模様は、囚人服のように、どちらかというとネガティブなイメージがありますが、日本は少し違います。「縞帳」なんてものがあるくらい、膨大に縞模様がある国なんて他にありません。
また、縞という模様が、日本の古代の布、本来の布を考えるきっかけにもなりました。貴族が身につけていたような高価な布には研究家がいっぱいいますが、「ボロ」のような、生活に寄り添っていた大衆の布の歴史は、あまりにも身近すぎてなかなか見えてこない。もともと日本は、麻とシルクの国。なんだか渋いでしょう? 最近では、日本の風土に一番あった素材、日本人の肌に一番近い素材はなんだろう、なんていうことを考えるようにもなって。
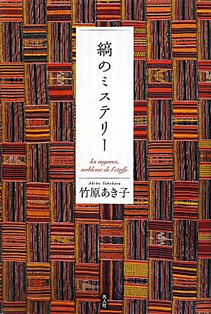
『縞のミステリー』(光人社)
縞というもっとも単純な模様の正体をめぐって、日本、アジア、ヨーロッパ、アフリカ、イスラム諸国を旅し、産業、デザイン、歴史に触れたエッセイ。著者は、キヤノンカメラなどで工業デザイナーを務めた竹原あき子氏。
ちょうど2011年の東日本大震災をきっかけに、日本の産地を歩こうと思ったのも理由のひとつ。私がテキスタイルのデザインアドバイザーを務めている無印良品でも、日本の布をテーマにした「Found MUJI」の活動や、岩手県大槌町の女性が刺繍する刺し子のデザインをしたりと、日本のものづくりに深く関わるようになりました。私自身、そんなことをするなんて、考えてもみませんでした。でも、今までだったら出会えなかったような、工業製品ではない織物を織っている人たちや、着物の産地を訪ねる機会が増えたことを、とてもうれしく思っています。
未来にどうしようもないゴミを残さないために。
もう少し大きな話をすると、2003年に、私も関わった帝人の「エコサークル」というシステムプラントが立ち上がって、原油由来の化学繊維は、すべて再生可能になりました。すばらしいんですよ、このシステム。たとえばポリエステル100%、ナイロン100%であれば、あらゆるものが完璧にリサイクルできるんですから。
私も80年代、90年代には「ハイブリッドテキスタイル」と呼ばれる、化学繊維と天然繊維をミックスさせた新しい布をずいぶんたくさんつくりました。今までにない見え方をするので、「これはハイテクだ、日本でしかできない」と言われて、世界中の美術館にコレクションされたんです。
でも今、私自身は、原油由来の化学繊維と天然素材は分けて考えたいと思っています。そうやってものづくりをしていかないと、10年後20年後30年後の未来に、どうしようないゴミを残すことになってしまうんじゃないか。それは本当にやってはいけないことなんじゃないか、って思って。
大槌町の刺し子
東日本大震災からの復興、また現地のブランドづくりを目指す「大槌復興刺し子プロジェクト」に共感した、無印良品が商品を企画。岩手県大槌町の女性たちが一針一針刺繍した、大槌刺し子ストラップを販売中。http://www.muji.net/foundmuji/2014/12/174.html
化学繊維と天然繊維は分けて考える、テキスタイルの理想の未来。
だから、2003年以降は「懺悔の時代」と言っていて、本当に懺悔しっぱなし(笑)。たとえば、ポリエステルと紙をミックスしたテキスタイルは、紙の部分をポリエステルにして、100%ポリエステルの布につくり変えたり。今、デザインアドバイスをしているいくつかの企業とも、布のライフスタイルを考える取り組みを続けています。
もちろん全部が全部、完璧に理想の姿には至っていないけれど、いつかは実現できるような気がしているんです。今はまだ無理だけど、5年先、10年先には新しい技術も開発されるかもしれない。六本木の街がここ15年で大きく様変わりしたように、きっとテキスタイルの世界だって変わっていくはず。私が勝手にやっているだけで、まだまだ小さい動きですが、そういう流れがだんだんだんだん膨らんでいって、少しずつ広がっていったらいいなと思っています。
取材を終えて......
「すてきだよ〜」「おいしいよ〜」と言いながら、次々とおすすめのお店を紹介してくれた須藤さん。本文に登場した数は、おそらく過去のインタビューでも最多。それ以外にも、おそばの「HONMURA AN」、俳優座のパブ「HUB六本木店」、中華の「北海園」、さらに会社の"残業食"としてよく食べる「正直家」のやきとり重に、藍の風呂敷に包まれた木の出前ケースがかっこいい、うなぎの「野田岩」など。今後ブログなどでも、ぜひ紹介させていただきます!(edit_kentaro inoue)
RELATED ARTICLE関連記事



























