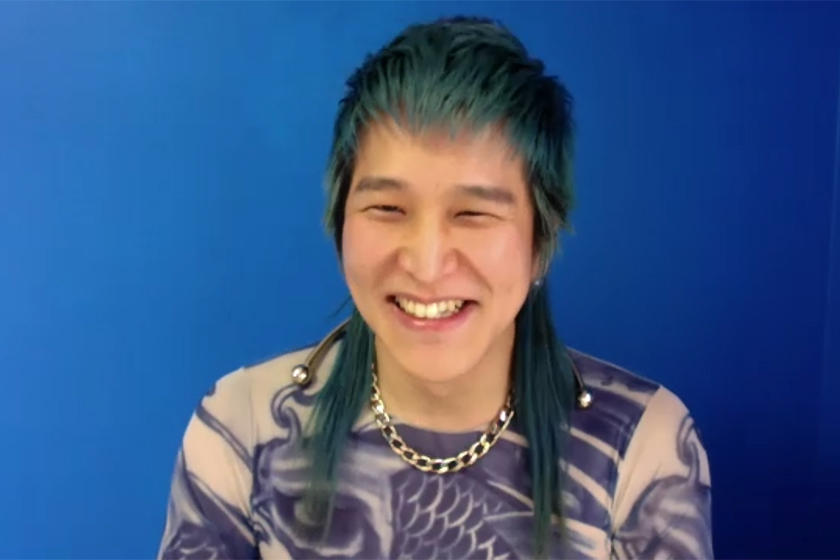


INTERVIEW
117
Dan Isomura / Artist
磯村暖美術家
Dan Isomura / Artist
『今できるアートを暮らす場所から始めていく』【前編】
社会的な繋がりを楽しみながらデザインする。
移民・難民、GSM(ジェンダーマイノリティおよびセクシュアルマイノリティ)、宗教の問題など、現代社会のひずみに焦点を当てた作品を多く制作する、磯村暖さん。子どもの頃に引きこもりを経験し、医学部志望から一転し、独学で多摩美術大学に進学。その1年後には東京芸術大学を受験し満票を獲得するなど、振り幅の大きい経歴が注目されがちですが、自らも困難を乗り越えてきた人らしい優しさが、作品の根底に息づいています。異端な若き美術家の目に、激変する世界はどう映っているのでしょう。新型コロナウイルスが感染拡大する最中、今回はオンラインのインタビューで、半年間にわたり滞在したニューヨークでの日々とともにうかがいました。
ニューヨークから東京へ。不安とともに始まった新生活。
昨年9月から約半年間、Asian Cultural Councilから助成をいただいて、ニューヨークに滞在していました。3月頭に帰国したのですが、僕がニューヨークにいた頃はまだ、新型コロナウイルスの感染者はアジアに集中していました。とはいえ、ニューヨークでも1月頃から警戒が強まり、アジア人として居心地の悪さを感じるようになってきました。たとえば地下鉄に乗ると変な目で見られたり、咳払いをすると見知らぬ人から激しく文句を言われたり......。一方で、マスクをしているアジア系の人を見かけると、ニューヨークではマスクをする人が少ないこともあり、無意識に距離を取ってしまっている自分もいました。僕を含め、多くの人の思考回路が極端になっている、そんな時期でした。

Asian Cultural Council
アジアと米国におけるアーティストや研究者、アートの専門家に国際文化交流の機会を提供する非営利団体。ビジュアルおよびパフォーミング・アーツの分野におけるアーティストやアートの専門家へのフェローシップ助成プログラムを通じて、米国とアジア、そしてアジア諸国間での国際文化交流を支援している。
帰国する1週間ほど前に、ニューヨークで初の感染者が確認されたのですが、当時は日本の方がアメリカより感染者数が多かったので、周りの人に心配されながら帰る準備を進めていました。でもその1週間でニューヨークの感染者数が一気に増えて、どこにいれば安全なのだろうと混乱しつつ帰国して、同時に新大久保へ引っ越したのですが、意外とみんな普通に過ごしている、というのが最初の印象でした。ニューヨークでは非常事態宣言が出され、外出が制限されるなど深刻な続報が届いていたので、あまりにも落差が激しく、不安とともに新大久保での生活が始まりました。あれから2カ月ほど経ちましたが、いまだに引っ越しが終わっていません。家具を揃えたり内装を整えたりしているのですが、感染が怖く実家に荷物を取りに行けず、資材もコロナの影響で海外から届かないんです。
移民の多い新大久保を拠点にした理由。
新居の真向かいに、もうひとつ100平米ほどのスペースを借りました。スタジオ兼ギャラリー兼イベントスペース「UGO」を始めるためです。アーティストだけでなく、いろんな人が自由に出入りできる空間にしようと、数人のアーティストと立ち上げた場所で、ニューヨークに行く前から進んでいた計画でした。3月21日にオープニングパーティーをする予定だったのですが、コロナで延期せざるを得なくなり、不特定多数の人に開かれた場所にするというそもそものコンセプトも、一から考え直さなければいけない状況になっています。

UGO
4人のアーティスト(磯村暖、龍村景一、林千歩、丹原健翔)を中心に主宰する、新大久保駅から徒歩3分の"新しいパワースポット"。制作スタジオ、イベントスペース、ギャラリー、バーなどとして運営していく予定。
新居とUGOを新大久保に構えたのは、日本有数の多文化的な土地柄だったから。そこで移民の人たちと関わりを持ちながら制作するようなスタイルは、以前鶯谷に住んでいた時から始まりました。日本にいる移民の現状は、近くに住んでみなければわからないことがたくさんあるし、おずおずとやってきて限定的に交流するのではなく、普段から日常的な交流があった方がいいと思ったんです。新大久保はご存じの通り、韓国人やベトナム人、ネパール人などが比較的多く、それ以外にもさまざまな国の人が集まる街です。僕は以前、難民の方たちに日本語を教えるボランティアをしていて、アフリカ系の方なども多かったのですが、彼らは授業の後に日本で手に入りにくい食材を買いに新大久保の店によく行っていました。ボランティア団体のスタッフから絵画教室などをやってほしいと言われたりもして、いつか自分でスペースを持ってやりたいと思っていたんです。そういったつながりもあり、住んでいない人でも集まりやすい新大久保にしようと思いました。
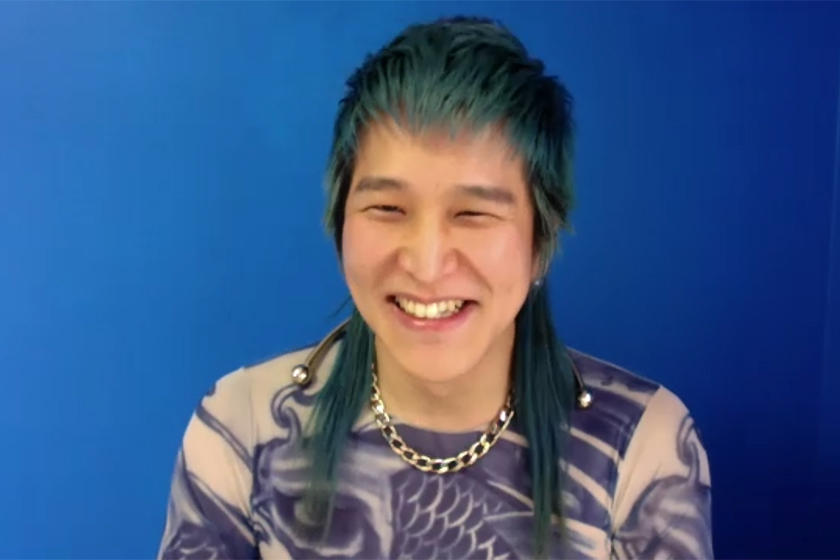
言葉にするのが難しい問題を作品で客観視する。
社会問題を作品につなげるようなことを考え始めたのは、東京芸大に在籍していた2013年頃。仲良くなったドイツからの留学生が、日本人の同級生よりも日本の原発について詳しくて、理由を尋ねたら「日本で暮らしていたら不安だから、情報を集めるのは当然だよね。逆になんで知らないの?」と言われて。ドイツは日常と社会問題とアートがごく自然に結びついていて、その留学生自身もやはりそういう作品をつくっていました。以来、僕も普段考えることに対してより自覚的になって、社会問題などを意識しながら制作するようになりました。同時に、芸大で専攻していた絵画でもできることはたくさんあったのですが、絵画以外の表現を取り入れることが自分にとってより自然になっていき、現在に至っています。
数多くある社会問題の中でも移民とGSMに関しては、いつも頭にあって、でも社会的には話しづらいトピックだと感じていました。今でも不特定多数の人に向けると特に言葉にするのが難しいのですが、作品に取り入れることでもう少し自然に言及できて、単に話すことよりも客観視することができるのだと感じています。ニューヨークに行きたいと思ったのも、これらの問題が社会で早くに顕在化して、世界的に見ても先進的に取り組み、同時に多くのバックラッシュも経験しているから。現状を自分の目で見たかったし、昔のことを知っている人たちの話も聞きたいと思って行ってみたのですが、想像していた以上にあらゆる差別が今も当たり前に存在していました。最初はがっかりもしたのですが、そんな状況だからこそ、多くの人は差別意識を自覚したうえで、理性を働かせて適切な言動を選択しようとする意識を共有しているようにも見えました。
ある事件で気づいた、自分の中の偏見。
滞在中、差別意識に気づかされる衝撃的な事件がありました。住んでいた家から徒歩10分圏内の公園で、女性が刺殺されたんです。身近で殺人事件が起こったことなど今までもちろんなかったので、外に出るのも怖くなってしまいました。容疑者は13歳の少年であることがニュースで報じられたのですが、僕の住んでいたハーレムという地域は歴史的にアフリカ系アメリカ人の人が多く住む街で、この辺りで13歳の少年が刺殺したと聞いたら、アフリカ系アメリカ人だろうと多くの人は反射的に思ってしまうんです。実際、人種等の情報が出ていない段階で「容疑者の黒人の少年は......」と口を滑らせる場面にも遭遇しました。僕自身、日本で暮らしながら、差別意識や偏見を持つことはできるだけしたくないと思っていたし、そのためにはどうすればよいかかなり考えてきたつもりだったんですけど、生命に危険がおよびかねない事態にさらされて、人種のように見てわかる情報をほしがってしまう自分がいました。最初は身の危険に対する不安が大きくてストレスだったのですが、しばらくすると自分の差別意識に気づいて、どう対処すればいいかわからないことに対するストレスの方が大きくなっていきました。
そんな中カナダのトロントへ行ったのですが、ニューヨークと比較すると、人種に関するステレオタイプが薄いと感じました。2週間弱の滞在だったので、その感覚が現実に即しているのかわかりませんが、貧富の差が人種によって分けられていない印象を受けたのです。ステレオタイプが薄ければ、差別意識や偏見を持ちにくいことに気づいた反面、それが効果的かどうかは別としてニューヨークのような場所では偏見を持つと楽だったのだとわかりました。トロントをいい街だと思いながらニューヨークに戻って、疑心暗鬼に他人をジャッジしてギスギスしている雰囲気に、安心感すら覚えてしまいました。

ニューヨーク滞在
ニューヨーク滞在中の磯村さん。写真は、ホイットニー・ヒューストンの叔母としても知られているポピュラー歌手Dionne Warwickと会食中のもの。アメリカ国内で先駆けてLGBTQの権利を訴えていた人物でもある。
街に出た時に遭遇する他人のバックグラウンドを知ることは不可能で、その場で得られる情報というのがやはり人種とかになってしまいます。そして現在のニューヨークでは、その偏見と実際の犯罪率などに相関が見れてしまうので、自己防衛のための判断材料を何も持たないよりは偏見にまみれていた方が犯罪に遭遇する率が下がるということを肯定せざるをえないんです。ただ言うまでもなく問題なのは、偏見に繋がる状況は特定の人種の人たちが自ら好んで生み出したものではなく、社会全体が生み出したものであるというところです。
アメリカ人の友人とこの件について話してみて知ったのは、やはりアメリカは人種によって経済力や教育の格差が生まれやすい土壌であることです。そして今、Black Lives Matterの運動が大きくなっていて「これは"黒人VS白人"の運動ではなく"すべての人VS差別主義者"の運動である」という言葉を見て頷きましたが「すべての人(今まで差別に加担してきた人も含む)VS差別を生み出す社会」のスケールで考えないと、偏見を持たざるをえなかった人たちを新たに差別主義者の枠に押し込め、分断を深めてしまうのではないかと危惧しています。もちろん自覚的な人種差別主義者が多い日本においても"VS差別主義者"で始まる議論は同じく分断を進め、開き直った極端な差別主義者の居場所をつくってしまうのではないかと思います。差別主義者を擁護しているようにも聞こえかねないのであらためて強調しておくと、他人を傷つけ殺めるような差別的な言動は決して許されないし、それに対抗するための行動をとるべきだと思っています。
※画像はオンラインインタビューで撮影したスクリーンショットを使用しています。
RELATED ARTICLE関連記事



























