


『カウンター・ヴォイド再点灯から、アートとこの街の未来を考える』
観るだけのパブリックアートを 人の集まるプラットフォームへ。
- JP / EN
六本木を代表するパブリックアートのひとつ「カウンター・ヴォイド(Counter Void)」を手がけたのは、世界的にも知られる現代美術家の宮島達男さん。東日本大震災以降、消されたままになっているこの作品が、いよいよ「光の蘇生」プロジェクトとして、再点灯に向けて動き出しました。そもそもなぜ光を消したのか、そして再点灯のプロジェクトへと至った経緯、さらに3.11後の新しいアートのあり方まで、たっぷり語っていただきました。
カウンター・ヴォイドを消した理由。
現在カウンター・ヴォイドは、僕自身の意志で消したままの状態になっています。実はスイッチを入れさえすればすぐにつくんですが、あえてつけていない。そのきっかけは、3.11の東日本大震災でした。震災が起きてすぐ、自分がアーティストとして何をしなければいけないかを考えたとき、まずこの作品を消そう、と。もちろんエネルギーの問題もありましたが、大勢の人が亡くなったことに対する黙祷というか、鎮魂の意味を込めています。

カウンター・ヴォイド
高さ5m全長50mのガラススクリーンに表示された1から9までのデジタル数字が、それぞれ異なるスピードでカウントダウンを続ける。2003年にテレビ朝日の壁面に設置、2011年3月13日、作家自らの手で消灯された。
写真提供:テレビ朝日
震災直後には、東京にも節電の流れがあって、消しているのが当然という雰囲気がありました。それが復興が進むにしたがって、だんだん街のいろんなところに電気がつきだして、広告も光りはじめた。でも、自分としてはある種の違和感を持ち続けていて、再びつける理由が見つからないまま3年がたってしまったんです。
巨大なアート作品は、街の空間をねじ曲げる。
この作品はもともと、テレビ朝日が六本木に新しい社屋を建てるとき、建築家の槇文彦さんの依頼でつくったパブリックアート。よく「時刻を表しているんですか?」なんて聞かれるんですけど、そういうわけではありません(笑)。私が作品に使うデジタルの数字は人間の「生と死」の象徴で、カウンター・ヴォイドもテーマは同じ。ただ六本木の場合、昼間は白く光らせている数字を、夜は黒くしています。

テレビ朝日
六本木ヒルズ内に、2003年に完成した本社ビル。北側外周にはガラス張りの吹き抜けがあり、そのほかオフィスとスタジオが設けられている。敷地内には、「カウンター・ヴォイド」をはじめ、設計した槇文彦氏が選定した3つのパブリックアートが配置されている。
学生時代、よくディスコに踊りにきたりしていたように、言い方は悪いですが、六本木は僕にとって"ちゃらけた街"。そこにシリアスな生と死の現実というか、人間のヒューマンスケッチというか、そういうものを取り戻したいという思いが込められています。白と黒、どちらも死を表現していることに変わりはないんですが、黒のほうがより強調される。夜の六本木の風景のすぐ隣に、死が口を開けている、そんなイメージです。
巨大なアート作品が街に突然現れると、空間は変容していきます。空間がねじ曲げられる、そこにいる人たちが「圧」を感じるといってもいいでしょう。カウンター・ヴォイドに関していえば、狙いどおり、いや狙い以上でした。それは、街行く人がいろんなリアクションをしてくれたから。実際この作品ができてから、テレビをはじめ、いろいろなメディアがここで撮影をするようになりました。ある種、東京の風景の一部になったし、受け入れられているなあという実感があって、非常にうれしかったですね。
「あの作品をもう一度見たい」という声に押されて。
最近、「あの作品をもう一度見たい」という声をよく聞くようになって、そろそろ再点灯のタイミングなのかなと思うようになったんです。3.11のあと、節電によって東京の街は暗くなりましたが、それもゆるやかに解除されて、今ではもうエネルギーの問題なんて、まったくなかったかのよう。ただ、東北ではまだ仮設住宅に住んでいる人も多いし、再生に向かって踏み出せない人だっている。ならば、あえて今、再点灯することによって、もう一度3.11の記憶をとどめることができるかな、と。
一方で、「消えていたという事実」を浮かび上がらせる意味合いもあります。この間、六本木アートナイトでトークイベントをしたときに、お客さんから「カウンター・ヴォイドは、もともと光がついていたんですね」という話を聞いてショックを受けました。
ついていたことすら知らない世代が増えているとすると、「僕が消した」という意味そのものが不在になる。消し続けているというメッセージは、消したことを認識している人にしか伝わりませんから。再点灯することで、「じゃあ、なんで消えていたの?」というフィードバックにつながるんじゃないか。そんな狙いもあって、「光の蘇生」プロジェクトをはじめることにしたんです。

アートは、アーティストのものでなく見る人のもの。
3.11のあと、作品をつくる手が止まってしまった時期がありました。理由は、3.11を境にアートの姿が変わってしまったから。3.11以前のプレゼンの仕方といえば、アーティストが作品をつくって「ほらお前たち見ろ」というもの。天才がつくった作品をありがたがって見るようなマッチョな世界観です。
もっといえば、そうした資本主義的な構造を推し進めてきたのが、20世紀という時代でしょう。でも、その流れは限界にきている。3.11によって、自然はコントロール不可能で、畏敬の念を持たないと人間はたちまち立ち行かなくなるというのも明らかになった。だとするとアートも、資本主義的なマッチョな世界観ではなく、もっと違った形でつくり上げなければならないのでは......。
「光の蘇生」プロジェクトの一番のキモは、見る人たちがアートを血肉化していくこと。つまり、アートというのは、つくったアーティストのものではなくて、見る人たちのものだということです。一人ひとりが、作品をどう捉えどう考えていくのか。誰がつくったかではなくて、何を感じられるかに重きを置く。それが本来のアートの姿だと思うんです。僕は3.11以前から、「Art in You」をテーマに、さまざまな展示やワークショップを行ってきましたが、今回のプロジェクトは、まさしくこの概念を社会化するプロセスだと考えています。
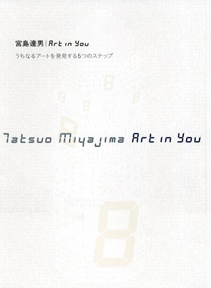
「Art in You」
「アート的な体験や感動は、受け手一人ひとりの想像力の中にある」という、宮島氏が提唱するアートの考え方。この概念をテーマに、2007年には広島平和記念公園など国内4ヵ所でワークショップキャラバンを実施、2008年には水戸芸術館で同名の展覧会を開催した。
「光の蘇生」プロジェクトは、一般の人が主役。
大きな目的は、3.11の記憶を再びよみがえらせること。それとともに、3.11以降のアートのあり方や、街のあり方を考える場にもしたいと思っています。たんに電気をつけるだけならば、ただ行ってスイッチを入れればいい。そうではなく、エネルギー問題をへて、どんな姿だったら再びつけることが許されるんだろう、一番いいのはどういう形なんだろうと議論を重ねる。しかも、作品を見ている一般の人たちに考えてもらって、再生してもらう。

「光の蘇生」プロジェクト
東京文化発信プロジェクトとNPO法人ArchARTが主催。勉強会をはじめ、市民と議論や対話しながら「カウンター・ヴォイド」の再点灯を考えていくプロジェクト。写真は、六本木アートナイト2014で行われたワークショップの様子(©蓮沼昌宏)。
http://countervoid.com/
アーティストが「もう1回つけたいから、寄付してよ」と言って、ワーッとやるのは簡単。いや、たいへんな予算がかかるので簡単ではありませんが(笑)、できなくはない。ただ、3.11以降のアートのあり方としていいのかというと、そうではないでしょう。
ネオン管は消費電力が大きいから、LEDに換えたほうがいいんじゃないか。太陽光発電で電力をまかなうことはできないか。極端なことをいえば、話し合った結果、やっぱり消しっぱなしにするという選択だってないわけじゃない。だいたい、この作品は、テレビ朝日に引き渡した段階で、もう僕のものではありません。僕は"娘"を嫁に出した、ふるさとのお父さんみたいな存在ですから(笑)。
最終的に、こういう形にしようと決まったら、ようやく具体的にどれくらいのお金が必要で、どんな工事が必要でという話になる。そんなプロセスを経て、3年くらいかけて、なんらかの結果が出せたらいいなと思っています。
アート作品=未来の生き方を考えるツール。
通常のアートプロジェクトって、アーティストとパワーを持った人たちが5〜6人集まると、なんとなく実現できてしまう。でも、今回はそうじゃなくて、もっと草の根的に広がっていくイメージ。たとえるとしたら、こんな感じでしょうか。
アート作品(カウンター・ヴォイド)は、僕が生み出した娘のようなもので、その娘が病気にかかってしまった。海外で手術をしなくちゃいけないんだけど、それにはお金がかかる。だからお父さんが頑張って「治療させてください」と訴えてお金を集める。と、これはけっこうマッチョな方法。一方で、娘のキャラクターに魅力があれば、友だちづてに支援が広がって、自然とお金が集まったり、他の方法をリサーチしてくれたり。お父さんはそれを見守って、感謝の言葉を述べたりサポートしたりするだけ。
僕にとって今回のプロジェクトは、後者の関わり方。主体的に動くのはあくまでNPOであり、市民のみなさん。アーティストがしゃしゃり出ると、どうしてもマッチョな構造体になりがちだし、僕が言っていることが正しい、という話になってしまいますから。
アートってもともと「人間とは何か」を考えるきっかけであって、アート作品は「未来の生き方を考えるツール」だと思うんです。このカウンター・ヴォイドという作品を通して、僕らが未来の社会のあり方、人間のあり方を考えていく。そういうプラットフォームになったらすばらしいなと思っています。

コンセプトが変わらなければ、何度つくり替えたっていい。
20年くらい前、日本のある企業がお金を出して、バチカンのシスティーナ礼拝堂の壁画を修復したことがありました。そうしたら、あまりにピカピカになりすぎて、こんなはずじゃなかったってみんな怒ってしまった。修復にはそういうリスクもある。僕自身は自分の作品を修復したい、再点灯したいという気持ちとともに、ひとつの"判例"をつくりたいという思いがあります。
アート作品が未来にわたって人々の共有財産になるためには、どんな姿が一番望ましいのか。みんなの意識や議論を積み上げることで実現していく。それが判例になれば、他の作品も同じように修復される可能性があるし、ノウハウだってできる。そういうことをやっていきたいんです。
とくにコンテンポラリーアートは、メディアを使った作品が多く、古びていくし壊れていきます。たとえば、ナム・ジュン・パイクの有名なブラウン管を使ったアート。とてもすばらしい作品ですが、今はブラウン管が製造されていないので、壊れたら二度と見られないわけです。だから、ナム・ジュン・パイク アートセンターでは、ブラウン管テレビの外側だけを使って、中を液晶画面とDVDに変えて展示しているんですね。いいか悪いかは別として、いろんな修復の仕方があるし、そうしないとコンテンポラリーアートの作品は永遠に残っていかないんです。
ナム・ジュン・パイク
メディアアートの第一人者(1932-2006)。1963年に初めてテレビモニターを使ったビデオ作品を発表、その後も先進的な作品を発表し続け、「ビデオ・アートの父」とも呼ばれる。韓国京畿道龍仁市にあるアートセンターには、数多くの作品がアーカイブされている。
僕は「Sea of Time」というLEDの作品を初めて発表した当時から、テクノロジーにはおよそ限界があると気づいていました。作品はコンセプトやデザイン的なメソッドだけを残したまま、永遠に何度でも繰り返しつくり替えられることを想定していた。つまりネオン管がLEDに変わっても、「生と死」というコンセプトさえ変わらなければ問題ない。伊勢神宮は20年に一度遷宮をして建物を新しくしますが、その方法とデザインは変えません。そうやって精神性を永遠たらしめているのと同じです。

「Sea of Time」
床一面に敷き詰められたLEDの数字が、暗い部屋の中で明滅する。1988年、ヴェネツィア・ビエンナーレに出品され、世界的に高い評価を得た、宮島氏が発表した初のLED作品。写真は、直島の家プロジェクト「角屋」に設置されている「Sea of Time '98」。
写真提供:ベネッセアートサイト直島
再点灯したからといって終わりじゃない。
かつてカウンター・ヴォイドができて1〜2年は、新鮮なアート作品が突然現れたことで、六本木の街にはある種神聖な空気が流れていました。それが3年くらいたつと日常に変わって、慣れてしまう。どういうことが起こるかというと、作品の前に自転車やバイクを置く人が現れます。自転車の数が増えて作品が見えなくなると、今度はそれを嫌がるテレビ朝日が駐輪禁止のコーンを置くようになる。当たり前ですが、そんな状態で作品を見ても、全然よくないわけですね。
アート作品やパブリックアートは、手を入れていかないと、常にこうした問題が起こる可能性がある。そうならないようにするための対策を考えることも、デザインとアートの街、六本木の未来を語るうえでは重要でしょう。
先ほども言ったように、僕はカウンター・ヴォイドはプラットフォームだと考えています。このプロジェクトの運動体であるNPOを中心とした人々のアクティビティは続いていくことを想定しているし、続いていってほしい。再点灯したから終わりというんじゃなくて、再点灯したあと、どんなふうにこの作品を活用していくのかも含めて、継続して活動していってもらいたいですね。
カウンター・ヴォイド前の歩道をパフォーマンスの場に。
これは勝手な提案なんですが、カウンター・ヴォイドの前の歩道って、けっこう広いんですよ。そこを、何かパフォーマンスのできる場所にしたらいいんじゃないかと。今の六本木って、情報は飛び交っているけれど、生の人間のアクティビティが足りないような気がしていて。
肉体で表現するダンサーや大道芸人たちがパフォーマンスを披露できる場所があったら、すごく楽しい街になるんじゃないかと思うんです。カウンター・ヴォイドをアート作品としてだけでなくプラットフォームにして使っていくと、慣れることがなく、常にフレッシュな何かが生成される場になる。そういう場を運営する母体として「光の蘇生」プロジェクトが発展していってくれたら面白い。

カウンター・ヴォイドの前の歩道
けやき坂通りと環状三号線の交差点、TSUTAYA TOKYO ROPPONGIの向かいにある広場のようなスペース。カウンター・ヴォイドの前には幅の広い歩道が敷かれ、ストリートファニチャーが設置されている。
ややこしい話をたくさんしてしまいましたが、どんなにかっこいい街でも、人が行き交う場所である以上、泥臭い部分は外せません。情報化社会でインターネットがどうしたなんていっても、人間らしいリアルな部分は絶対に捨てられないし、変えられない。最近、アートの世界でパフォーミングアーツが再評価されているのも同じ。僕もそうしたリアリティをベースに、アートや街がつくられていったらいいなと思って、いろいろ考えているところです。
取材を終えて......
この取材は、公開インタビューとして行われ、終了後には未来会議読者のみなさんとの交流会も。インタビュー中も交流会でも、カウンター・ヴォイドを"娘"にたとえていた宮島さん。個人的には、かっこいい"息子"のイメージなのですが......みなさんはどうでしょうか?(edit_kentaro inoue)
RELATED ARTICLE関連記事



























