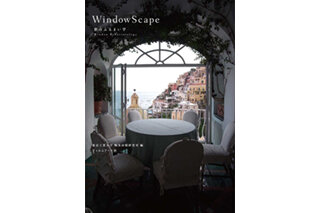PROJECT
六本木未来会議アイデア実現プロジェクト #15
「六本木、旅する美術教室」第11回 アーティスト布施琳太郎の「地球と生きるためのデザインの見方」【後編】
update_2023.01.18
photo_masashi takahashi / text_yoshiko kurata
六本木の美術館やギャラリーを舞台に繰り広げられる「六本木、旅する美術教室」。アートディレクター尾原史和さんがインタビューで語った「アートの受け手側の"考える力"は、教育的なところから変えていくべき」という提案を実現するべく、クリエイターやアーティストのみなさんに、その人ならではの美術館やアートの楽しみ方を教えていただきます。
第11回目の「旅する美術教室」の舞台は、TOTOギャラリー・間で開催中の企画展『How is Life? ――地球と生きるためのデザイン』。本展は4名の建築家、建築史家がキュレーションし、古今東西の多彩な事例や作品を紹介しています。今回の先生、布施琳太郎さんもまたアーティスト活動と同時にキュレーション活動を精力的に行い、多数の展覧会を主催しながら、新たなアートシーンを切り開いている存在です。本展のキュレーターの1人、建築家の塚本由晴さんとともに、地球と建築の関係性、そして今どのように生きるか、など、地球と生きるためのデザインの見方について探っていきます。
六本木、旅する美術教室 第11回
「地球と生きるためのデザインの見方」
- #1
- 未来の芽を育てる当事者になる
- #2
- 便利さで不可視になっているものを想像する
- #3
- 行ったり来たりの"間"に注目する
- #4
- 身体の感覚から理解する
- #5
- 不変の法則を知る
- #6
- 企画者の問いを共有する
動き続ける建築をどう見せるか。
展覧会観賞後、あらためて建築と現代美術の展覧会の違いについて振り返ります。布施さんは「プレゼンテーションの仕方」に注目していたそう。塚本さんは、現在の建築の状況と併せて、建築展で何を表現するべきか、を説明します。
布施琳太郎今回は、特別に予習をしてから見るというよりは、自分が普段どのように展覧会を見ているのかを伝えられたらと思いました。僕がいつも展覧会を見ていて楽しいと思うのは、まず会場になんでこんなものが置かれているかわからないと感じられること。そこから、伝えたいことがわかったり、伝えたいことを手探りしている様子を感じられたりする。そういう意味で、建築展は異なるプレゼンテーションの仕方があっていいなと思いました。
塚本由晴建築展となると、完成された図面と模型を見せるのが古典的なやり方。ところが、建築をめぐる今の状況を見ると、ずっと動いている感じなんですよね。いつ終わるんだろう、というのがわからないくらい、揺れ動きながら進んでいる。そんな姿を、どのように展覧会で表現するのかは大きなチャレンジでした。鑑賞者の方々としては、建築と自分を切り離さず、建築に触れている時に生まれる感情を思い出して、自分ごととして受け取ってもらえればいいのかなと思います。
自分事として捉える体験として、布施さんは「身体的にわかる」瞬間があったそうです。
布施僕の関心と合致しているのもあると思いますが、壁面にあった4象限の図を見てから、作品があって、ギャラリーの外に建つ街のビルがあって、と図と風景が繋がっていったんです。それは思考のモデルとしてだけではなく、身体的にわかる瞬間だったな、と。その時、すごく景色が広がる感覚がしましたね。
塚本今回展示しているものは、本来はバラバラに活動してきたものです。でもどこか仲間が一緒に集まってきているようにも感じられて、こんなに同じ感覚の仲間がいるんだということを見せられたと思います。そういった感覚が芽生えたならば、嬉しいですね。
【地球と生きるデザインの見方 #4】
身体の感覚から理解する
里山で培う人間の感覚と想像力。
今回の展覧会を通じて、どのような感覚や想像力を伝えたかったのでしょうか。塚本さんは、普段活動している里山での体験を引き合いに出しながら、説明してくれました。
塚本今って目の前のものがどこから来たのかを考えなくていいし、信用してしまっていますよね。それでも服や食事については、ずいぶんトレーサビリティを問題にするようになってきました。一方、建築は材料が多いし、プロセスも複雑で、なかなか追いきれない。なので里山の活動では、身の回りの山の木や田んぼの土を使っていろいろとつくろうとしています。そうやってできるだけ目に見える事物の連関からつくることを出発点にして、そこからなぜ都市でこれができないのか、を考えたいんです。都会の建築家が里山で活動するのは、レジャーと変わらないと言う人もいますが、自分たちを取り巻いている障壁が見やすくなるのは確かです。
布施ちょっと違う話かもしれませんが、都市の子どもにマグロの絵を描いてもらうと、「切り身」を描いたという話を聞いたことがあります。レジャーじゃないかという批判があったとしても、里山のような体験を重ねていかないと、おそらく永遠に頭があって尻尾がある魚へと想像力がたどり着かないですよね。やっぱり死があるから食べ物があるわけで、そういう人間の良心にとって不都合なことに対していたずらに蓋をして暮らし続けるのもよくないと思いますね。

積み重ねられた「振る舞い」の法則を学ぶ。
布施さんと塚本さんは、ともにつくり手、表現者でもあります。布施さんからは、里山などの体験をふまえて、これから建築家やつくり手を志す人々は、どんな知識や技術を基礎としていけばいいのか、という問いを投げかけます。
布施藝大の先生になった知り合いがいるのですが、現状「アートの基礎が何なのかわからなくなっている」と言っていて。これから建築を志す人々は、里山の体験や都市の体験をふまえて、どんな知識や技術を基礎にしてやっていけばいいのだろう、と気になりました。
塚本私が担当する学生によく言うのは「ふるまい」から何事も考えること。ふるまいというのは、文化的な蓄積から出てきたものもあるし、身体のつくりから出てきたものもある。また人間だけじゃなくて、水や光や熱にもふるまいがあるし、違う街に行けば、違う建物が並んだ風景があるように、建物にもふるまいがある。
水が高いところから低いところへと動くのは水のふるまいですが、面白いのは、ふるまいはその対象に埋め込まれていて、われわれはそれを変えることができないということです。できるのは、ふるまいの範囲を決めることで、目的に合わせてその働きをよく引き出すこと。事物のふるまいを理解する上で、物理学や化学や生物学などの自然科学、文化人類学や民俗学などの社会科学がとても役に立ちます。
布施なるほど。ふるまいの中にある不変の法則や特殊な出来事の積み重ねの歴史や営みがあって、それを統合できるような技術が基礎になってくるんじゃないかなってことですね。
塚本デザインの役割はそこだと思うんですよね。ものづくりでも料理でも、ものに即した不変の法則や、変わらないふるまいがあることを理解しないと、うまくいきません。人は何をしているかというと、法則を繰り返し利用できる型みたいなものを見つけている。ものがなりたいように、ふるまいたいように仕向けているのだと考えれば、人間が全部やってるんだと気負わなくて済むのではないでしょうか。
【地球と生きるデザインの見方 #5】
不変の法則を知る
展覧会の空間で起きていること。
昨今、クリエイターやアーティストが自らキュレーションを手掛ける展覧会や展示が増えているように見受けます。自ら展覧会をキュレーションするお2人に、自身で企画することの狙いやその先にあるビジョンとは一体どのようなものなのか、についてお伺いしました。
布施自分でキュレーションすることによって、誰かからの依頼や要請で展示しなくていい、というのはすごくいいことだと思います。つくられた枠組みの中で、自分を位置付けることを考えてなくていいんです。美大生は、自主企画の展覧会はよくあることなのですが、その中で僕はたまたま流れに乗って、だんだんと規模も大きくなってきました。キュレーターや批評家を介さずに自分自身で価値をつけられるので、「ズル」と言われることもあるのですが......。
塚本それは面白いね。
布施今回、塚本さんに解説いただく中で、塚本さん自身のプロジェクトでありつつ、たまたま偶然出会った作品をセレクトしてもいるという、企画者の実感と探求がキュレーションに込められているなと感じました。それはいわゆるキュレーションの部分と、何かある種のコラボレーションの成果物を出している部分がシームレスに繋がっているようでした。そういう面も「ズル」にはあるな、と。
塚本そう言ってもらえると、今回の展覧会はうまく「ズル」できている気がします(笑)。私も建築展のキュレーションにはこれまで何度か関わってきました。もちろん建築をつくることは肝心なのですが、複数の建築を時代によらず並べることで、今、何を考えるべきか問いかけるには、様々な人と共有できる展覧会が良い。そんな「批評空間」を組み立てることも、建築家の大事な仕事ではないかと思っています。
【地球と生きるデザインの見方 #6】
企画者の問いを共有する
「地球と生きる」ためには、身体の感覚からモノや環境を捉えることが重要。普段のわたしたちの「ふるまい」を、あらためて振り返ってみたくなる講義となりました。展覧会会場には、今回触れた塚本さんがキュレーションされた作品とともに、たくさんの作品(千葉学氏、セン・クアン氏、田根剛氏キュレーション)が展示されていますので、ぜひ足を運んでご覧ください。
information
TOTOギャラリー・間 企画展 How is Life? ――地球と生きるためのデザイン
会場:TOTOギャラリー・間
2022年10月21日(金)~2023年3月19日(日)
開館時間:11:00~18:00 事前予約制
休館日:月曜、祝日 ※2023年2月11日(土・祝)は開館。
展覧会情報:
>https://6mirai.tokyo-midtown.com/event/how_is_life/
RELATED ARTICLE関連記事