
PROJECT
六本木未来会議アイデア実現プロジェクト #15
「六本木、旅する美術教室」第3回 美術家やんツーの美術展の見方【後編】

update_2018.07.25
photo_masashi takahashi / text_momoko kawano
六本木の美術館やギャラリーを舞台に繰り広げられる「六本木、旅する美術教室」。クリエイターやアーティストのみなさんに先生になってもらい、その人ならではの、美術館やアートの見方を教えていただきます。 第3回の先生は、デジタルメディアを基盤に、文字や身体にまつわる作品を多く制作する美術家のやんツーさん。訪れたのは、国立新美術館で開催されている『ルーヴル美術館展 肖像芸術―人は人をどう表現してきたか』。この展覧会のキュレーターの宮島綾子さんに案内していただきます。古代から1848年までの美術作品が収められているルーヴル美術館と、デジタルアートの領域であるやんツーさんの作品は、扱う作品の時代性がまったく違うようにも感じられるかもしれません。けれども、今回の美術教室では、古代と現代美術がつながっていることを節々と感じることになりました。
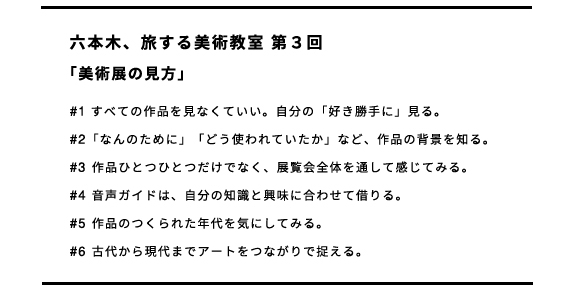
自分らしく展示を見ると、自分が何に興味があるのかわかってくる。
アウラ
批評家・哲学者のヴァルター・ベンヤミンが著書『複製技術時代の芸術』などで唱えた概念で、複製技術時代の芸術作品において、芸術家の作品のオリジナルから感じられる、崇高で、一回限りの特有な輝きを示す。
美術家として、いくつもの作品を発表してきたやんツーさん。今と昔では、展覧会の見方が変わったそうです。なぜでしょうか?
「昔は、ひとつひとつしらみつぶしに見ようとしていたんですよ。でもたくさんの作品を同じ熱量で見ていると、時間もかかるし、半分くらいで疲れてしまう。今は、気になったものをじっくりみます。目が止まらないものはサッと流してしまいますね。
そう変わったきっかけは、2013年に米小説家トレイシー・シュヴァリエのTED TALK『絵画で見つける物語』をYoutubeで観たこと。プレゼンテーションの中で作品の見方について多く語っていた彼女が『興味がないものは飛ばしましょう』と言っていて、救われた気持ちになりました。僕たちはもっとカジュアルに展覧会を見にいっていんじゃないでしょうか」
展示を案内してくれた宮島さんも「好きに、自発的に見て欲しい」と言っていました。ふたりとも、与えられたもので説明を読むだけでなく、自分の興味にひきつけながら自発的に見ることをすすめています。自分の「好き勝手に」見るようになったやんツーさんは、あることに気づきます。
「自分の興味の赴くままに鑑賞していると、作品そのものよりキャプションを見ている自分に気づきます。ふと『作品を見てないな、ダメだな』と思うこともあるんですけれど、やっぱり無理に見方を変える必要はない。自分の鑑賞態度は作品そのもののアウラを感じるよりも、どちらかというと意味や文脈で理解して楽しむほうが比重として大きいです。自由にしているうちに、自分がどういうところに興味があるかは明確になっていくと思います」
また、自身も作家だからこそ、展示のしつらえも見ると言います。どういうふうに絵画がかけられているか側面を覗き込んだり、どのように壁紙を貼ったか、どれほど手間がかかっているかなど。ときには、全然作品を見ていないことに気づいたりもする。それでも「それはそれで自分はおもしろいし、オッケーかな」と笑います。
「見るのは、半分趣味だけど、半分仕事。作家として見るのは義務。現代美術も古典的なものも、なるべくインプットして、自分が展示するときの参考にします」
それも、やんツーさん独自の見方と言えます。
「あとは、音声ガイドは基本的につけません。耳で聞くと、自分のペースで見られなくなってしまうので。誰かと来てもひとりで見て回ります。何を見るかも事前に決めず、その場の成り行きに従います。気になったものは戻ってもう一度見ることもありますね。その場で気になったことや、わからなかったことは、家に帰って自分で調べます。結局、自分が気に留めたものしか記憶に残らないんです」
特にルーヴル美術館展のように老若男女の幅広い世代に人気のある展示には、事前知識のない方から、深い知識のある方までさまざまなお客さんが来場します。「それぞれの知識と興味に合わせて、必要であれば音声ガイドを使い、自分の楽しみを見つければ良いのでは」とやんツーさんは提案します。
【美術展の見方#4】
音声ガイドは、自分の知識と興味に合わせて借りる。
「自分が作品を展示するときも、お客さんには好きに見てほしい。僕は、自分が疑問を持ったことについて作品をつくっているので、キュレーターと違ってお客さんのことはあまり考えてないかもしれないですね」
これまで見て好きだった美術館や展示の共通点は、"インパクトがあって、理解できないもの"だと話します。
「杯のまん中に男性の顔の彫刻が置かれていた『ボスコレアーレの至宝』のように、『なんだこれ!? 』と思うような作品に出合うとソワソワします。今まで印象的だった美術館は、スペインのビルバオ・グッゲンハイム美術館。岡本太郎の世界観をソリッドにしたような印象のとんでもない建築でした。そして印象的な展覧会、いろいろあるんですがなぜかすぐに思い出すのが、2013年にロンドンのヘイワード・ギャラリーで開催された、マーティン・クリードの展覧会。なかでも巨大な"MOTHERS"というネオン文字の看板が展示室の中で回転する作品が一番印象的で、壁から数センチのギリギリのところを回る"MOTHERS"の文字が非常にスリリングでありながらとても大らかに見えてなんだかよくわからない気持ちにさせられました」
現代美術についても、すべてをロジックで説明しきれない作品が好きなのだと話します。
「ある程度までは説明できてしまうんですけど、最後の1割に作家の感覚を感じるときに、ぐっときます。それまでわかっていた気になるのに、最後に『ああ、わからない』と思わされる。顔面を強く殴られ、新しい概念を植え付けられたようなショックを受ける瞬間が、現代美術にはあります」

どの時代の作品も、すべては地続きに繋がっている。
どんな展覧会を見ても、自分ごとに置き換えて考えることができるやんツーさん。それは美術を仕事とするものとしてのスタンスでもあります。やんツーさんが手がけるのは現代美術やメディアアートと呼ばれる領域ですが、古典と呼ばれるものも含め、あらゆる美術展に足を運びます。その理由をうかがうと、現代美術界が抱える課題が見えてきました。
「僕は、自分がテクノロジーを用いてつくる作品は、古典の美術作品の地続きにあるのだと考えます。"印象派も写実主義も、かつては最先端だったはず"とはよく言われることです。油絵の具やキャンバスが発明された当時は、それらメディアを用いた作品が最先端のテクノロジーを使ったメディアアート的なものだったはずです。ですから作品を見るときは、年代を気にしますね。そうすると、美術全体の歴史の流れが見えてきますので」
その時代、その作品は一体どういう役割だったのか。それを想像しながら見ることで、当時の人々の雰囲気まで感じられる......そういう人の生活のつながりの先に、現代があるのだと考えています。
「例えば古典美術からメディアアートまで、それらを一連の地続きのものとして捉えられると、作品をもっとおもしろく感じるはず。現代美術を見ない人は美術をつながりで捉えることができてないのかもしれません」
【美術展の見方#5】
作品のつくられた年代を気にしてみる。
「多くのメディアアートの作家にも、同じようなことが言えそうです。エンジニアサイドからメディアアートの作家になる人は多いので、むしろ"メディアアートはエンジニアリングの延長だ"と捉えられがちで、美術の歴史から地続きであることに多くの作家が無自覚です」
やんツーさんは「美術とエンジニアリング、両者の歩み寄りが必要だ」と言います。
「理系出身の人が美術の勉強をして、美術や文系出身の人がコードを読めるようになるといいですね。両方の文脈からの理解、歩み寄ることが必要で、両者とも足りていない。美術畑でコードが書ける人は少ないけれど、僕は全人類プログラムは読めたほうがいいくらいに思います。反対に、エンジニアリングが得意な作家は文脈で美術を理解できると、美術畑の人にも注目される作品がつくれるのではないでしょうか」
当のやんツーさんは、もともと美術にもプログラミングにもそれほど興味がなかったと言います。大学受験ではグラフィックデザイン学科を受験したのですが合格ならず、滑り止めだった情報デザイン学科に入りました。入学当初は美術どころかメディアアートにすらあまり能動的に興味を持てず、学部4年でようやく本腰をいれて作品制作に取り組み、大学院で本格的にメディアアートを研究しはじめ、そこからようやく美術に目を向けるようになったそうです。
「現代美術の展覧会は、来場者がとても少ないのが現状です。美術について、多くの人はおそらく印象派くらい(1910年ほど)までは興味を持つけれど、次時代の抽象表現主義あたりから、突然理解を示さなくなる。それ以降のリテラシーが低いんだと思います」
ではどうすればいいのか。それは「教育」から変えられるというのが、やんツーさんの実感です。
「僕は今、大学でメディアアートを教えていますが、これまでのメディアアート教育がいかに美術の話をしてこなかったかということを実感しています。自分が学生のころ、プログラミングや電子工作を行う演習授業はあったのですが『なぜ美術についての技法ではなく、これらの技術を学ばなければいけないのか』『なぜ美大に来たのに工学部のようなことをしているのか』という疑問が常にあり、そこに関して説明する教員はほとんどいませんでした。ハウツーとして技術は教わるのですが、それが魅力的で意味のある表現のためのスキルということに結びつかず、その時はほとんど身にならなかったです。技術が過去の作品や自分の表現にどう関わってくるのか、うまく説明できればプログラミングにアレルギーがある学生がもうちょっと減るんじゃないかと考えています」
【美術展の見方#6】
古代から現代までアートをつながりで捉える。
現代の最先端の作品を制作するやんツーさんには、『ルーヴル美術館展』のプロローグにある3,000年以上前のマスクと、2018年の美術が繋がって見えているのでしょう。自分らしく、自分の「好き勝手」に展示を見ると、また違った美術館の姿、アートの魅力が見えてくるかもしれません。
information
ルーヴル美術館展 肖像芸術―人は人をどう表現してきたか
会場:国立新美術館 企画展示室1E
会期:2018年5月30日(水)~9月3日(月)
開館時間:10:00~18:00 ※金・土曜日は21:00まで ※入場は閉館の30分前まで
休館日:毎週火曜(ただし8月14日は開館)
観覧料:一般1,600円、大学生1,200円、高校生800円
展覧会サイト(URLをクリックすると外部サイトへ移動します):http://www.ntv.co.jp/louvre2018/
RELATED ARTICLE関連記事



























