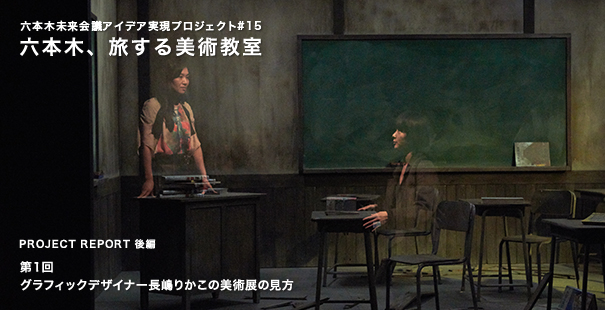
PROJECT
六本木未来会議アイデア実現プロジェクト #15
「六本木、旅する美術教室」 第1回 グラフィックデザイナー長嶋りかこの美術展の見方【後編】

update_2017.12.27
photo_yuta nishida / text_akiko miyaura
クリエイターインタビューで生まれたアイデアを実現するプロジェクトの第15弾は、六本木の美術館やギャラリーを舞台に繰り広げられる「六本木、旅する美術教室」。アートディレクター尾原史和さんがインタビューで語った「アートの受け手側の"考える力"は、教育的なところから変えていくべき」という提案を実現するべく、クリエイターやアーティストのみなさんに先生になってもらい、その人ならではの、美術館やアートの楽しみ方を教えていただきます。 第1回の先生は、グラフィックデザイナー長嶋りかこさん。ガイド役は、森美術館キュレーター椿玲子さんです。教室の舞台となったのは、『レアンドロ・エルリッヒ展:見ることのリアル』。一体どんな美術教室になったのでしょうか。
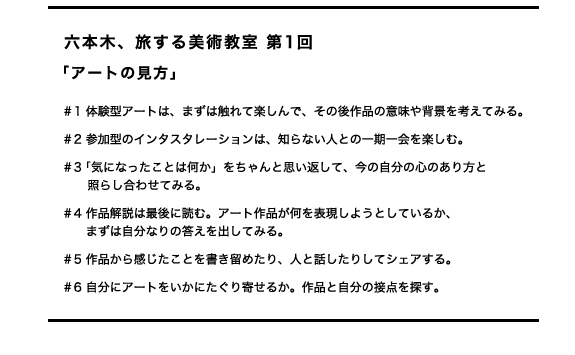
作家の思考に触れ、どう社会にメッセージを届けるかを学ぶ場所、美術館。
自身が設立したデザイン会社「Village®」で、グラフィックデザイナーとして、多くのデザインを世の中に送り出している長嶋りかこさん。刺激やヒントを求め、積極的に美術館へ出向くようになったのは「仕事を始めてから」だと言います。
「やっぱり、仕事になると"何のためにデザインするのか"って自分に問いかけるようになるんです。デザインって、言ってしまえば"受注"の仕事。"こうしたい"とビジョンを持ったクライアントがいて、それをどう形にするのかの答えを出していくのがデザイナーだと思うんです。
一方、アーティストは自分のなかに"こうせざるを得ない"という切迫した必然性や答えがあって、それを形にしていく作業をしていると思うんです。そういう意味でデザインとアートは成り立ちがまったく違う。ただ、デザイナーがアーティストの持つ姿勢なくして、クライアントの受注に答えを出していくことが正しいのかと思うと、そうではないと感じることが多いんです」
相手のなかにある答えを見つけるデザイナー、自分のなかにある答えを形にするアーティスト。一見まったく違うアプローチにも感じますが、デザイナーとして"アーティストの姿勢"を知り、感じ取ることが大事だと長嶋さんは考えます。
「美術館は、アーティストが世の中にどうリアクションして、作品を通じてどう社会にメッセージを送っているのかを感じとれる場所。作家の思考に触れるたび、デザイナーとしても、その姿勢を持って仕事をしたいと感じるんです。自分発信のプロジェクトであれば当然ですが、受注仕事の場合でもです。たとえばプロダクトでも建築でもグラフィックでも、そもそもの依頼に社会的な意義を感じない場合、その仕事を受けない、という判断ができる。人の思いを形にすることはデザイナーの大きな役割ですが、そもそもの起点が正しいのかを疑ったり、クライアントと共に掘ったりする姿勢が必要なんです」
長嶋さん流、美術館の楽しみ方。
「展覧会全体のテーマが掲げられた、入口のテキストはしっかり読みますね。でもそれ以降は文章に目を通さず、先に作品を見ることがほとんど。作品を通じて作家が伝えたいのは、こういうことかなと自分なりに答えを出してから、作品の説明を読みます。あらかじめ見てしまうと想像が広がらず、それだけになってしまうから。まずは勝手にあることないこと考えて(笑)、自分がどう思うかを咀嚼してから、作家やキュレーターの意図を情報として入れます。合っているときは"合っていた!"って嬉しくなるし(笑)、合っていなくても"そういう考えがあるのかと視座が増える。そこに正解はないと思うんです」
【アートの見方#4】
作品解説は最後に読む。アート作品が何を表現しようとしているか、
まずは自分なりの答えを出してみる。そこに正解・不正解はない。
まっさらの状態で作品から感じ取り、自分で思考してから、作家やキュレーターの意図を知る。ひとつひとつの作品を丁寧に見るため、「すごく時間がかかるんですよ」と長嶋さんは笑います。
「だから、1日でいくつもの展覧会をまわることはできなくて(笑)。行けて、せいぜい2か所。それに、あまりたくさんの情報を入れすぎると情報として入ってきやすい外側だけを見ることになるので、つまらないじゃないですか。できるだけ流れにそって、1作品ずつじっくり内側も見たいんです。作家が思考したであろう道筋を辿ることで、デザイナーとしてものを考えるときのヒントになりますし、自分が気になるポイントを通じて現在の自分自身が抱いている思いや疑問に気づけます。
そう考えるとアートを見るときって、自分の心のあり様を問われている感じがするんです。あと、自分が感じたこと、捉えたことをメモしたり、人と話してシェアしたりもしますね。異業種の友人と一緒に展覧会を見るのもおもしろい。その場で意見交換ができて、思わぬ広がりがあります」
【アートの見方#5】
作品から感じたことを書き留めたり、人と話したりしてシェアする。
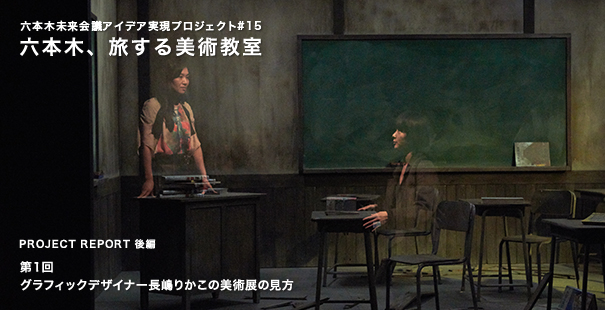
『教室』 2017年
ものの見方をどう学校で教えていくか。
これまで見たり、触れたりした美術館、展覧会で心に残っているものをたずねると、日本の芸術祭の名前があがりました。
「近年は日本でも芸術祭が乱立していますが、日本に芸術祭がまったくなかった頃に見た『瀬戸内国際芸術祭』や『越後妻有 大地の芸術祭』は衝撃が大きくて。社会に明確に機能する芸術のあり方を作れるんだな、と驚きました。今は乱立してしまったことや、芸術に明確な役割を求めすぎたことの悪い側面も出てきていると思いますが、誰でも気軽に美術に触れる機会ができたことは良い面だと思います。海外だと美術館には無料で入れるのに大規模な展覧会をやっていることもあって、お年寄りも子どもも公園感覚で美術館に入ってアートに触れる。そんな環境は、すごく意義があるなと感じていたので」
たしかに、日本は気軽にアートに触れる機会が多いとは言えないのかもしれません。美術館に行くことへのハードルが高いのは、美術教育にも理由があるのではないでしょうか。
「私は美大出身ですが、振り返るとどうしても手法を習うことが主となりがちだったと感じました。美術教育って、本当は"ものの見方"だと思うんですよ。何をどう捉えたのか、なぜ作るのか。その"なぜ"を形にするために"どうやって"作るのかっていう、そこで初めて手法の話になるはずなんですよね。自分がつくる意味に自覚的であればあるほど、作ったものは人に何がしかの影響を与えるのではないでしょうか。ものの見方の意見がある作品は、作ったものが人に与える影響も変わる。
見た人にとっては、日常がひっくり返るとか、見えてこなかったものが見えるようになり始めたり、世の中の小さな声が大きな声になったりする。そういう大きな変化を、もたらす可能性があるんですよね。
日本だけかもしれませんが、振り返ると美術教育は"なぜ"より"どうやって"が先行している気がします。逆に欧米では"なぜ"にとことん向き合う。例えば日本人の若い建築家志望の学生は世界ですごく重宝されると聞いたことがあります。理由は、めちゃくちゃ精度の高い模型が作れるから。その現状が本当なのだとしたら、教育の現場の一側面を表している気がします」
日常では出会わない、別の言語を知る。
廃校になる小学校の生徒に向けて、過去にワークショップを開催した際、こんな試みをしたと言います。
「小学校での思い出を絵に描いてもらったんですが、その際に絵を描くための道具ではなく、おはじきやビーカーなどを渡して、それで描いてもらいました。そうするといつもは書かないような、別の新しい言語が生まれるんです。
たとえばある子は騎馬戦を描いたのですが、抽象的な絵なのに闘っている状況とか熱量とかがわかるんですよ。実際に描いた子どもも、"あ、なんか描けた"と手応えを感じていました。自分が今まで描いてきたり見てきたような、具体的なものとは違う、別の騎馬戦があるんだという事実が目の前に立ち現われる。それが、すごくおもしろかったですね」
その感覚はアートをいかに自分にたぐり寄せるか、ということでもある。美術館を楽しむときもその感覚が大切。
「これまでに出会ったことのない、見たことのないものにも、どこかに必ず接点があるはず。"もしかしたら、こういう気持ちで創造したのかな""こういうことを批判しているんじゃないか"と、何でもいいから感じ取ってみること。その気持ちって、実は自分を映す鏡になるんですよね。作品に触れることで、自分自身から出てくる感想や感情に出会い、今何に関心があるかがわかったり、興味のあることに気づいたりすることで、自分のもとにアートをたぐり寄せられるんじゃないかなと思います」
【アートの見方#6】
自分にアートをいかにたぐり寄せるか。作品と自分の接点を探す。
長嶋りかこさん流、美術館の巡り方。共通点はありましたか? まだエルリッヒの不思議な世界を体験していない方は、この記事を片手に、森美術館で開催中の『レアンドロ・エルリッヒ展:見ることのリアル』を訪れてみてはいかがでしょうか。一度訪れた人も「見方」を意識してみたら、新しい発見があるかもしれません。
【information】
レアンドロ・エルリッヒ展:見ることのリアル
会場:森美術館
会期:2017年11月18日(土)~2018年4月1日(日)
休館日:会期中無休
開館時間:10:00~22:00(最終入館21:30)
※火曜日のみ、17:00まで(最終入館16:30)
入場料:一般1,800円 高校生・大学生1,200円、子ども600円、シニア1,500円
公式サイト(URLをクリックすると外部サイトへ移動します):http://www.mori.art.museum/jp/exhibitions/LeandroErlich2017/
RELATED ARTICLE関連記事



























