
PROJECT
六本木未来会議アイデア実現プロジェクト #10
六本木未来会議BOOKキャラバン @TSUTAYA TOKYO ROPPONGI【前編】
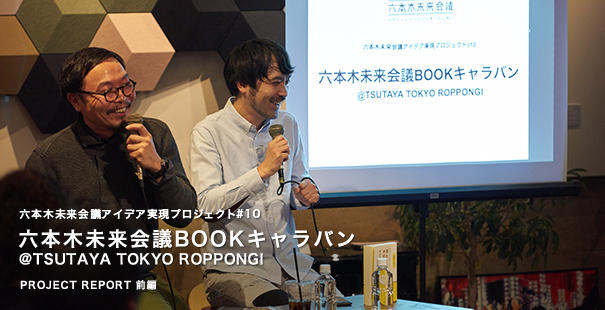
update_2018.01.31
photo_yuta nishida / text_tami okano
本屋は「枯れた」からこそ、可能性がある。
クリエイティブ集団「graf」を率いる服部滋樹さんへのクリエイターインタビューをきっかけに実現した、「六本木未来会議BOOKキャラバン by 服部滋樹」。大好評を博した前回の芝生広場でのキャラバンから一転、今回は、ブック&カフェの先駆けであり、六本木のカルチャースポットのひとつ、「TSUTAYA TOKYO ROPPONGI」が舞台です。「東京ピストル」代表で編集者の草彅洋平さんと共に、参加者のみなさんが持ち寄った本を使ってワークショップをしながら、六本木未来会議の「移動式本棚」に加える1冊を決定! 果たして、どんな話題が飛び出し、どんな本が選ばれたのでしょう。
本屋は「枯れた」からこそ、可能性がある。

「TSUTAYA TOKYO ROPPONGI」にやってきた六本木未来会議の「移動式本棚」。この本棚には、主に、六本木未来会議の人気連載『デザイン&アートの本棚』に登場した本が収められています。服部滋樹さんのアイデアで生まれ、デザインも服部さん。その本棚の横で、ふたりのトークは進みます。
服部 今日はみなさんに、「クリエイションのスイッチを押された本」を持ってきてもらっているのですが、今、僕の横にあるこの移動式本棚には、六本木未来会議の「クリエイターインタビュー」で出てきたクリエイターの人たちが"スイッチを押された"本が並んでいるんですね。私の好きなあのクリエイターの1冊はこれなんだ! ということがわかる、実は、けっこうためになる本棚なんです。まずはそれをみなさんにお伝えしないと!
その『デザイン&アートの本棚』で服部さんが選んでいるのは『共同体の基礎理論』(著 大野久雄/岩波現代文庫)。草彅さんは『ものづくりのイノベーション「枯れた技術の水平思考」とは何か?』(著 横井軍平/スペースシャワーネットワーク)。

草彅 『ものづくりのイノベーション「枯れた技術の水平思考」とは何か?』は、自分が編集した本でもあるんですが、任天堂でゲームボーイやゲームウォッチを開発し、『枯れた技術の水平思考』という考え方を遺した横井軍平さんの遺稿集です。僕は、物をつくるときに、横井軍平的な考え方がすごく大事なんじゃないかってことを、ずっと伝え続けているんです。もう当たり前になって見向きもされなくなったり、流行が終わって廃れたようなもの、そういう一度「枯れた」ものにアイデアを加えるとイノベーションが起こる。本屋だって、そうだと思うんですよね。
服部 え!? 本屋、枯れてる?
草彅 枯れてますよ。実際、本屋の数も減っているし、もう本屋はアマゾンに勝てないからこそ、可能性があるというか、違うやりようがあるはずなんです。
服部 僕が選んだ本、『共同体の基礎理論』を読んではっきりしたことは、今生きている21世紀の初頭という時代は、20世紀に生まれたジャンルやそこから細分化していった古いカテゴリーみたいなものが終わり、それぞれがボーダーを越えてミックスされていく時代だということなんですね。図書館が公民館と一緒になったりとか、公共施設だとなかなかそうは行かなかったものも、ボーダーをこえた新しい形が生まれている。本屋もまさに、ここ「TSUTAYA TOKYO ROPPONGI」みたいにレンタルビデオもあれば、カフェもあれば、オーディオ製品や服だって売っているところは話題になっていますよね。

草彅 複合(ミックス)ですよね。
服部 そういうミックスが、興味のない人に興味を持たせる方法として必要になっているわけですが、単純にアクティビティがくっつけばそれでいいのか、というと、そうではなくて、相乗効果が生み出しやすい親和性みたいなものをどうやって「編集」するかが大事だな、と。
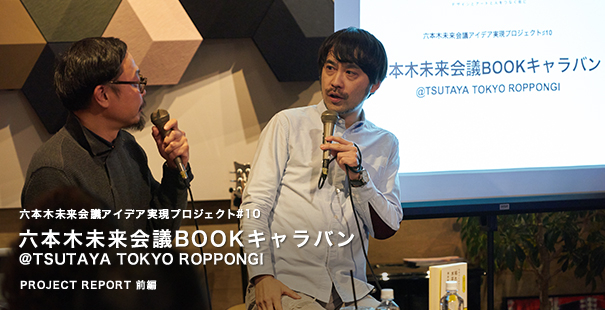
ひとつのテーマに特化した書店の奇跡。
草彅 僕、昔イデーというインテリアの会社にいて、おもしろい会社だったんですけど、当時のイデーがやっていたことって、バブル期のダサイものに手をつけて、おしゃれにすることだったと思うんです。でも今、みんな、最初からおしゃれなことしかやらなくなっちゃったから、ぜんぜんイノベーションが起こらない。カフェとかクラフトビールとか、僕からするとそういうものってもういらなくて、もっとダサくて、もっとイノベーションを起こせるものは何かってことなんです。
服部 本屋の他に、草彅さんが枯れていると思うものって何?
草彅 たとえばサウナですね。サウナとか全然アップデートされてないし、もっとおしゃれにできるだろうと思っているんですよね。そこで昨年、下北沢のイベントスペースで仮設のサウナイベントを実施してもらいました。
服部 サウナかぁ! そういえば最近、洞爺湖とか琵琶湖でサウナキャンプやってたりしますよね。サウナ用のテントをつくって、そこで温まってから湖に飛び込む、みたいな。「枯れている」という言葉をもとに考えると、扱う対象がいっぱい出てきそうな気がします。
草彅 みんな枯れると逃げちゃうんですけど、本屋さんだって僕、まだまだ、ぜんぜんやりようがあると思っているんです。自分で「歌舞伎町ブックセンター」をやってみて、めちゃめちゃ自信がついたんですよね。
服部 え? なにそこ?
草彅 新宿の歌舞伎町でホストクラブを経営している手塚マキさんという方のプロジェクトですね。まだ右も左もわからないような若いホストたちの教育を目的に、「夜鳥の会」というゴミ拾いを始めたりしている方です。
服部 もう、その時点でめちゃめちゃおもしろいやん。
草彅 でしょ? その教育の一貫で、ホストに本を読んでもらいたいと、読書会もはじめるんです。で、どうしたらもっと、本を読むようになるのかと手塚さんに相談されたのがきっかけで、ホストは「愛」を扱う仕事ということで、愛にまつわる本だけを集めた「歌舞伎町ブックセンター」をつくりました。そしたら、今まで考えられなかったくらい、彼らが本を読むようになったんです。

歌舞伎町ブックセンター
避けてきたことにもう一度目を向けてみる。
服部 すばらしい。僕が最近気になっていることにも、だんだん近づいてきているんですけど、それって何かというと、避けてきたものにもう一度目を向けてみるってことで、たとえば、「ファンキー」っていう言葉、最近使います?
草彅 ファンキー? いやぁ、あんまり使わないですね......
服部 ちょっとファンキーって言うの、恥ずかしいじゃないですか。避けめになってる。
草彅 なってます、なってます。
服部 ファンキーって、実はめっちゃリスペクトの言葉だったはずなのに、いつからか、恥ずかしいことになっていて、でも、今日の草彅くんを見ていると、自分ファンキーやな、と言いたくなる。
草彅 ありがとうございます!!
服部 そういう、ちょっと避けてきた言葉や恥ずかしいなと思っていることって、実は"宝もの"で、そこにすごいヒントがあるかもしれないと、思いはじめているんです。
草彅 ありますよ、そこに宝が! それと、「歌舞伎町ブックセンター」みたいなことって、特殊すぎて、大型書店はやらないと思うんです。でも、そういう特殊なことをやらないからダメになる。同じ店をチェーンでつくったら絶対にダメで、あれは歌舞伎町だから成立するけど、六本木では成立しない。
服部 そうだよね。"歌舞伎町らしさ"が出ているからいいんだよね。
草彅 本来、その場から店をつくって、発信しなければいけないのに、今って逆転していますよね。たとえば、ピザ屋やりたいから物件探す、っていう"目的"からの流れじゃないですか。で、たまたま空いていて家賃も手頃な場所があったら、そこではじめる、っていう。その人の勝手な"目的"から物事を進めると街がおかしくなっていっちゃう。
"その場らしさ"から考える。

服部 わかります。それって東京だけの話じゃなくて、地方でも同じような状況が起こっていて、「この事例だと、だいだいこのくらい稼げる」という数字しか見てない。
草彅 それはぜんぜん「編集」じゃないし、何も生まない。僕ね、やっぱり、個人商店が大事だと思うんです。六本木は地価が高いから、利益率の低い本屋を個人でやるのはなかなか難しいと思うんですけどね。
服部 で、ちょうどお題が出てますけど、今日、僕たちが考えなきゃいけないことのひとつが「六本木に本屋をつくるなら」ということなんですが......
草彅 六本木といえば、60年代の「六本木野獣会」しかり、僕にとっては夜のカルチャーのイメージが強くて。たとえば、六本木ヒルズ内にある「リゴレット」が、書店になったらおもしろそうですけどね。服部さん的には、その答えが、この「移動式本棚」だったわけですよね?
服部 そうですね。でも、これについては、まず「六本木未来会議」というものがあり、そこに参加しているイノベーターの人たちが「デザイン&アート」をテーマにセレクトした本があった。ということは、彼らが未来を考えるために、必要だと思った本が並んでいるということで、それを集めた本棚は、六本木から未来を発信する装置になるんじゃないか、と思ったんです。で、これを持っていろんなところに行ったら、みんなで未来を考える場づくりができるんちゃうの? って。僕はこの本棚を通して、いろんなところに、未来への種をまいていくことができたらいいなと思っているんです。

ふたりのトークが「移動式本棚」に戻ったところで、いよいよ、その本棚に追加される一冊を選ぶべく、参加者とのワークショップタイムへ。後半はその様子をお伝えします!
RELATED ARTICLE関連記事




























