


INTERVIEW
82
Asato Izumi / Columnist
泉麻人コラムニスト
Asato Izumi / Columnist
『六本木の全景を捉える、街歩きの未来。』【前編】
過去から学び、路地裏を歩きながら、六本木の新しい地図を作る。
幼い頃から地図が好きで、その地図を片手に街歩きを重ねてきたコラムニストの泉麻人さん。ビルの狭間や路地裏を好んで歩き、いわゆる一般的なガイドブックからは溢れ落ちてしまう風景を独自の視点ですくいあげては、私たちに新しい東京の魅力を見せてくれる、いわば街歩きのスペシャリストです。そんな泉さんに街歩きの視点から垣間見る東京、そして六本木の街の魅力や可能性を伺いました。
山手線内側と外側の違い。
東京生まれ、東京育ちの僕の地元は新宿区の中落合。30歳の頃までこの街で暮らしていたんですが、幼い頃は自宅から都心までの距離がとても遠く感じていました。というのも今から約50年前の東京は、山手線の内側と外側の景色に格段の違いがあったんです。今でこそ高層ビルや路地裏に広がるネオン街は、よくある東京の風景の一部ですが、その当時は山手線の外側にはない風景だったんです。だから両親と銀座に出かけたときにはすごく高揚しました。これが東京なんだ、と。絵本の中でしか見たことのなかった風景が銀座には広がっていたんです。
今は都内であればさほど風景に差を感じなくなりましたけれど、沿線ごとに街の性格は違っていて、それが東京の魅力の一つだと思います。東京はいろんな人に寛容で、多様性に満ちている。だから僕自身は東京の街でここが一番、という場所は特にないんです。どこもそれぞれに味わい深いから。
ただ、どの街に行っても共通していいな、と思うポイントはあります。それは戦前の古い洋館とか、この時代の建物がまだここに残っているんだ、といったものを思いがけず発見した時です。やっぱり僕自身が60代になったこともあって、惹かれるものは渋い造りをした町医者や理髪店とか、郷愁漂う建物が多い。
見つける度に中に入ってじっくり眺めたいと思うのですが、それこそ診察をしてもらう、髪を切ってもらうとかしない限りのぞくことができないので、それがすごくジレンマでもありますね(笑)。
街もまた、人と同じ生き物であるということ。
幼少期に親しんだ建築物にどうしても惹かれてしまうので、ひと昔前に街全体が高度経済成長期を経て、ニュータウンとして変貌していく姿を目の当たりにしたときは、正直苛立ちもありました。でも時が経つに連れて、気持ちもまた変化していくものです。
例えば 東京オリンピックを翌年に控えた1963年に、日本橋の上に首都高速道路の都市環状線が走りました。当時は空に蓋をされたような感じがしてショックでしたけれど、時が経てばそれなりにクラシックな趣が出てきて、親しみが湧いてきます。団地なんかもまさにそう。
近代化の象徴でありトレンドでもあった大型団地は僕自身にとっては正直、日本屋敷に比べると無粋な感じがしていました。でもこうして30、40年経つと、建築物としての味みたいなものが出てくるから不思議です。
要は街もまた人と同じ生き物なんですね。変わりゆく中で、人に与える印象も違ってきますし、その都度、発見や面白さを見い出せる瞬間がある。その瞬間をどれだけ見つけられるのか。見つけるための目を養うためには、やっぱり自分でいろんな道を歩いてみることでしか得られないことがたくさんあります。

路地裏から見る街のランドマーク。
今の六本木にも、僕は好きな風景があります。六本木ヒルズに程近い東京の山の手の丘陵地に「がま池」という小さな池があるんですが、このがま池は、江戸時代に主人を火事から守ったという「がま池伝説」が今に言い伝えられいる、このあたりではちょっと有名な池で、あのNHKの番組「ブラタモリ」でも紹介されていました。
現在がま池はマンションの敷地内にあるため、住人以外は敷地外からしか見ることができませんが、僕はちょうどこの池の辺りから望む六本木ヒルズが好きなんです。
がま池
4江戸時代、備中国成羽の領土・山崎家の屋敷内にあったがま池は、その当時約500坪の面積を誇っていた。その後、大火で周辺の屋敷が全て焼けても、山崎家の屋敷だけは燃えなかった。それはこの池の大きなガマガエルが水を吹いて火を消したためであるという伝説が残っている。現在、池は少しずつ埋め立てられ、マンションの中庭の一部となっている。
「ブラタモリ」
地形好き、地学好きのタレントタモリが、"ブラブラ"歩きながら知られざる街の歴史や人々の暮らしに迫る、NHK総合テレビの人気紀行番組。2008年から放送がスタートした本番組は現在、第4シリーズ目に突入。東京限定だったロケ地は、第4シリーズから全国に拡大している。
http://www.nhk.or.jp/buratamori/
そもそも六本木と元麻布周辺は山の手台地と低地の境目の地域にあり、坂が多い街です。道源寺坂、なだれ坂、芋洗い坂、狸坂など、一歩裏に入れば歴史のある坂がたくさん点在していて、そういった坂を含めた路地裏から街のランドマークを望むとまた、街の印象は全然変わります。
路地裏の隙間からにょきっと顔を出す東京ミッドタウンや東京タワーを眺めてみる。するとこういう見かたがあったんだ、と自分の世界がちょっと広がるんです。つまり視座、視野、視点をどう持つのかによって世界は変わっていく。そういう街歩きが僕の基本だと思います。
迷子になるのもまた、散歩の醍醐味。
街歩きの基本といえば、やっぱり地図の存在は欠かせません。僕は幼い頃から地図を読むのが大好きな子どもでした。いつも地図を片手に近所の道をうろうろ。この道は一体どこに繋がっているのだろう?ということが気になって仕方がなかったんです。
そこから本格的な街歩きに発展したのは、小学5、6年生の頃。バスが大好きで、降りたこともないバス停を降りては周辺をうろうろし、自宅に帰れば、初めて降りたバスの停留所の名前を地図に書き込んだりして、自分だけの地図を作り上げていました。

自分だけの地図
泉さんが小学生(高学年)の頃に愛用していた日地出版の各区別の地図。「とくに近所の中野区や練馬区の地図には、ぬけおちているバス停の名前を書き入れて満悦していました」とのこと。
あと、その当時中学受験を控えて進学教室に通い始めるんですが、教室が丸ノ内線の沿線にあったんですね。だから沿線上にある駅を降りては歩いていました。よく降りていたのは淡路町駅。そこから歩いて神保町まで行って古本屋巡りをしたりして。過去の歴史を調べることも大好きだったから神保町の古本屋で古い雑誌や新聞の記事を集めたりしながら、東京の歴史や文化をいろんな角度から調べたりしていました。
コラムニストとしての原点は、まさにこの頃にありますね。その後、社会人になって泉麻人というペンネームを使って、コラムニストとして独立したのは1980年のこと。まだ発行されたばかりの雑誌『STUDIO VOICE』の中で「ミーハーチックな夜が好き」というこれまた軽薄なタイトルのもと(笑)、東京のあちこちの街を歩きながらメインストリートにはない路地裏カルチャーのエッセイを書かせてもらったのが、独立後の初仕事だったと思います。
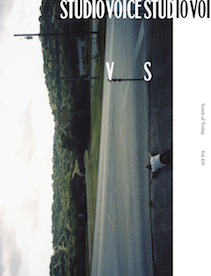
「STUDIO VOICE」
カルチャー雑誌の先駆けとして1976年に創刊し、毎号異なる切り口の特集や斬新な誌面デザインが若者を中心に共感を呼び、日本のカルチャーシーンを牽引。その後発行部数の低迷などを理由に、2009年8月6日発売の同年9月号(通巻405号)をもって休刊。以後はオンライン版のSTUDIO VOICE ONLINEの編集を継続させつつ特別号を単発で発行していたが、2015年4月20日発売の同年5月号にて、6年ぶりにリニューアル復刊し、現在年2回のペースで発行中。
http://www.studiovoice.jp
赤坂へ行くつもりが気づいたら麻布十番に行ってしまっていた。なんてことがその連載中、頻繁にありましたけれど、でもそういうことこそが街歩きの醍醐味でも思うんですよね。
RELATED ARTICLE関連記事



























