
79 為末大 (元陸上競技選手)
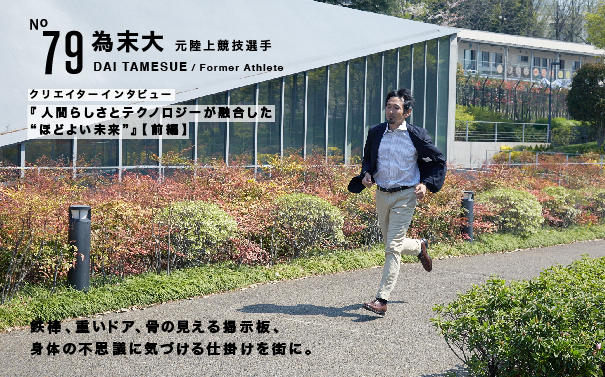
スプリント種目における日本初の世界大会メダリストで、2012年の引退後は、コメンテーターをはじめ幅広いジャンルで活躍する為末大さん。現在、21_21 DESIGN SIGHTで開催中の「アスリート展」では、展覧会ディレクターのひとりを務めています。テーマはずばり「六本木×未来×アスリート」、ふだんのクリエイターインタビューとは少し違った視点から語っていただきました。
日本の街は、多様な人間が動くことを想定していない。
「未来の六本木をアスリートの街にするには」ですか......。そうですね、鉄棒とか置いたらいいんじゃないですか(笑)。そもそも「アスリート」をどんな人と定義するかで、ずいぶん話は変わってくるとは思うんですけど。
日本の街を見ていて思うのは、さまざまな動きをする人たちを想定してつくられていないということ。だから、少し違う動きをする人が出てきたとたんに困ってしまう。ときどき夜、西麻布や六本木を走っていると、あんまり走る人を前提にしていないなと感じます。そういう人はそういう場所に行ってください、みたいな。
海外の街に行くと、歩いている人がいたり、走っている人がいたり、自転車に乗ったおじさんもいるし、当然車椅子の人もいる。多様な人間が動くことを、それなりに余白をもって受け止めている感じがして。

21_21 DESIGN SIGHT
2007年、東京ミッドタウン内「ミッドタウン・ガーデン」にオープンし、これまで34の展覧会を開催。2017年3月31日には、10周年を機に新たな活動拠点「ギャラリー3」(写真)を開設。21_21 DESIGN SIGHTの今後を考えるイベントシリーズ「オープンカンバセーション」も開催中。
Photo: Masaya Yoshimura
アスリート性を高めるのは、ランダム性や余白。
「アフォーダンス(環境が動物に働きかけ、そのフィードバックから動作などが生まれること)」という言葉がありますが、人間には反射があるので、「つい、◯◯しちゃった」というように、外の環境に合わせようとするんですね。
日本の都市ってあんまり考えなくても、家からオフィスまで来られるように上手につくられすぎている気がします。改札を出たら人の流れがあるので、そのままビルに入れて、エレベーターに乗るあたりで、ようやく少し意識する。一方で、アスリートが合宿をするときに、好んで行くところって、自然がある場所が多いんです。言い換えれば、不整地で直線が少ない場所。地面がボコボコだったり、道がクネクネしていたり、そういうランダム性が組み込まれているところを選びます。
全世界の人に共通する記憶なんてあるの、と疑問に思うかもしれませんが、ものの仕組みとか形って、そんなに違わないですよね。たとえばスプーンにしても、それほど変な形のスプーンはないでしょう? 年代によって、もちろん国によっても差はありますが、人々の共通の記憶って必ずあるんです。
アスリートというのは、環境に合わせることと自分で表現することの、ちょうど中間にいる存在なので、完全に設計されすぎていると"遊ぶ余地"がなくなってしまう。きっと、ランダム性や余白が完全になくなってしまうと、アスリート性も失われてしまうんじゃないかな。
日本の競技場は世界で一番使いにくい。
僕が好きな街は、合宿をしたことのあるオランダのデン・ハーグ。そこの競技場は、陸上のトラックを囲むようにして、学校や高齢者向けの施設が建っているんです。午前中は、まずおじいちゃんが出てきてペタンクをして、子どもの体育の授業があって、昼にはお母さんがランチを食べにきて。夜になると、お父さんたちのサッカークラブがはじまったり、ビールを飲んでいる人がいたり。
朝から晩まで練習しながらそんな風景を見ていると、ああスポーツが自然に生活に溶け込んでいるなって感じられて、僕はすごく好きだったんです。
日本って立派な競技場はたくさんありますが、手続きもめちゃくちゃ多いし、僕個人の感覚からすると世界で一番使いにくい。デン・ハーグの場合は、管理人のおじちゃんに会いにいって「今度この日本人が来るから」って言う、ただそれだけ。鍵も空けっぱなしで、いつ使ってもいいよみたいな感じで、使用料を払うときも「何日いたの?」「3週間くらい」って自己申告(笑)。
競技場というより公園の感覚だと思うんですね。日本だと、代々木公園にある「織田フィールド」が少し似ているかな。でも、もし東京ミッドタウンの裏側に陸上のトラックがあって、柵がなかったら、比較的近い風景になる気がします。

アスリート=身体を使って卓越したパフォーマンスをしている人。
今回、「アスリート展」のディレクターをやってみて、あらためて人によってアスリートの定義が違うなと感じました。いわゆる世の中一般で「あの人アスリートだね」って言われるのは、「オリンピックに出ている人」っていうイメージが強いですよね。でも僕は、身体を使って、何らかの卓越したパフォーマンスをしている人をアスリートって呼ぶべきじゃないかと考えています。

アスリート展
躍動するアスリートの身体を映像や写真で紹介するほか、体験型の展示など通して、デザインの視点からアスリートを紐解いた展覧会。2017年6月4日(日)まで、21_21 DESIGN SIGHTで開催中。
だとすると、けん玉のチャンピオンだってアスリートだろうし、もしかしたら料理人だって、頭を使うゲームのプレイヤーだってそうかもしれない。実際、ヨーロッパではチェスはスポーツとして認識されているし、囲碁はかつてアジア大会で公開競技に入ったこともあるんですよ。
スポーツ哲学でよく議論されるひとつに、ドーピング問題があります。これって健康の問題を抜きにすると、あとは公平性の話になるんですよね。でも、もし全員がドーピングしてよくて健康にもいいってなったら、どうでしょう? それでも抵抗がある"何か"ってなんだろう。健康な人が義足を付けて、めちゃくちゃ速く走って何が悪いんだろう......。
「アスリート性」は、工夫のプロセスの中にある。
つまり、自分の意志と力で習得していくことが重要で、簡単にワープしちゃまずいよね、と。そう考えると、アスリート性っていうのは自分の身体を高めていくプロセスの中にこそあるんじゃないかって。
たとえば、僕は身長170cmで体重が66〜67kgくらい、小さめの体型で筋力的には瞬発力の方向に寄っている。また、ハードルという競技は、400mを四十何秒間で走って、かつ10台のハードルを越えていく、若干の持久性とテクニックが必要とされます。この2つの間に努力できる領域がある。
バスケットボールの世界なんかは、20歳から40歳までの、身長が213cm以上のアメリカ人男性のうち17%がNBA選手というデータもあるので、どうにもならない部分も大きいんですが......。
身体のサイズも競技のルールも変えられないけれど、自分の身体をどう活かせば条件に当てはまりやすくなるのか、その余白は残されている。その工夫のプロセスの中から生まれてきた卓越した身体性みたいなものが「アスリート性」なのかなと。

剣道などを例に、相手をどのように見ているかを視覚化した「アスリートの眼」。

力やタイミング、空間と距離を、アスリートがどのようにコントロールしているかを体験できる「身体 コントロール」。
photo:木奥恵三
意識するのは難しい「身体知」を感じてほしい。
アスリート展では、すべての人の中のアスリート性にフォーカスしています。そもそも人間は、考えごとをしながら、アシモですらできない階段をひょいひょい上がることができますよね。紙のコップを持つ動作ひとつにしても、いまだにロボットは困っちゃうのに、人間はさわった瞬間に硬さを認知して、つぶさないように持ち上げることができる。
「アマゾン・ピッキング・チャレンジ」という、ピッキングロボットの大会では、掃除機のようにモノを吸って移動させるタイプのロボットが主流になっています。なぜならモノをつかむのが難しすぎるから。こういう僕らが無意識でやっていることの延長線上に、反応できないような速さのシャトルを打ち返すバドミントン選手みたいな存在がいると思っていて。
コップを持つこととバドミントン選手の差は大きいけれど、ロボットと人間の差よりはよっぽど小さいよねっていうのが、僕の考える「すべての人の中のアスリート性」なんです。日頃意識するのは難しい「身体知」みたいなものを、じわっとでも感じてもらえないかっていうのが、この展覧会のテーマでした。
RELATED ARTICLE関連記事



























