


『みんなが欲しがる未来の“国家”のつくり方』
必要最低限がデザインされていて、対価のないアートが生まれる街。
15歳でアメリカへと渡り、写真家として数々のアーティストジャケットやPV、CMを手がけ、映画「CASSHERN」「GOEMON」の監督としても知られる、紀里谷和明さん。2015年11月には、ハリウッドでの最新作「ラスト・ナイツ」が公開されました。そんな紀里谷さんに、未来会議の編集部がぶつけた最初の質問は「六本木を映画の街にするには?」。その答えとは。
この街は、リアリティのないデザイン実験場に見える。
無理でしょう! まず行政がそれを許さないし、撮影の許可も取れませんから。六本木だけじゃなくて、東京はもちろん日本国自体で無理。とにかく規制が多すぎちゃって、映画が撮れないんですよ。最近では、フィルムコミッションがある自治体もありますが、それでも外国と比べたら非常に厳しい。
そもそも、六本木で映画を撮りたいとも思いませんね。だって、今の六本木ってリアリティがないじゃないですか? 僕がアメリカにいた十代の頃、ときどき日本に来たときに遊んでいた六本木だったら面白いなと思いますけど。今は開発もされちゃったし、なにより住んでいる人たちにリアリティがないから。
社会の裏と表みたいなものがあってこそ、都市だと思うんですよね。それが結局、すべて消毒されて、除菌されていっている。建物のデザインとか、そういうものは面白いかもしれないけど、人間味を感じない、ただのデザイン実験場みたいに見えてしまって。
六本木未来会議とは、誰にとっての未来か。
もちろん、ふだん六本木に来ることはありますよ。東京ミッドタウンの「Union Square Tokyo」というレストランとか、他にもラウンジとかキャバクラとか(笑)。立地的にも便利だし、東京ミッドタウンとか六本木ヒルズに住んでいる、お金がある人たちにとってはいいところなんでしょう。でも、自分ではめったに行かないし、たまたま連れてこられるのがほとんど。

Union Square Tokyo
(ユニオン スクエア トウキョウ)
ニューヨークの人気レストラン「Union Square Cafe」海外初の姉妹店として、2007年に東京ミッドタウン(ガレリア内ガーデンテラス B1F)にオープン。モダンでアットホームな店内では、東京で手に入る旬の食材を活かしたニューアメリカン料理が楽しめる。
なんていったらいいのかな、非常にこう薄っぺらいというか、デザインとかアートとかファッションとか、この街にあるものすべてがコンプレックスを解消することを目指しているように思えちゃうんです。だって、こんなところに住めるのって、それこそ日本人の0.1%以下の、ごく一部の人たちだけじゃないですか。
ちなみに、六本木未来会議っていいますけど、これって誰にとっての未来なんですかね? 「デザイン」とか「アート」とか「人をつなぐ街」なんて書いてあるけど、誰のためなのかさっぱりわからなくて。六本木に住んでいる人? 港区人? 日本人? それとも地球人? 0.1%の人たちが楽しむためなのであれば、いろんなアイデアが出せるでしょう。しかしそれは、地球の裏側の人たちにとっては、まったく意味のないことですよね。
質素にならざるをえない時代がやってくる。
もし仮に、地球人みんなのためだとしたら、こういうことに使っているお金を、今すぐ全部ばらまいたほうがいい。単純な話、日本をはじめ先進国の人が搾取をするから、貧困や内戦が起こるわけでしょう。フランスから空輸されたワインを飲みたいとか、ありとあらゆるものが欲しいというから石油が使われる。そして石油が使われるがゆえに、それを取り合う戦争が終わらない。シリアの難民の人たちからしたら、「デザインとかアートとか言う前に、私に何かくださいよ」って話になっちゃう。
僕は、まずは搾取をやめるべきだと思う。たとえば、この時期いろんなところでやっているイルミネーションなんて、真っ先にやめるべき。震災のときには、あんなに節電節電って言ってたのに、イルミネーションは続けるじゃないですか。外国から空輸されてくるぜいたく品だっていらないと思うし、全部地産地消で、できる限り自給自足。でも、それはやりたくないわけですよ、みなさん。
もっと質素になっていくべきだし、ならざるをえない。だってこんなの破綻しますから、もうすぐ。

日本人らしさ、六本木らしさ、「らしさ」は偏見を生む。
ただただ、六本木が他の都市の人たちからうらやましいって思われたい、ロンドンとかニューヨークに負けない都市にするんだ、そういう話でしょう? よく「世界の中で埋もれないためには、その街らしさが必要だ」なんて言いますけど、そんな価値観なくなっちゃえばいいと思うんです。なぜって、「らしさ」は偏見を生むから。
じゃあ聞きますけど、日本人のアイデンティティってなんでしょう? 本音と建前? おもてなし? そんなこと言ったら、日本人でも本音だけで生きている人はいっぱい知ってるし、おもてなしにしても、アメリカなんか今すごくサービスがいい。逆に日本人でも、おもてなしのない人はいっぱいいるでしょう(笑)。「ラスト・ナイツ」を観て、武士道の映画と言う人がいましたが、自分の命を捨てて何かを守ろうとする心は、騎士道だっておおよそ同じ。世界中どこの国にもあるものです。

ラスト・ナイツ
クライブ・オーウェンとモーガン・フリーマンが主演を務めた、紀里谷氏のハリウッド初進出作品。主君の首をはねることを強いられたライデン隊長と仲間たちが、その敵を討つべく立ち上がる。モチーフは「忠臣蔵」、封建的な帝国を舞台に活躍する騎士たちを描いた物語。
「日本人らしさ」っていうのは、とかく日本人が言ってるだけの話で、別にそれほど変わらない。同じように、ニューヨークの人たちはこうですよね、六本木の人たちってこうですよねって、型にはめたいだけ。そういう発想自体、きわめてつまらない。だいたい未来には、都市なんてなくなると思うんです。これだけ通信環境が発達していて、アマゾンが何でも届けてくれて、今でさえ都市で暮らしている意味がわからないですから。
東京ミッドタウンも六本木ヒルズも壊しちゃえばいい。
六本木では、ここ十数年の間に、雑多なものを排除したほうがいい街になるという方針のもと、いろいろなものがバーッと消されましたよね。でも、いまだに「昔はよかった」って言っている人がたくさんいる。六本木未来会議と一緒で、明らかに混乱しているんですよ(笑)。
開発なんかしないで、ほっとけばよかったし、できることなら東京ミッドタウンとか六本木ヒルズなんて、壊しちゃえばいい。だって、街をコントロールしようとするじゃないですか。そこに大きな問題がある。いくらアートを置いたり、美術館をつくったりしても、そんな場所に本当の意味での文化なんか生まれるわけがないと思うんです。
すべてはコンプレックスであり、憧れなんですよね。こういうものがあれば自分たちもクリエイティブになれるかもしれない、こういうものがあれば日本人もアーティスティックになれるかもしれない、そうやってつくり続けてきて、結局は真逆の方向に進んでいる。そこに何のクリエイティビティがあるのかって、ゼロですよね、僕に言わせると。
ルールやシステムがあるところにクリエイティブは生まれない。
本当にクリエイティブな街をつくりたいなら、商業施設なんか壊してくれって話だし、信号なんかなしにしてくれって感じ。ルールとかシステムがあるところにクリエイティブは生まれない、だからカオスにするべき。そして、クリエイティブになりたければ、単純に自分の衝動に忠実に生きていけばいい。しかし、それを国家が許さないし、システムが許さないし、共同体が、ご近所が許さない。
たとえば、僕がそこらへんでパンツ一丁になってうちわで扇いでたら、「すみません。景観を損なうので、どっかに消えてください」って言われちゃうでしょう。洗濯物ひとつ自由に干せないのにクリエイティブな街にしたいなんて、そもそも矛盾しているんです。
お金を持っている人たちがクリエイティブに憧れていろいろやった結果、アーティストはお金が集まるようなアートをつくりはじめます。映画だってそうで、本当にいいと思っている作品がつくりづらい時代になってきた。ちなみに、人はお金持ちになると、まずいい車を買います、いい家を買います、愛人を囲います、ヨットを買います、別荘を買います、そのあとにアートを買い漁ります。そして、映画に出資するんです(笑)。
昔の六本木はノールールで、超楽しかった。
そういう意味では、昔の六本木にはノールール感が多分にあって、何やったっていいよみたいな雰囲気が漂っていて、超楽しかったし、超クリエイティブな街でした。歌舞伎町なんかもそうだし、それこそ戦後の日本自体がノールール。だから面白かったわけじゃないですか。
それをルール化して、規制化して、システム化していったことで、人々の魂は死んでしまい、人間性が奪われ、人間が人間でなくなったわけです。そういう人たちの集まりが、日本であり六本木じゃないですか。だからリアリティがない、別に人間じゃなくてロボットだっていいもん。
ちなみに、これ(六本木未来会議)だってシステムです。クリエイティブな世の中をつくりたいというのであれば、必要なのはカオス、アナーキーですよ。お金を持っている人は、お金だけ出して「あとは自由にやってください」って。いや「自由にやってください」ということすらもルールだから、お金だけください(笑)。でもさすがに、そこまで器の大きな人間なんて、なかなかいないわけで。

作品で世界は変えられない、でも何かのきっかけになればいい。
究極的な話をすれば、僕は、地球自体が滅びてしまえばいいと思う......あーあ、ついに言っちゃった。だって、どれだけの人がこのシステムのおかげで、苦しみを受けていることか。そんなくだらない世の中で、デザインがどうの、アートがどうのって言ったところでどうなるの? 映画を撮っていても、オレ何をやってるんだろうって思いますもん。
僕が言いたいのは、「地球上で、なんでこんな不必要な争いをしているのか、なんでこんな不必要な苦しみを生み出しているのか」ということ、以上。自分の作品では、「私はそう思います」って言っているだけ。ジョン・レノンの「イマジン」ですら、世界は変えられないんですよ。でも、ちょっとずつ、何かしらのきっかけになればそれでいいし、できているかどうかは置いておいて、自分もその一端を担っているつもり。でも、やればやるほど、無力さを思い知りますよね。
混乱が楽しくてしょうがない、それが地球人。
都市も、国家も、経済も、世界すらも混乱しているなかで、みんなはどんどん自分の人間性を放棄して、システムの中に入っていく。学校というシステム、就職というシステム......喜んで工場の機械の部品になろうとしています。その工場が何をつくっているのか知ろうともしないし、たとえ地球にとって最悪なものを生み出していたとしても関係ない。この混乱が楽しくてしょうがないわけです、地球人は。
人類は常に狂っている、それは今にはじまったことではありません。中世に、髪の毛の赤い人を魔女だといって捕えて火あぶりにするシステムがあって、数百万人が殺されたことを知ってますか? ひどい話だと思うかもしれませんが、これと似たようなことはずっと、いまだに続いています。
そういう混乱した人たちや社会とは、僕は関係を持ちたくない。言ってみれば、火あぶりにもしないし、火あぶりにもされない、というスタンス。まず、自分の混乱を解かない限り平穏なんて訪れないだろうし、逆にいえば、自分に平穏が訪れれば、世界がどんなに混乱していたって大丈夫。そもそも混乱を解こうっていうこと自体、自分のエゴだから。
すべては"最低限"を考えるところからはじまる。
戦争をやめたい、飢餓をなくしたい......。それはとても簡単な話で、搾取をやめて、搾取をしなくていいシステムをつくればいいんです。具体的には、消費を減らして、必要ないものを必要だと思わないこと。だいたい生きていくだけなら、それこそ少々の米と屋根と、凍え死なないだけの一枚の布があればいいでしょう。狂気を引き起こしているのは、そこから先の話。私のほうが上だとか、私のほうがすぐれている、私のほうが目立ちたいという相対の概念、虚栄心やエゴがすべてを狂わせているわけです。
その次元で考えると、デザインとかアートなんて、きわめてちっぽけなもの。クリシュナムルティが、美術館があるのは都市だけ、なぜならそれは自然がないから、というようなことを言っていました。つまり、美しくないところにいるから、美しいものを求めて、人工的にアートをつくり出している、と。
ただ、人間にとって必要最低限のものを、どのように供給していくかを考えるにあたっては、僕はデザインの力が必要だと思っています。デザインっていうのは、科学とアートの融合。たとえば、どれだけ低資源でどれだけ安価に家を建てられるか、そして、どうやって量産するか。エネルギーにしても、もっとも効率よく発電できるソーラーパネルとはどんなものか。食べ物だって、最低限の栄養をまかなえて、それでも喜びを感じられる食糧とはなんなのか......。そこから、すべてははじまると思います。
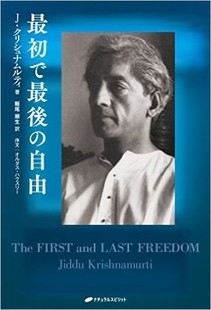
ジッドゥ・クリシュナムルティ
インド生まれの宗教家・思想家。34歳で自らの教団を解散後、1986年に亡くなるまで、世界中をめぐり、数多くの対話や講演、著述活動を行う。現代的なアプローチで、宗教界のみならず幅広い支持者を獲得した。写真は、代表作のひとつ『最初で最後の自由』。
テクノロジーやデザインやアートは、世の中の混乱を解決できるのか。
もしかすると、これからのテクノロジーとかデザインやアートが、世の中の混乱や狂気すらも解決してくれるのかもしれません。そうあってほしいと願ってはいるけれど、今のような既得権益にがんじがらめに縛られた社会の中では、まあなかなか難しいですよね。
それなら僕は、まったく違う"国家"をつくったほうが早いって思っちゃう。資本主義から決別して、外の価値観とかシステムをいっさい取り入れない。自分たちで自分たちの食べるものをつくって、水も住むところも着るものもあって、ちゃんとした教育が受けられて、病んでいる人がいたら誰かが助けてあげられる。みんなで劇をやって面白かったねとか、絵を描いてこれ楽しいね、といった対価のないアートが自然的に発生する......。
最後に言うけれど、そういう街があったら最高だし、僕はそこに住みたいと思う。みんなが本当に欲しがっている未来って、そんなことじゃないかな。
取材を終えて......
インタビューの最後に「どうせすごく短くまとまっちゃうんでしょう?(笑)」と紀里谷さん。紙幅の関係上、たしかに少し短くはなってしまいましたが、お話の流れはほぼそのまま、こちらも(なるべく)ノールールでお伝えしたつもりです。(edit_kentaro inoue)
RELATED ARTICLE関連記事



























