
59 中村拓志 (建築家)
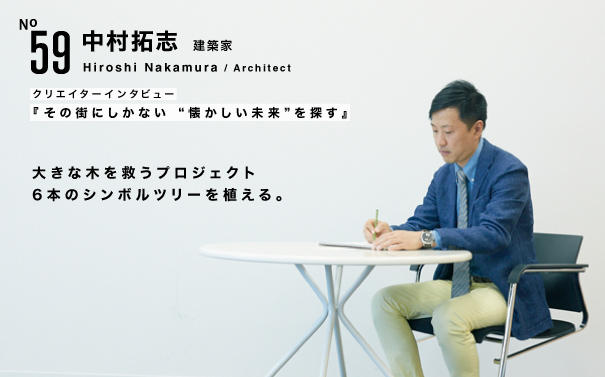
「東急プラザ表参道原宿」や「Ribbon Chapel」などの作品で知られ、数々の受賞歴を持つ建築家の中村拓志さん。10月16日(金)から開催される「Tokyo Midtown DESIGN TOUCH 2015」のプログラム、「Salone in Roppongi by OFFICINE PANERAI」では、イタリアの高級時計ブランド、パネライの世界観を表現したインスタレーションも手がけています。インタビューのはじまりは、そのお話から。
建築とは、自己実現ではなくソリューション。
建築物や空間をつくるときに僕が一番大事にしているのは、やっぱり周辺環境。クライアントニーズはもちろん、商業空間であれば、そこに置かれる商品だったり提供されるサービスだったり。建築とはそういうものに対するソリューションであるべきだと考えているので、作家の自己実現として何かをつくるというスタンスはとっていないんです。
たとえば、今回のインスタレーションなら、光や音が遮蔽できない吹き抜けの空間に、どうやって海の中の世界を再現するか。パネライというブランドの歴史は、イタリア海軍のために深海でも機能する時計をつくる、というところからスタートしています。そこで、潜水時の景色や音を追体験することで、その歴史や魅力を感じてもらえないだろうか、と考えました。
会場には、海中で作業をするときに使われる「潜水球」を模した球体の装置が5つ置かれ、ボールの内側に投影された光が海の中の光景を、そして振動スピーカーが潜水音を再現しています。潜水球が着水すると、最初は淡いマリンブルーの世界、そこからだんだん色が変わっていって、最後は真っ暗な深海の世界へ。
ちょうど、自分の網膜に青いペンキを塗りたくって、それを見ているような感覚。ただ光だけが変わっていって、奥行きがなくなって見えたり、逆にものすごく深い奥行きにも見えたり。まるで、映画「グラン・ブルー」の世界のような、心細くもあり、でもどこか懐かしい気持ちにもなれる。東京のどまん中で深い海に潜る、そういう体験ができるインスタレーションです。

Salone in Roppongi
毎年4月にイタリア・ミラノで開催される世界最大規模の国際家具見本市「ミラノサローネ」。そこで活躍する日本人デザイナーや企業に焦点を当てるDESIGN TOUCHのプログラム。写真は、今回のインスタレーションの完成予想図(上)と、中村氏によるスケッチ(下)。
OFFICINE PANERAI
イタリア・フィレンツェの時計工房として1860年に創業。イタリアンデザイン、スイスの時計製造技術、海への情熱を融合した伝統的な時計づくりを続けている。中村氏が着けているのは、人気モデルの「RADIOMIR 1940 3DAYS AUTOMATIC TITANIO-45mm」(3ページ目メイン写真参照)。
ブランドヒストリー×無限空間への憧れ。
パネライの時計は、文字盤と夜光塗料の塗られたプレートが二枚重ねになっていて、切り抜かれた数字が輝く機構になっています。水深が深くなると徐々にまわりは暗くなっていくので、ダイバーにとっては、相対的にこの文字盤がどんどん輝いて見えると思うんです。もちろん時計ですから、陸の上で刻んでいたリズムを同じように刻み続ける。外の世界の名残を伝える安心感や信頼感は、海に潜ったときでないと感じられない強い体験でしょう。
建築家はふだん、壁があって天井がある"有限空間"を設計しています。そうすると、無限の空間に対する憧れが日に日に増してくるんですね。このインスタレーションは、パネライのブランドヒストリーと、無限空間への憧れという自分の興味、その接点を探しながらつくっていきました。
環境保護と資本主義、相反するものをどう調整していくか。
僕はこれまで、木と建築の関係を大事にして設計を続けてきました。今までの建築のつくり方って、斜面を全部フラットにして、大きな石や木を取り除いて更地にしてから建てる。いわば、その場所の歴史や時間を全部ゼロにして新たに建てるっていうケースが多かったんですね。
でも僕の場合は、自然の中にある木をとにかくよく観察して、三次元測量もして、たとえば台風のときにはどういうふうに揺れ動くかまでシミュレーションしたうえで、木に寄り添うように建物を建てていく。木を残しながらも最大容積を目指す、環境保護と資本主義という相反するものをどう調整していくかに挑戦しています。

地名のごとく、6本の木を六本木に。
今回、「建築や空間をテーマに、六本木の街を変えるアイデアを」という質問を受けて思いついたのは、まさにその地名のごとく、この街のどこかに木を6本植えること。六本木の由来は諸説あるようですが、そのひとつに「6本の木が生えていたから」というのがありますし。
六本木の地名の由来
6本の松の木が立っていたという説のほか、江戸時代、青木氏、一柳氏、上杉氏、片桐氏、朽木氏、高木氏という「木」にまつわる名前の大名屋敷が存在したことに由来する説なども。
本当は、とんでもなく大きな木がいいんですけど、移植をするのも罪だから......。国立競技場の跡地を見てもわかるとおり、道路を通すとか、マンションを建てるといった事情で今、大きな木がどんどん切られてしまっています。そうした木の引っ越し先になれるような場所。大きな木を救い出すプロジェクトのシンボルになるような、6本の木を植えるのはどうでしょう。
よくお寺なんかに大きな木が立っているのは、やっぱり木の下には、昔から自然と人が集まってくるからなんですね。僕が設計に関わった、リゾナーレ熱海の原生林の中にある「BIRD'S NEST ATAMI」は、いわゆるツリーハウスのようでありながら、木をまったく傷めない構造になっています。そういう最先端の技術を使って、木に寄り添うように小さなカフェを建てたり、下にデッキがあったり、集まるみんなが自然を感じられるような場所をつくる。その木の下で、未来を語り合えたらいいですね。

BIRD'S NEST ATAMI
高さ22m、樹齢300年以上のクスノキの上につくられたティーハウス。枝の間に鉄棒をトラス状に組み上げることで、木に負担がかからない構造になっている。設計には中村氏のほか、ツリーハウスクリエイターの小林崇も参加。
いくらかっこいいデザインをしても自然のすばらしさにはかなわない。
木にこだわっているのは、子どもの頃からツリーハウスに憧れていて、それで建築家を目指したというのが理由です。もうひとつ、設計を続けていく中で、いくら建築家がかっこつけたデザインをしても自然のすばらしさにはかなわないと気づいたから。木って蒸散効果があって、風がなくても空気を上にあげて循環させてくれるんです。そういう心地いい風や匂い、美しい木漏れ日を内部空間にどう取り入れるかを考える。自然が主役で建築は脇役、それが結局、一番かっこいいんじゃないかという結論に至りました。
都市環境においても今、クリエイティブな人たちが創造性を羽ばたかせられる街づくりが重要になってきていると感じます。利便性や濃密な情報といった都市の持っている機能にプラスして、ビーチや森、豊かな自然とつながっている。これからの時代に一番必要とされているのは、リゾートと都市が同時に成立しているような街。
容積や効率ばかりを追求して、単純労働をするためには機能的なんだけれど、クリエイティブな場所としてはどうなの、という街はたくさんあるでしょう。そういう意味では、六本木ヒルズや東京ミッドタウンのように、豊かな森がそばにあるところで仕事をしたり暮らせるというのは、この街の大きな魅力。どうしても、その2つがどーんと強いイメージがあるので、さらに街場の個人商店が楽しく、かっこよくなってつながっていけたら......。既成の価値観にとらわれず新しいものを生み出していける、未来の街がつくれると思います。
かつて都市は、風土や気候からつくられていた。
パリだったら地下にライムストーンの採石場があって、それを使って街ができたわけだし、モロッコを旅をしていると、その場所の土に合わせて外壁の色がどんどん変わっていく。かつて都市は、風土や気候、その土地でとれるものなどからつくられていました。僕はそういう都市ごとの魅力をフラットに眺めているので、とくに好きな街っていうのはないんです。そもそもベストをつくること自体が間違っているというか。
強いてあげるなら、面白いなと思う街はモロッコのフェズ。細い道がアリの巣のように張り巡らされていて全然抜け出せない、完全なる迷路都市ですね。地図を見ながら歩いても何度も同じところに出てしまうし、お店はどれも似たように見える。もし夜に到着したら最悪です(笑)。街灯も少なくて、人影を感じて振り返っても、みんなベールを被っていて見えるのは目だけ、いろんな人が声をかけてくるんですが誰も信用できなくて。実際、怖い思いもしましたけど、なぜだか魅力があるんですよね。

街の魅力を生み出す鍵は「謎」があること。
その理由はきっと、「謎」がある、ということだと思います。情報がどんどんネットにあげられてフラットになった今、都市には未知の部分がなくなってきているじゃないですか。その場所に行かないとわからないし、自分の身体能力でしか開拓したり認知できない。そういう街って、今だからこそすごく輝き出すんじゃないかな、と。そういえば六本木も、昼と夜の表情がまったく違うし、アンタッチャブルな部分もまだまだ残されている感じがしますよね。
なんでもネットで買える時代に、わざわざそこに足を運ぶ動機をどうつくるかというのは、僕ら建築家が抱えている大きな課題です。だからこそ、そこでしかできない体験や、そこにしかない場所性を求めたり、あるいはコミュニケーションを拡大して空間化することを目指したりしているわけです。もしかすると、謎をつくるというのは、ものすごく濃密な体験につながる、ひとつの鍵になるかもしれません。
過去の時間とつながった、その先に未来はある。
入ってすぐに全部がわかってしまう空間はものすごくつまらないし、人は飽きるということに、ようやく最近気づきました。でも実際、難しいんですよ。コンセプトを決めて、それをピュアに伝えるようにものをつくっていくことは、ある種わかりやすくする作業でもあって、謎をつくる空間づくりとは逆行しているところもあるので。コンセプチュアルでありながら、どこかに完全には理解しきれない何かを用意することに、僕ら建築家は不慣れなんです。
街の魅力を生み出すために「謎」という切り口で建築をつくったことはまだありませんが、ふだんは地道に場所の固有性を大事にしながら設計をしています。表参道だったら表参道の場所性や地域性、あるいはそこにある石だったり木だったり、先ほどの「6本の木」にしてもそうですが、その街のいわれや歴史、らしさ......。そうした固有性を一つひとつ掘り返して、特別なものにしていく作業が必要でしょう。僕は、その先に未来を紡いでいきたい。
近代の社会は、未来を今までどこにもなかった新しいものと考えることで、ずいぶんたくさんの貴重なものを失ったのではないかと思います。結果として人々を破滅させる未来ではなく、持続的な未来を考えるヒントは、人々が太古の昔から続けてきた過去の中にまだまだ眠っているはずです。けっして懐古主義的な話ではなくて、過去の時間とつながった、その先に未来はあるんじゃないか、って。
「新しいけれど懐かしい未来」を求めて。
最近、徳島県の上勝町にある「ライズアンドウィン ブルーイングカンパニー バーベキューアンドジェネラルストア」という建物の設計をしました。上勝町は、ゴミをゼロにすることを目指す「ゼロ・ウェイスト宣言」をしていて、「リサイクル」「リデュース」「リユース」といった、いわゆる3Rを推進している街。ゴミを減らすには結局、上流のモノを売るところから考えないとダメだということで、量り売りやリサイクル商品を扱うお店と、ビール工場をつくったんです。

ライズアンドウィン ブルーイングカンパニー バーベキューアンドジェネラルストア
2015年5月にオープン。マイクロ・ブリュワリーやジェネラルストアのほか、テイスティング・スタンド、バーベキューガーデンなども併設。ゴミ集積所にあった建具や家具を再利用し、地産地消的なアプローチで設計されている。
ビールも大きなボトルを買ってもらって、飲んだらまた持ってきてもらって量り売りをする。もちろん未来を見ながら設計した建物ですが、量り売りなんて、まさに「懐かしい未来」ですよね。そういう新しいライフスタイルをどうやってつくっていくか。それに今、一番興味があるんです。
取材を終えて......
話を聞いていて思い出したのは、小山薫堂さんによる「アートの実がなる6本の木を植える」というアイデア。それと似ている......かと思いきや、中村さんの「6本の木」は、自然を大事にする建築家ならではのもの。ぜひ、小山さんのインタビューと読み比べてみてください。(edit_kentaro inoue)
RELATED ARTICLE関連記事


























