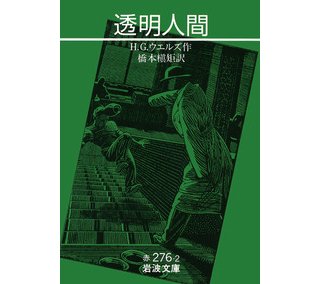INTERVIEW
171
Shunji Iwai / Film Director
岩井俊二映画監督
Shunji Iwai / Film Director
『新しい時代の哲学に響き合う、これからの物語を創造する』【後編】
過去の叡智に眠る、未来のルネッサンスの種。
update_2025.09.03
photo_tada/ text_ikuko hyodo
誰かにとっての廃墟が、ほかの誰かにとっては楽園になる。
とある土地の風景や文化、歴史背景などが物語の構想のきっかけになることは大いにあります。僕が生まれたのは仙台の街のどまん中で、幼少期の記憶は必然的にその景色と結びついています。物心のつく前から映画館によく連れて行ってもらっていて、内容などもあまりわからないまま、スクリーンに映し出される映像を楽しんでいました。あるときは高畑さんと僕をつないでくれた叔父が仙台駅前でデートしているところに遭遇して邪魔したり(笑)。おそらく3、4歳だったと思うのですが、そんな幼い頃に繁華街で遊んでいたということですよね。その後、親の転勤で街から離れ、田んぼしかないような田舎で一日中遊んでばかりの子ども時代も過ごしました。だから都市と田舎という異なる世界が、自分の原風景として共存しているのです。自主映画を作り始めた学生時代は横浜にいたので、そのとき培われた感覚も今の創作のベースになっているのでしょうし、気がつけば東京生活も結構長くなりましたね。
六本木の思い出といえば、シネ・ヴィヴァン六本木というミニシアターには頻繁に行きました。今も西麻布や麻布十番にはちょくちょく出かけます。というのも、映画監督の紀里谷和明さんを発起人に、10人ほどが共同オーナーをしているバーがあって。僕も一口オーナーとして参加しているので、そこに集まって飲んだりする機会が結構あります。
シネ・ヴィヴァン六本木
1983年から1999年にレコードチェーン店「六本木WAVE」の地下で営業していた映画館。ジャン=リュック・ゴダールやエリック・ロメールなどヨーロッパの監督のアートシネマを数多く上映。ミニシアターの草分けといえる場所だった。
街にまつわる妄想は、映画の種を探す上でも欠かせません。六本木ヒルズや、高畑勲展の会場となっている麻布台ヒルズなどのビル群を見ると、人類の進歩はここまで来たのかとしみじみ思いますし、デベロッパーの都市計画思想が現代人のあり方を示しているのではないかと、哲学的なことを考えたりもしてしまいます。発展を遂げた都市が廃墟になったらどうなるのか、一度真剣に妄想したこともあります。そのときインフラはどうなって、どういう人たちが、どんなふうに生き残っているのか。もしかしたら、住む場所を追われて難民となった人たちの楽園になっているかもしれない......、とか。今の六本木を謳歌している人たちにとって居心地が悪くなったら、おそらくほかの人たちが六本木に流れ込んできて、新しい賑わいが誕生すると思うのです。誰かにとって居心地の悪い場所が、別の誰かの楽園になり得る。要は、すべての人にとって優しい街はこの世に存在しないわけで、それ自体が都市の課題ともいえるのではないでしょうか。あらゆる人にとっての楽園を、どうしたら実現できるのか。
小説でも映像でも、フィクションがつくられるときは、のっぴきならない現実が否応なしに内包されていきます。だからこそつくり手は忖度抜きの表現と向き合わなければいけない。僕がシビアな妄想をしてしまうことは避けられないのです。
初めて訪れたのに、懐かしさを覚えた東ベルリン。
自分にとって魅力的に映る街には、ちょうどよいノスタルジーがあるのかもしれません。古風な部分も度が過ぎるとわざとらしく見えるというか、少しでも作為的なものを感じてしまうと本来あったはずの懐かしさから遠ざかってしまう気がして。今まで行ったなかで忘れがたい街は、ベルリンの壁が崩壊した直後の東ベルリンです。一見よくある素朴な風景なのですが、初めて訪れた場所にもかかわらず懐かしさを覚えてしまったのです。どうしてなのか説明のつかない感じも含めて、不思議な体験でした。撮影で訪れたのですが、建物も本当に美しくどこを切り取っても絵になるから、ロケハンがいらない。次のシーンをどこで撮るか前もって決めておかなくても「そこを曲がったらきっと何かしら良いスポットがあるだろう」と。歩みを進めると、予想通り絵になる風景がちゃんとある(笑)。普通だったら、限られた場所をなんとか探しながら撮影をしていくものなのですが、そんな必要がまったくなかったのが新鮮でした。
別の観点になりますが、景観の美しさでいえばヘルシンキも好きな街のひとつです。どこを見てもデザインが巧みで非常に洗練されている。どうしたらこういう街並みができるのだろうと興味が湧きました。

新しい哲学の誕生とともに、新しい物語が必要とされる。
少し先の未来について考えると、これから、今の感覚や価値観では思いつかないような新しい哲学が次々と誕生してくるのではないでしょうか。その変化に付随して、新しいストーリーもおのずと必要とされるのではないかと思っています。だからこそ、これまでの経験に頼りすぎてはいけない。自分が映画づくりに出会った18歳のときのような気持ちで目の前の素材と向き合っていかなければならない、そんな気がしています。
一方で、新しい哲学のことを考えるなら、過去の哲学もないがしろにしてはいけません。たとえば『柳川掘割物語』は柳川の水路システムを淡々と描写していますが、おそらく高畑さん自身もそのすべてを解読できていない。水という存在はとても難解で、2025年になってもすべて研究し尽くされているわけではない。でも、当時の柳川の住民たちは今の僕たちよりも高い知性で環境と向き合っていたとも感じています。むしろ我々は、自然を活かす感覚を自ら手放してしまったのでは。こう考えると人類はだんだん賢くなるという論理は、必ずしも妥当ではないのかもしれませんね。過去に置き去りにしてきたものはほかにもたくさんあるはずで、もしかしたらAIによって明らかにされるかもしれない。今後AIと付き合っていく過程で、失われた叡知に気づかされることがあっても不思議ではないと思っています。
たぶん、未来から見た現代文明は、まだまだ未熟な段階なのかもしれない。「この時代の人間は、まだこんなこともわかっていなかったのか!?」と思うようなことだらけで、未開の民に映るのではないでしょうか。太陽光や波、風などの自然エネルギーも、もっと効率的に活用できるはずです。それに、いまだに人類は地球上から戦争をなくすことさえできていない。多様性が重要だともこれだけ叫ばれていますが、真の意味での多様性は認められているのでしょうか。
"SFの世界"を生きる我々はどこへ向かうのか。
とはいえ長い目で見れば、人類は多様化されていくのだろうと想像しています。SF的なファンタジーですが、進化によって、象のように巨大な人間や鳥みたいに空を飛べる人間が生まれないとも断言できない。けれど、そういう変化は遠い未来に待っているかもしれませんが、今の世の中はあまりにも画一的すぎると危惧もしています。みんなが同じ価値観を持とうとしているというか、多様性とは真逆のほうを向いているのではないかという気もします。
「SFの父」と呼ばれたH・G・ウェルズの小説を今読むと、100年以上前にこんなことまで描いていたのかと驚愕するんです。我々の想像力が及ぶずっと先まで予見しています。現在は、僕が子どもの頃にSFだと思っていた段階に突入していて、当時、夢物語とされていたかなりのことが実現しています。ここにあるスマホも今では当たり前の日用品ですが、数十年前の世界に持っていったら超未来的存在ですよね。我々はこの先どこへ向かっていくのか。そんなことを考えながら、もしかすると昔の人がすでに気づいていたのに現在は忘れ去られた価値もあるのだろうと思い巡らせています。未来の人がそれらを拾い直してルネッサンスを起こすかもしれませんね。
H・G・ウェルズ
ハーバート・ジョージ・ウェルズ(1866年~1946年)。「SFの父」と呼ばれたイギリスの作家。代表作は『透明人間』『タイム・マシン』『宇宙戦争』など。科学知識をもとに、核の脅威や自然破壊など現代にも通じる問題を描いた。
画像:『透明人間』(著:H.G.ウェルズ、訳:橋本槇矩/岩波書店)
撮影場所:『高畑勲展─日本のアニメーションを作った男。』(会場:麻布台ヒルズ ギャラリー 会期:2025年6月27日~9月15日)
取材を終えて......
高畑作品への思いも、物語の種となる妄想も、現代社会に抱く危機感も、同じように穏やかな口調で語る姿が印象的でした。洗練されているのにどこか懐かしくもあり、儚さを感じさせる岩井さんの映像世界や物語には、さまざまな思いや哲学が地層のように重なっていることを知り、映画制作というはてしない旅の一端を見せてもらった気がします。同じ映画でも、観るタイミングによって心を動かされるポイントが違ったり、新たな発見があったりするのは、そういった深みがあるからこそなのでしょう。今の自分は何を感じるのか、あらためて岩井さんの映画を観たくなりました。(text_ikuko hyodo)
RELATED ARTICLE関連記事