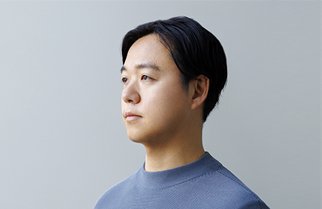INTERVIEW
165
Yusuke Takahashi / Creative Director
高橋悠介クリエイティブディレクター
Yusuke Takahashi / Creative Director
『街に溶け込むアイデアをベースに、コミュニティをデザインしてみる』【後編】
建築的な視点で衣服を捉え、ものづくりに向き合う。
update_2025.03.19
photo_yoshikuni nakagawa / text_akiko miyaura
10年勤務した三宅デザイン事務所では「イッセイ ミヤケ メン」のデザイナーを6年勤め、2020年に自身が手掛ける「CFCL」を立ち上げた高橋悠介さん。伸縮性に富んだニットの特性を活かしエレガントな美しさと快適性を宿したデザインは、瞬く間に世界に広がっていきました。3月には、ブランド5周年を記念した展覧会の開催や『Tokyo Creative Salon』と連携した六本木・渋谷エリアでのインスタレーションも実施され、高橋さんのクリエイティブにもさらに注目が集まります。「CFCL」のスタートから5年を迎える今、ブランドの現在地やグローバルな展開に向けたビジョンや課題、ものづくりをする上で大切にしていることなどを語っていただきました。
ワークショップやインスタレーションのその先。
今年2月にリニューアルされた、金沢21世紀美術館のユニフォームをCFCLが制作した際、ミーティングや撮影などで何度か現地に足を運ぶ機会がありました。今でこそ、街をつくる要素としてアートが力を発揮していますが、美術館が完成した20年前は現代アートがまだまだ人々の暮らしとは遠いものだった。でも今は本当の意味で、美術館が地域の中心となっている。地元のおばあちゃんが生き生きと館内で働いている光景から、本当の意味で地域に根付くということを実感しました。
金沢21世紀美術館のユニフォーム
水平ガラスをイメージした色彩に、金沢21世紀美術館のアイコンカラーのオレンジを配色したユニフォームで、夏用のビッグTシャツとチェスターコート、サコッシュの3アイテムで構成されている。空間に馴染みながらも視認性の高いデザインで、CFCLらしくさまざまな体型、年齢層の人にフィットする美しいユニフォームになっている。
だからこそ街を舞台にするのであれば、純粋に自分のやりたいことだけをやる、という考えは違うなと。まずは、そこに住む人々の生活や文化を知り、街に溶け込むようなアイデアが必要です。同時に、次のコミュニケーションにどうつなげていくのか? そんな想いを抱きながら、東京ミッドタウンで行われる5周年を記念したインスタレーション『POTTERY LUCENT DRESSES』の制作に向き合いました。現代アートのインスタレーションやパブリックアートは集客力や話題性はあるけれど、そこからどのように人々に自分事として受け取ってもらうのか。次に移行するステップの段差の大きさを感じています。
POTTERY LUCENT DRESSES
2020年に誕生したCFCLの5周年を記念する特別アイテム "POTTERY LUCENT DRESS"。ブランドを代表するアイコニックなドレスが9mにもおよぶインスタレーションとなって東京ミッドタウン ガレリア吹き抜けスペースに登場。空気のように軽く、光を透過するニットドレスは、漂うオブジェとして空間に溶け込み、柔らかな春の光を演出する。
ファッションにおいても、次世代を育てる意味で、衣服を通して将来を考えるプロセスが大事。そのためのワークショップやイベントには価値があると考えています。特にファッション業界は、他の産業に比べてサプライチェーンが長く複雑です。例えば、お米が食卓の白米になるプロセスはイメージしやすいですが、ファッションになると、繊維だけでもいくつものプロセスがあり、織りなのか編みなのか、さらに染色や縫製など、一着の服が出来上がるまでにさまざまな過程を経なければならない。だからこそ、製造プロセスの流れを視覚的に伝えられるような場が必要ではないでしょうか。
同時に、ファッションには大きな力があると思っています。カッコいい服とお店と、カッコいいイベントがあれば、興味の入口になります。服を着ない人はいないし、おしゃれを楽しみたいというポジティブな気持ちの人も多い。入口づくりができても、問題はその先。コミュニケーションまでのステップをどれだけ段階的につくっていくか。コミュニティデザインの創造には、プロフェッショナルな設計のスキルや知見が必要だと実感しています。
専門分野以外からのインスピレーション。
何事も遠回りしたからこそ出てくる旨味が大事だと思っています。ワークショップやコンテストの審査員をする際に学生には、ファッション以外の分野をどれだけ学べるかが重要だと伝えています。何からどれくらいインスピレーションを受けて、自分の感性や技術を磨けるか。どれだけ多角的な視点を得ることができるかが、ものづくりの本質に関わっていると考えています。
学ぶという意味で興味があるのは文化人類学や社会人類学。ファッションは西洋で誕生し、無数のデザインが生み出されてきた面もある一方、非西洋の目まぐるしい発展を遂げる国々の文化や、少数民族が昔から着ていた伝統的な衣装がどう作用するのか。そういった社会・文化とファッションのつながりに興味があります。
プライベートでは、娘を通じて広がる世界もあります。特に、文化について考える機会は確実に増えましたし、子どもの視点に気づくことで、立体的にものを見る力が養われているように感じています。
娘に伝えるべき未来、伝えるべき文化とは何かと考えたときに、挨拶やご飯の食べ方ひとつをとっても、彼女を形成する要素になっていく。そう思うと、日々真剣な取捨選択を迫られている気がします。節分やお正月の行事をしっかり行うとなれば、豆まきのあとに掃除をしたり、しめ縄飾りの準備をしたりとなかなか大変です(笑)。それでも、なぜ豆をまくのか、しめ飾りは何でできているのかを知り、体験することには意味がある。
同じ理由で、娘には服やテキスタイルが何からできているのかを学ぶ機会もつくるようにしています。コットンボールの出回る12月にはコットンの紡ぎ方を見せたり、織り機や編み機を買って一緒に毛糸を織ったり編んだり。タイに行ったときには養蚕農家に行って、「蚕からこういう糸ができて、それを染めるんだよ」と過程を一緒に見学しました。

CFCLの5年先のビジョン、日本のファッション産業への想い。
ブランド設立5周年を迎え、次の5年を考えたとき、今後もニットによるものづくりの探求を続けていく姿勢は変わりません。そのなかでひとつ挙げるとしたら、生産拠点の課題があります。ほとんどのブランドは規模が大きくなると生産を海外移転しますが、CFCLは日本のニット業界への貢献を大切にし、日本のファッション産業を盛り上げていきたい。今は自社の「CFCL ニッティングラボ」に編み機が3、4台という規模ですが、今後は国内工場を増やしていくことも視野に入れています。
CFCL ニッティングラボ
2024年に設立した、研究から開発、企画、生産までを一貫して行う自社生産拠点「CFCL ニッティングラボ(CFCL Knitting Lab.)」。次世代の技術者の育成、日本らしい素材や伝統工芸との共創など、実験的な制作や研究を行い、ニット産業のさらなる発展とニットウエアの可能性を模索している。
海外へのさらなる展開を考えると、グローバルな人材も必要です。日本で働きたいけれど日本語が話せない人の受け皿になれたらという意味で、2025年4月から社内公用語を英語に切り替える予定です。また、世界のどこでも働ける環境を整えるために、グローバルリモートワークも推進しようと動いています。
グローバルな舞台で戦うために必要なこと。
文化に根差したローカリティも、世界で戦っていく上では重要です。西洋ではファッションはどのようなオケージョンで着用するかを考えてデザインされ、消費の延長線上で語られることが多い。一方で、日本は日常のなかにデザイン性や美を見出す傾向があります。もし、ハイエンドで特別なオケージョンに対応できる服に、実用性の美との連続性を持たせることが日本独自の美意識とするならば、ヨーロッパの人々は日本のブランドにそうした部分を期待しているのではないでしょうか。そこにあらがう必要も、自ら適合する必要もありませんが、世界からどのように見られ、何を求められているかを察知することは、ブランディングにおいて欠かせない要素です。
また、グローバルに展開していくためには、日本の民芸や工業デザインの歴史を考えることも不可欠です。約1年前に隈研吾さんと対談した際、隈さんが民芸について「好きだけど嫌いだ」というようなことを語っていました。その理由として、民芸の美意識は男性の目線だけで美しいか、美しくないかという物差しで成り立っていて、実際に使用しているはずの女性の目線からは今まで語られてこなかった、と。同じ歴史でも、異なる視点が加わると、見方が変わります。だからこそ、新しいものを生み出すときには、手を動かすだけでなく、想像力を広げる思考の体操を日々大切にしたいですね。
隈研吾
1954年横浜生まれ。工業化社会の建築的理念であるインターナショナリズムに代わる「場所に根ざした建築」の可能性を追求し実践している。
六本木未来会議クリエイターインタビューNO.18で登場。
https://6mirai.tokyo-midtown.com/interview/18/
そして、一番大事なことは継続だと思っています。CFCLに求められているものは明確で、イージーケアだけど品があって、仕事にも休日にも着られるニットのドレスやセットアップ。そのニーズとしっかり向き合いながら、これからもコレクションを展開していきたいと考えています。
撮影場所:東京ミッドタウン ガレリア
取材を終えて......
高橋さんの視点はとにかく多角的で、柔軟。小さな視点から、その向こうにある大きな世界を見るのではなく、最初から広い世界で物事を考え、戦っているからこそ、思いもよらない視点や考えで、身の回りのことを分析できるのだと感じました。日本のファッション産業を盛り上げるトップランナーでありながら、自分の名前を冠していないブランド名にも、髙橋さんのアイデンティティや人間性を感じます。そんな高橋さんが率いるCFCLの生みだすニットウエアが、さらにグローバルに、スタンダードになる日が楽しみです。(text_akiko miyaura)
RELATED ARTICLE関連記事