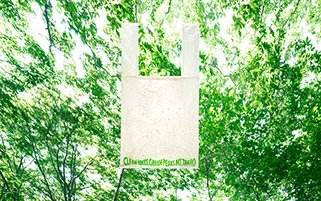INTERVIEW
156
Tomoe Shinohara / Designer / Artist
篠原ともえデザイナー / アーティスト
Tomoe Shinohara / Designer / Artist
『ずっと愛することが持続可能なものにつながっていく』【後編】
挑む気持ちやそのプロセス、作品が完成した喜びが、その人の未来をつくるアクションになっていく。
update_2024.05.08
photo_yoshikuni nakagawa / text_akiko miyaura
向き合う課題があるから乗り越える楽しみがある。
私は2020年に、夫でアートディレクターの池澤樹とクリエイティブスタジオ「STUDEO」(ストゥディオ)を立ち上げました。設立当時、徐々に世の中に浮かび上がってきていたのが「多様性」や「持続可能」といったワード。当初はその課題に向き合えるか不安もありましたが、アイテムを通じ世の中に新しいアイデアの発信や、クライアントの問題解決をすることはデザイナーの責務でもあります。私自身、現代のさまざまな議題を当初からポジティブにとらえ、受け入れながらモノをつくっていきたいと思っていましたし、今となっては多様性も持続可能であることも自分のモノづくりの中に根付いています。例えば「OMO7大阪 by 星野リゾート」のユニフォームはコンペでの参加だったのですが、世代や性別を問わないジェンダーレスで機能的なスタイルを徹底的に追求し、ホテルのコンセプトと掛け合わせご提案したアイテムです。向き合う課題がある時代、新しいことに取り組む過渡期にいられるのは、乗り越える楽しみがある。どんなものを社会に届けていけるのか、自分自身にも期待しながらつくっていきたいです。
STUDEO
篠原さんとアートディレクターの池澤樹さんが、2020年に設立したデザイン会社。「STUDEO」はSTUDIOやSTUDYを語源した言葉であり、「専念する」「勉強する」「努力する」などを意味するラテン語。ブランド戦略のコンセプト構築から広告をはじめとしたコミュニケーションの設計、ビジュアル開発、商品デザイン、ウェブ・空間デザインまでを一気通貫した仕事を強みとし、その他クリエイティブ分野であるファッション・テキスタイルデザイン、アートマネジメント、アート・デザインキュレーションなども手がける。
OMO7大阪(おも) by 星野リゾートのユニフォーム
大阪のホテル「OMO7大阪 by 星野リゾート」のユニフォームを篠原さんがデザイン。ネイビーを基調にドット柄とピンドットを掛け合わせ、ジャケット、シャツ、パンツで構成され、すべて日本生産であることもこだわっている。世代や性別を選ばないのはもちろん、帽子やバッグといった小物でスタッフが個性を表現することもできる。
Photo: Takakazu Aoyama
愛せるモノは、ずっと未来に残っていく。
今思うと私が10代の頃の創作していた衣装は、どちらかというとジェンダーレスなスタイルが好みでした。純粋に自分に似合うと思って着ていたものが、たまたま男性も女性も真似しやすいスタイルだった。アクセサリーなどを自分で制作していたので、ゼロから創作したファッションがメディアを通じて広がりカルチャーへと発展していった。当時は、真似してくださる喜び以上に、つくる喜びを届けられたことが何よりうれしかったのを覚えています。
何かに対して「好き」「楽しい!」と夢中になれる、その気持ちはみんなに届くと信じています。ファッションなら自分で好きなものを着て、絵であれば部屋にお気に入りのものを飾って、プロダクトなら自分が価値を感じるものを手に入れる。そうやって見つけた愛せるものたちは、ずっと未来に残る大切なものになっていく。一見、サステナブルの文脈とは別ものに感じるかもしれませんが、ずっと愛することが持続可能なものにつながっていくのではないかとも思います。
街に根付く美しいものが見えると、つくるべきモノがわかる。
人にモノを届ける立場になって、新たな視点や意識の変化が生まれたのは、夫との出会いがとても大きいです。アートディレクターとしてデザインに対する総合的な知見があり、私にとっての恩師です。設立したデザイン会社では就職するような気持ちで、たくさんのことを見聞きし、一つひとつの学びを大切にしてきました。クライアントワークでは自分だけの感覚や思い付きではなく、デザインを届ける相手のことをまずは調べ、学ぶことがマナーだという彼の姿勢は、今の私のモノづくりに大きな影響を与えています。
昨年、参加した「八王子芸術祭」のアートプロジェクト「CLEAN HIKES, GREEN PEAKS MT. TAKAO」で制作したメッセージバッグも、まず街を調べるプロセスから始まりました。八王子はデザインを学ぶための学生時代を過ごした街ですので、自分ではよく知っているつもりだったんです。でも、実際にリサーチを始めると、知らないことの方が多く、いかに自分の知識が不十分だったかを目の当たりにしました。街のことをよくご存知の方にお電話をしてお話を聞いたり、八王子の歴史の本を読んでみたり、とにかく調べに調べました。
特に助けになったのが、街の方の声が記録された「オーラルヒストリー」。それは新しい施設等をつくるときに、周辺に住む地域の方や関係者から聞いた話や証言を、市が街の声として資料化していたもの。そこには市民の方の街への悩みやリクエストも記されており「八王子は高尾山が有名だけど、アイコン的なアイテムがない」という声が綴られていました。また別の資料では、林業に従事されている方の間伐材に関する深刻な状況や課題も知ったのです。さまざまな問題を自分なりに書き出していくと、つくるべきものが段々と浮かび上がってきました。そうして私が導いたデザインアイテムが、間伐材を資材にし創りあげたメッセージバッグでした。
CLEAN HIKES, GREEN PEAKS MT. TAKAO
2023年の「八王子芸術祭」で、篠原さんが手掛けたアートプロジェクト。地域の方々に守られてきた高尾山の自然の美しさと、それを守る活動や意識に敬意を込め、「クリーンな山歩きが、緑美しい山々を育む」という思いで、持ち運べるアートとしてメッセージバッグをデザイン。高尾の間伐材を活用して、和紙製作の技法を掛け合わせ、一つひとつ手づくりで制作された。期間限定で無料配布を実施した。
Photo : Machiko Horiuchi

ポテンシャルがある街だからこそ、可能性は無限大。
そう考えると、きっと六本木も紐解いていったらまだまだ知らない歴史が出てきそうです。八王子の声を聞き導いた私の作品のように、六本木に住まわれている人や足を運ぶ方々の声、この「六本木未来会議」のアーカイブから何か新しいものが見えてくる可能性もあるかもしれません。ポテンシャルがある街だからこそ、できることはジャンルレスで無限大ですよね。
今、六本木未来会議をはじめ、皆さんが実践されているさまざまなプロジェクトも、いち参加者として期待しています。例えば「六本木アートナイト」は、私も楽しみにしているアートフェスティバルです。特に印象に残っているのは、「Compagnie des Quidams(カンパニー・デ・キダム)」による白いバルーンの作品です。かつて2010年に足を運びましたが、夜の六本木に巨大なバルーンがゆらめき合う圧巻のパフォーマンスは今でも鮮明に目に焼きついています。フランスのラ・マシンというアート集団が、機械仕掛けの巨大な人形を作り、それを使ったパフォーマンスをしているのですが、「六本木アートナイト」ではそれと近しい雰囲気を感じて、とてもワクワクしました。
また、最初にお話ししたように、六本木にはたくさんの自然があります。春の美しい桜やたくさんの緑、冬にはアイススケートもできる。面白いアートや新しいカルチャーだけでなく、豊かな四季も感じられる場所だと、より多くの人に知ってもらうこと、気づきを与えることで、さらに街が魅力的になっていくのではないかなと思います。
Compagnie des Quidams(カンパニー・デ・キダム)
主宰者ジャンバティスタ率いるフランスのスペクタクル・パフォーマンス・グループ。巨大な光るバルーンを多用した造形が特徴的で、その幻想的な美しさと気品のある演技は国際的に高い評価を得ている。「六本木アートナイト」には、これまでに2度登場し、2010年に「ハーバードの夢」、2016年には「FierS a Cheval〜誇り高き馬〜」を披露した。
https://www.roppongiartnight.com/spinoff/contents/295/
©六本木アートナイト実行委員会
ラ・マシンは1999年に設立されたフランソワ・ドラロジエールが監督を務めるストリートシアターカンパニー。機械仕掛けの巨大なオブジェクトなどを制作。さまざまな演劇や世界各地のイベント、都市計画のプロジェクトなどに参加している。
撮影場所:東京ミッドタウン ミッドタウン・タワー1F アート作品《2・1・2・3柵型四群一瞥と擦れ違い》* 前
* 中西 夏之 《2・1・2・3柵型四群一瞥と擦れ違い》1993年〜2006年
取材を終えて......
篠原さんは、聡明であると同時にチャーミングで品がある。デザインや表現はもちろんのこと、そのピュアな人間性と真摯な姿が多くのオファーを引き寄せているのだと感じる取材でした。手のひらで何でも調べられる時代に、自らの身体を動かし調べ上げる篠原さんのリサーチはとても尊い行為。対象へのリスペクトと深い洞察が、純度の高い作品をつくるのだとあらためて感じました。そして、「TOKYO MIDTOWN AWARD 2024」が目指す、新たな才能の発掘への温かな思いに感動しました。(text_akiko miyaura)
RELATED ARTICLE関連記事