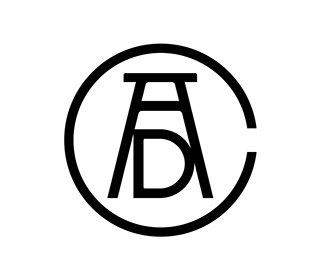INTERVIEW
156
Tomoe Shinohara / Designer / Artist
篠原ともえデザイナー / アーティスト
Tomoe Shinohara / Designer / Artist
『ずっと愛することが持続可能なものにつながっていく』【前編】
挑む気持ちやそのプロセス、作品が完成した喜びが、その人の未来をつくるアクションになっていく。
update_2024.05.08
photo_yoshikuni nakagawa / text_akiko miyaura
六本木は好奇心をちゃんと育ててくれる街。
私が歌手としてデビューしたのは1995年。当時の六本木は「大人の街」「夜の賑わい」といった印象で、10代の私がカジュアルに行く場所というイメージはあまりありませんでした。けれど、私自身がアートやデザインに興味を持ち、つくる側になっていった時期と並行するように、美術館の建設など都市開発が進み、いつしか身近に感じる場所になっていきました。それは、クリエイティブに関心のある大人が集まれる場所を街がつくってくれたという感覚でした。
今は、何か新しいものに出会える六本木の街の力を信じて、導かれるように足を運んでいます。休日に「何かやっているかな」と調べると、面白い美術展が行われていたり、気になる映画が上映されている。また、何かファッションのアイテムがほしいときに六本木ヒルズのショップを覗くと、そこには新しいファッションやカルチャーが生まれているんです。常に新しいものを探し求めている私にとって、六本木は好奇心をちゃんと育ててくれる場所。アイデアのきっかけやインスピレーションをもらえる何かがある街なんです。
日々見つめる自然が作品のインスピレーション。
六本木は都会的な冷たさではなく、自然と融合しているとも感じます。私も参加したことがありますが、六本木ヒルズで開催される「六本木天文クラブ」の「星空観望会」は自然を感じられるイベントです。また、「東京シティビュー」から見える景色は圧巻で、展覧会を見に行ったはずなのに、つい夕暮れの写真を撮ってしまったり(笑)。雲の動きを眺めたり、雨が降った日に虹が出るのを待ったりと、とてもワクワクさせてくれる場所です。
一方、東京ミッドタウンには雄大な芝生があり、子どもたちがはしゃいでいる楽しい声も聞こえて、五感を楽しませてくれます。以前、寒い冬の日に夫と買い物をした帰りにミッドタウンガーデンを歩いていたら、絵に描いたようなかわいらしいミノムシが木にぶら下がっているのを見つけました。ビル群がそびえ立つ都心に小さな命が宿っていることに、とても感動したのを覚えています。
六本木天文クラブ/ 星空観望会
「六本木天文クラブ」とは、六本木ヒルズ展望台 東京シティビューが実施しているさまざまな天文に関するイベントの総称。毎月第4金曜日は「六本木天文クラブの日」として「星空観望会」などを六本木ヒルズ内で実施。「中秋の名月」や「流星群」などに合わせた特別観望会やワークショップなど、年間を通して楽しい星空イベントを開催している。
https://tcv.roppongihills.com/jp/tenmon/
私のインスピレーション源は意図せず自然そのものになることが多いので、街中にいるときも常に自然に反応してしまいます。夕暮れのグラデーションや、ふと緑が風に揺れる瞬間、美しい太陽の光といった風景を日々見つめていると、あるとき作品となって私の中から湧き上がってくる。自然の中に組み込まれた無作為な美しさは、まさにありのままの芸術です。つい自然の中にあるグラデーションを目で追いかけてしまうのも、きっと自然へのあこがれの表れなのでしょうね。

コンペには、プリミティブなつくることへの楽しみがある。
グラデーションといえば、「第101回ニューヨークADC賞」のブランドコミュニケーション部門でシルバーキューブ、ファッションデザイン部門でブロンズキューブをいただいた革の着物の作品《THE LEATHER SCRAP KIMONO》も水墨画のようなモノクロのグラデーションを生かしたものでした。これまで見た美しい幽玄の世界が自分の中に残っていたのでしょうね。本来捨てられてしまうエゾ鹿の革の端切れの曲線美を見たとき、山の稜線と重なったんです。
自然のうつろいや季節を美しく感じるのは、日本人の審美眼だと思いますし、そういったものを感じ取って作品にしたいという思いが私の中に常にあります。自分が美しいと信じたものをつくっていると、心を震わせてくれる人に必ず出会える。「ニューヨークADC賞」での評価は、その信じる力に対する答えをいただけたようで、とてもうれしかったです。同時に、デザインの力が職人さんたちの素晴らしい技術や育まれてきた文化をつなぎ、新たな魅力を引き出す糸口になることに、実感を得られた経験でもありました。
ニューヨークADC賞
1921年に広告美術団体「Art Directors Club(ADC)」によって設立された、世界で最も歴史のある広告デザインの国際賞。2017年からは「The One Club」と「Art Directors Club」の合併によって設立された「The One Club for Creativity」が主催している。毎回、世界中から多くのエントリーがあり、各国の広告、デザイン、アートなどの関係者から注目を集める。
THE LEATHER SCRAP KIMONO
篠原さんが「動物たちの命からいただく貴重な革を、余すところなく使いきる」との思いを込め、エゾ鹿の革の端切れを使って、草加の革職人や染め職人などの技術によって具現化。革の端を山の稜線に見立て、水墨画の風景を表現した着物。篠原さん自ら何度も工場に足を運び、たくさんの時間をかけてつくり上げた。2022年には「第101回ニューヨークADC賞」で、ブランドコミュニケーション部門でシルバーキューブ、ファッションデザイン部門でブロンズキューブの2冠を受賞。
Photo: Sayuki Inoue ©TANNERS' COUNCIL OF JAPAN
思い返すと、私が初めてコンペティションにエントリーしたのは、12、13歳の頃。中学の放送委員会とチームをつくり、企業が主催した学校紹介のビデオコンクールに参加しました。私は脚本や編集を担当したのですが、その作品が優秀賞をいただいたことが思い出として残っています。洋裁の本が主催するコンペに自分で考えた洋服のデザインをイラストにして送ったら、実際に服にしてもらったことも。どれも小さな賞ではあったけれど、人に見てもらえる機会を得た喜びはとても大きいものでした。また、デザイン学科に通っていた高校時代には、先生の勧めで応募したポスターのコンクールで賞をいただいたこともあります。その経験は当時の多感だった創作の感性に大きな勇気をくれました。
応募する側の私の根底にあるのはシンプルに「作品を見てほしい」、「見た方に喜んでほしい」という思いです。プリミティブなつくることへの楽しみが、そこにはあります。ですから、いい意味で考えすぎず、「挑戦してみよう!」とエントリーして「できた! 見て見て」と子どものような気持ちで作品を届けられるのだと思います。
視点や未来を大事にしている「TOKYO MIDTOWN AWARD」。
デザイン会社を立ち上げた今もコンペにトライする立場ではありますが、同時に審査する側を務めさせていただくこともあります。2023年に続き、「TOKYO MIDTOWN AWARD 2024」でも、デザインコンペの審査員をお受けすることになりました。私自身、コンペに挑む皆さんの気持ちはよくわかります。自分の作品は本当に見てもらえているのかな、作品に込めた思いや意味は届いているのかなと感じることもあるかと思いますが、「TOKYO MIDTOWN AWARD」は、審査員全員が本当に真剣に作品を審査していることを知ってもらえたらうれしいです。
TOKYO MIDTOWN AWARD 2024
東京ミッドタウンが「"JAPAN VALUE(新しい日本の価値・感性・才能)"を創造・結集し、世界に発信し続ける街」をコンセプトに、才能あるデザイナーやアーティストとの出会い、応援、コラボレーションを目指して、2008年からデザインとアートの2部門で開催するコンペティション。篠原さんが審査員を務める「TOKYO MIDTOWN AWARD 2024 デザインコンペ」の応募締め切りは6月27日(木)。審査員は篠原さんの他、倉本仁さん、菅野薫さん、中村拓志さん、山田遊さんの4名が務める。
https://www.tokyo-midtown.com/jp/award/
昨年、TOKYO MIDTOWN AWARDの審査に参加して感じたのは、作品やデザイナーの未来を見ている審査員の方が多いことでした。このアワードでは「未熟ではあるけど、育てる価値のある視点を持っている」「作品としてはゴールには届いていないが、未来へ向けての可能性に溢れた作品だ」等、視点や未来を大事にされています。例えば昨年のデザインコンペでは、黒澤杏さんの《動く募金箱》がグランプリを受賞しました。1次審査では、作品案のみを見るため、学生だと知らずに選んだのですが、結果的に最終審査を経て、若い世代が受賞されたことは、審査員としてもとてもうれしかったですね。また、いろんな人が楽しめる《リバースけん玉》や、家族の味を思い出してつなぐ《記すビーカー》といった、自分の体験やルーツを形にした作品、愛をつなげることをデザインした作品など、温かさを感じるものが選ばれた印象があります。
動く募金箱
「つながり」をテーマに開催された「TOKYO MIDTOWN AWARD 2023」で、デザインコンペのグランプリに選ばれたのが、学生の黒澤杏さんが制作した、人と人をつないでいる「バトン」と、人と人をつなぐ活動をしている「募金」をかけ合わせた「動く募金箱」。篠原さんも「アイテムを"バトン"にすることで、手渡しするという思いそのものも感覚的に体感できたプロダクト」と講評した。
リバースけん玉
「TOKYO MIDTOWN AWARD 2023」で、デザインコンペの優秀賞4点のうちの1作品。プロダクトデザイナーの都淳朗さんとUIデザイナーの太田壮さんが制作。従来の「玉と皿」「剣と穴」それぞれの役割を入れ替え、「役割の逆転」によって既存の遊びを誇張しながら新しい楽しみ方とコミュニケーションが生まれる作品。篠原さんは「新しいのに、懐かしいデザイン。検証結果の成果も発揮され、完成度の高さが光る逸品」と講評した。
記すビーカー
学生の大原衣吹さんが「オリジナルの目盛をメモできるビーカー」として制作。「TOKYO MIDTOWN AWARD 2023」では優秀賞を受賞。六角柱型のビーカー側面にはフロスト加工が施されていて、マジックペンで書き込むことができる。篠原さんは「味だけではなく、家族に記してもらった文字そのものも含め宝物になるような作品。文字を記す側にも幸せな時間をくれそうです」と講評した。
審査の流れとしては、1次の書類選考を通過した10組が2次審査に進み、2次では模型を用いたプレゼンを行っていただきます。プレゼン終わりで審査員との質疑応答の時間があるのですが、そこでは質問というより、アドバイスをたくさん投げかけているような状況になることもあるんです。審査員は現役で活躍する、アイデアを育むプロフェッショナルなので、的確にすぐ活用できる言葉を投げかけることも多く、それらのフィードバックは、未来ある応募者の方々にとって、とても価値のある経験になると思います。その一連のプロセスは私自身もとても勉強になっています。
審査員の皆さんが審査を進めるうちに作品への思い入れが強くなっていく様子も、このアワードの素敵な一面です。選考の際、もちろん意見が分かれることもありますが、「これはいい!」と感じた作品を審査員の誰かが一生懸命に推すという光景が生まれる。皆さん、過去の自分を見ているような気持ちになるのか(笑)、応援したいという空気に満ちているんです。
TOKYO MIDTOWN AWARD 2023
2023年度の審査員は篠原さんの他に、菅野薫さん、中村拓志さん、三澤遥さん、山田遊さんといったファッション、デザイン、建築、広告など各分野から集結。総計1,166点の作品を「デザイン力」「提案力」「テーマの理解力」「受け手の意識」「実現化につながる」という5つの審査基準のもとに審査が行われた。審査過程で議論をつくしたものの「僅差で優劣をつけられない」となり、優秀賞を規定の3点から4点へと1点増やす結果に。ジャンルが異なる審査員が集まったことで、菅野さんは「審査のプロセスが非常にクリエイティブなものでした」と振り返っている。
理由を考え探ることが、学びになっていく。
コンペの受賞数は限られているので、惜しくも受賞を逃した方は、審査員に作品が評価されなかったと感じることがあるかもしれません。でも、そこには届かなかった理由が必ずあるはず。選ばれなかったと気持ちを落とすのではなく、届かなかった理由を探ることが学びとなり、楽しさになっていくのではと思います。逆に「なぜ、この作品は受賞したのか」を考えていくと、自分の作品に足りないものを発見する機会になるのではないでしょうか。
審査員を務める立場からお伝えしたいのは、自信のある作品や誰かの瞳に映ることで行動源になると言える作品があるならば、ぜひ堂々とエントリーしていただきたいです。テーマに対して自分がゼロからモノをつくるって、それだけワクワクするじゃないですか。もちろん、受賞という目的に向かって走るけれど、挑む気持ちやそのプロセス、作品が完成した喜びが、その人の未来をつくるアクションになっていく。「私はこう思う!」と独自のアプローチを見つけたときの喜びも大きいと思います。今の私自身もこれまで多くの挑戦や挫折を遂げて今があります。アイテムを通じて問題解決をし、人とは違う表現を考えることが、オリジナリティを育てることにもつながっていく。1人じゃなく、チームで作品を作ってみるのも素晴らしい思い出になると思います。あまり気負いしすぎず、自分を楽しませる気持ちで、ぜひ参加してみてください。六本木という地で発進されるこのアワードから次世代のデザイナーが生み出されること、そして新しい才能が育つことを願いながら、しっかりと見届けさせていただきます。
撮影場所:東京ミッドタウン ミッドタウン・イースト1Fアート作品《passeneger》* 前
* 神谷 徹 《passeneger》2007、パネルに綿布、アクリル絵具、90 x 90 cm (12 点組)東京ミッドタウン コミッションワーク
RELATED ARTICLE関連記事