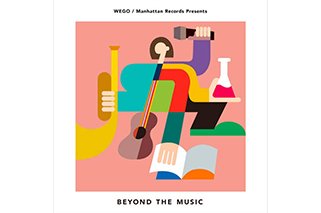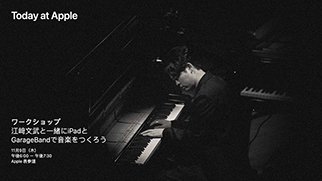INTERVIEW
153
Ayatake Ezaki / Musician
江﨑文武音楽家
Ayatake Ezaki / Musician
ラボのようなライブベニューで、音が生まれる瞬間に立ち会う【後編】
音楽で表現する楽しさを届ける。
update_2023.12.13
photo_tada / text_akiko miyaura
音楽で表現する楽しみを学ばないまま終わる教育。
日本の音楽教育のあり方は、ここ100年ちょっとの間、大きくは変わってないんです。ピアノと歌を軸にして音楽を学びましょう、リコーダーをみんなで練習しましょう、合唱コンクールで頑張って歌いましょう、といった構造はずっと同じ。多くの人が自分ならではの音・音楽で表現する楽しみを知らないまま学校を卒業していく。それは公教育のもっとも大きな問題だと感じています。
唱歌中心の音楽教育が奏功して日本はカラオケが根付いていて、着うたの文化の発達も早かった。そう考えると、「自分はこうです」とアイデンティティを音で示すことが、すごく好きな国民ですよね。風鈴や鹿威し(ししおどし)の文化からも分かるように、音に関する感受性も強いはず。ただ、自分だけの音や音楽を生み出して楽しむことはあまり得意でない。
僕の知人に、イギリスのパブリックスクールで育った人がいるんですが、高校3年生の時に音楽の授業で自分の曲をつくるところまでやったそうで。「当時は何も分からず辛かったけど、大人になってみると歌だけじゃなく、楽器もよく聴く耳になっていた」という話をしていたんです。それを聞いた時、「だから、あの国はRadioheadだとか尖ったバンドが、国民的な人気を博しているんだな」とすごく納得しました。
僕が思う音楽の一番面白い部分は、自分で音を見出したり生み出したり、曲をつくったりすること。でも、日本の音楽の授業だとそんな経験はほぼなくて。美術の授業だと技法だけを知って終わるなんてことはなくて、手を動かして絵を描くじゃないですか。でも、音楽はそうじゃない。それでは表現する術を習得できるはずもなく、大人になってカラオケに行くぐらいのことしかできなくなってしまいます。
テクノロジーで曲を生み出す経験は、ポジティブでしかない。
そんな教育のあり方を変えるために、昨今のテクノロジーの発達はメリットがあるなと感じています。パソコンなりAIなりを使って、曲を生み出す体験を若いうちにしておくのは、すごくポジティブに働くだろうな、と。かつ、ツールが発達するほど表現が多彩になっていく。例えば、手紙で思いを伝える時に、挿絵を入れる人がいるじゃないですか。もし簡単に音楽をつくることができれば、思いを乗せた曲をつくって人に伝えるとか、今すごく怒りが沸き上がっているから怒っている曲をつくった、みたいなこともできる。それくらい身近な表現のひとつとして、音表現がたくさん起こっていくといいなと思います。
僕がクリエイティブスクール「GAKU」で、10代に向けてやっている授業「Beyond the Music」もそのための第一歩。音楽を通してさまざまな分野のことを学びながら、実際に楽曲を制作してもらっています。また、11月にはApple 表参道でワークショップを開いて、参加者たちとiPadで曲をつくりました。僕は研究者でも教育者でもなく、ただただバンドやポップスの領域で活動している人間なので、「こういう世の中になったらいいな」ということを発信することしかできない。でも、活動を続けていると教育や研究の現場、あるいは学校のカリキュラムを考える文部科学省の人たちに、だんだんと届いている実感があります。
Beyond the Music
「GAKU」は10代のための新たなクリエイティブな学び舎として2020年に開講。山縣良和(writtenafterwards)がディレクターを務める。その中のひとつのクラス「Beyond the Music」は、江﨑さんが総合ディレクションを手掛け、実際に教壇にも立っている。2023年8月~翌年2月は第3期として開催中。10代に向けた新たな音楽教育の発信を目指し、生徒たちは実際に楽曲づくりに挑戦している。
江﨑文武と一緒にiPadとGarageBandで音楽をつくろう
2023年11月にApple 表参道で行われたワークショップ。iPadとGarageBandを使って、サンプリングした音からトラックを組み立てていく方法を江﨑さんが手ほどきした。参加者は、GarageBandのLive Loopsで「眠る時の音楽」をテーマに曲づくり。出来あがった曲をそれぞれが披露した際には、江﨑さんが即興でピアノを演奏する場面もあったそう。
先日、小中学校の音楽の先生が集まる学会で、講演をする機会をいただきました。そういう場で「ポップスの現場の音楽家でも全然ピアノが弾けない人、まったく楽譜が読めない人はいっぱいいるけど、表現することを楽しんでいますよ」と伝えることが、やがて教育の形を変えていく一歩になるのかなと思っています。
最終的には、公教育が変わってほしいというのが一番の願い。「型」を教える教育ではなく、歌が好きな人は歌をやればいい、ビートを組みたい人はビートを組み、DJをやりたい人はDJをやっていい、といったように「表現」を軸とした音楽教育が実現できるまで、自分が動けることはいろいろやっていこうと思っています。

何かが生まれる瞬間を創出することが、未来の価値になっていく。
音楽教育の話をしてきましたが、街づくりにおいては音楽が立ち入る隙ってあまりないんですよね。コンサートホールをつくるとか、ライブの便宜を図るくらいのことしかできなくて。六本木を例に挙げると、「Billboard Live TOKYO」はある程度まで磨き上げられたアーティストたちのショーケース。一方で、「21_21 DESIGN SIGHT」は何かのプロセスを見せたり、巨匠と新進気鋭のデザイナーとが同じ展示会に並んでいたりするじゃないですか。音楽の世界でも、もっと何かが生まれる瞬間を見せる場所や、エネルギーはあるけどセールスにはつながっていない若い人たちの受け皿みたいなものがあると、六本木はより面白い街になるんだろうなと思います。
まさに、僕らにとって「SuperDeluxe」はそういう場所でもありました。真っ白な壁がドカンとある無機質な箱で、コンテンポラリーダンサーの公演もあれば、プロジェクションマッピングを始めたばかりというチームの発表会もある。芽を出したばかりの人たちが集まっている、そんな場所でしたね。
SuperDeluxe
実験音楽やフリージャズ、電子音楽を中心に多種多様なアーティストが出演。有名・無名、国内・国外を問わず、先鋭的で実験的なパフォーマンスを展開する唯一無二の拠点として、多くの人から支持を得た。2019年にビルの老朽化により閉店したが、2022年に西麻布から千葉・鴨川に場所を移し、再始動した。
何かが生まれる瞬間に立ち会う機会をどう創出できるかが、すごく重要だと思います。例えば、音を出す環境が整っているオープンな場や、安く使える音楽家のラボみたいなものをつくったり、取り壊しが決まっている雑居ビルを簡易的なライブべニューとして稼働させたりできると、機会ができていくのかな、と。そういった場で、接点がないはずの人たちがこの企画だから一緒にやるみたいな組み合わせの妙が生まれると、さらにいいですよね。きっと大きなお金にはならないけど、将来的にビッグアーティストが生まれた時、「10年前、六本木のあの箱でやらせてもらったのが、今につながっている」となっていく。それ自体が、価値だと思います。
経済合理性だけではない余白を残す。
最近の東京は、経済合理性に偏りすぎているイメージがあります。同じような超高層ビルが建って、同じようなテナントが入って、飲食店も蓋を開けたら同じ傘下のグループだった、ということが起きている。そういった再開発によって失われるものって、資本的な面と整合性が取れないものなんですよね。だから、昔からあった街中華がなくなったり、古いライブハウスがなくなったりといった皺寄せを受けて、代わりに経済的に成功した人が使うべニューができていく。でも実際のところ、経済的に豊かとは言えない人たちこそが、すごく面白いことを考えていたりするじゃないですか。そう思うと、合理性を優先した再開発って、本当に豊かなんだろうかと思う時もあります。
もちろん経済的に成功すること、ビジネスが回ることは大事だから、ちゃんと考えなきゃいけない。それに僕自身、再開発自体は嫌いじゃないんです。この間パリに行った時に、延々と同じ街並みが保たれているのを見て、すごくカッコいいけど、これはこれでつまらないかもなと思っちゃったんですよね。街の新陳代謝みたいなものは東京の魅力のひとつだし、新しい建築が生まれるためには必要なこと。だから、すべてに反対するわけじゃない。ただ、経済合理性だけで回っていない余白を残すことは、忘れずにいてほしいなと思いますね。
撮影場所:MIDTOWN CHRISTMAS 2023《some snow scenes》(2023年11月16日~12月25日)
取材を終えて......
たぐいまれな音楽センスを持ちながら、冷静に今の日本の音楽シーンを俯瞰している江﨑さん。日本の音楽教育は技法だけを知って実践を伴わないこと、多くの日本人が歌と歌詞だけに耳を傾ける偏った聴き方など、"言われてみれば"とハッとすることが多々ありました。でも、何より心打たれたのは、「表現」を軸とした音楽教育の実現に向けて動き続けようとする行動力。遠くはない将来、江﨑さんの活動が、若者たちに音楽表現の楽しさを広げてくれるはずだとワクワクしました。(text_akiko miyaura)
RELATED ARTICLE関連記事