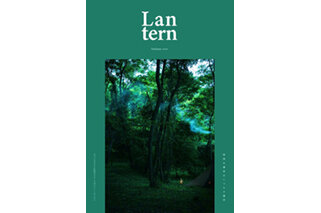INTERVIEW
143
Yusuke Narita / Researcher
成田悠輔研究者
Yusuke Narita / Researcher
『脳内イメージの街を再現し、謎の空間をデザインする』【前編】
何をしているかよく分からない人がやってくる余白を。
update_2023.01.11
photo_tada / text_akiko miyaura
科学や数学は、"クリエイティブだと思われていないクリエイティブ"。
私が普段向き合っている研究では、数式やプログラムなどを使って表現する科学っぽいことをしています。科学や数学、プログラムは"世のなかでは、クリエイティブだとは思われていないクリエイティブ"なのだろうと思います。
例えば、数学者が何をしているのか、人類の99.99%の人は興味がなくて、理解もしていない。その世界にはユーザー、リスナーといわれる人はほぼいなくて、当事者同士で鑑賞し合って、新しい発見に価値があるかを品評し合うということをずっとしている。超々マイノリティの間だけで流通する、特殊なクリエイション活動が数学であったり、科学であったりするんじゃないでしょうか。
1,000年くらい歴史を遡ると、アーティストといわれる存在と、サイエンティストといわれる存在とは、ほとんど渾然一体でしたよね。レオナルド・ダ・ヴィンチのような人は、よく"万能の天才"なんて言われるじゃないですか。でも、彼らが特殊な人だったというよりは、当時はそういう世界だったんだと思うんです。いろいろなものが、もっと原始的で単純だった。「この世界はどうなっているんだろう」と考えながら鳥を仔細に観察して手元でスケッチしたり、それをいじって改変した姿を想像したりすることが科学であり、同時にアートでもあった。
その頃は、アーティストやクリエイターといった職業の区分が曖昧で、創造したものを伝えるメディアやマーケットも未発達。たまたま知り合った人と雑談をしながらお土産と引き換えに似顔絵を描くとか、子どもがお絵かきをするみたいに半分暇つぶしでサッと手を動かすみたいなことが、アートと言われるものの原型だったのだろうな、と。それを現在の世界でも取り戻せるのか、"闘うプロ"より"逃げ続ける素人"みたいな存在をどうつくれるのか。そういう問題に興味があります。
"クリエイトしないクリエイション"は可能だろうか。
そもそも私自身が、ただただ受け身で闘うよりは逃げているんです(笑)。何の創造も発信もしてないですし。人に何か聞かれたら、その場で思いついたグダグダなことを言ってみる。ブツブツ独り言を言ったり、誰かとおしゃべりしたり。特に何の価値もない時間の浪費っていう感じがしますね。きっと、人前に出ている人のなかで、ここまで伝えたいこと、やりたいことがないのもめずらしいんじゃないかな。
最近ミュージシャンの方々と話すことがちょくちょくあるんですが、彼らなんて創造と闘いの極地じゃないですか。作詞・作曲からメイク、スタイル、照明、音響、振付とつくり込んで、数千人、数万人を集めて数時間のお祭に入魂する。天地創造っていう感じじゃないですか。かたやこっちは準備ゼロで寝起きにノーメイク。その場で思ったことを自室からテレビで喋ったりしてますからね。スタッフもチームも無。我ながら生きてて恥ずかしくないのかと思いますよ(笑)。
つくるべきものをつくって伝えるべきものを伝えるクリエイションはかけがえのないものですが、一方で逆のクリエイションもあるのではないかという興味も湧いてきます。本人は積極的に創造しているつもりはないのに、副産物として生まれたものがクリエイションに見えてしまう。存在自体がアート、生きてるだけでクリエイションみたいな存在にどうしたらなれるか。"クリエイトしないクリエイション"は可能かという問題です。
内容ではなく、伝え方の実験としてのポエム。
私はときどきポエムを書くんですが、それは創造的な行為というより、ある種のアジテーションや演説と同じだと捉えています。それとは別に科学や数学を通して表現する行為があるという、ざっくりとふたつの方向性が共存している感覚なんです。
数式やプログラムで表現したものが人にどう伝わっていくかを考えると、その中身よりも、どう表現されるかの方が影響力が大きいなと感じていて。その伝え方の実験が、私がポエムと呼んでいるものの中身かなと、最近思っているところです。要は実体より媒体、WhatよりHow、みたいなことですよね。情報そのものが新しいか独自かということよりも、どういう口調や声色で、どんな表情で伝えるか、どういう表現を使うか、という伝え方に注目しています。
去年の夏、『Lantern』というフリーペーパーにポエムを書いたのですが、それを紙で3,000部だけ、全国各地の場所に配るという謎のプロジェクトがあったんです。結局メルカリで5,000円だか1万円だかで転売されてましたが(笑)。唯一無二とされるアートでもなければ、複製して薄利多売ができる商品でもない。一見すると中途半端な「アートと商品の中間地点」に形を与え、名を与える試みはもっとやられていいんじゃないかと思います。

アートは、唯一無二だという幻想を生かしている。
アートって、一見無駄にも思えるものを、異様に儲かる洗練された金融商品みたいなものに替えることに成功した領域ですよね。六本木のど真んなかの施設や、マンハッタンのど真んなかのギャラリーを、謎の置物とか板が陣取ってるってよく考えると不思議じゃないですか。アートは"唯一無二だという幻想"を活用したことが勝因なんでしょうね。複製可能で薄利多売の商品として成功したマンガなどの出版と、複製不可能で唯一無二のアート、そのふたつの中間にあるハイブランド・ファッション。その3つの構造を分析する経済学はつくれないかなとか酔ってるときに考えることがあります。
MoMA
マンハッタンに位置する近現代美術専門の美術館。1939年に現在の敷地であるミッドタウン(西53丁目11番)に移転。2004年、谷口吉生氏の設計により大規模なリニューアルを果たし、現在に至る。
一方で、書なんかもアートの部類に入るけれど、文字ってアートになりづらい側面があるように感じます。恐らく文字にした瞬間、そこに表わされているものが情報・意味に還元されて、「コピーできる情報に過ぎない文字に、とてつもない値段がつくのはおかしい」という人間の直観が働いてしまうんでしょうね。要は"複製できちゃう世界"になってしまっている。
ごく普通の人を描くのが一番難しい。
私が文学や映画の世界に惹かれるのは、アートとはちょっと違う文脈なんです。そこに登場する人物って、有名でもなければ特別でもない、ごく普通の人。無名の人を描いて鮮烈なものを見つけ出すってすごいことだと思うんです。テレビやYouTubeだと、ちょっと変わった人や出来事をもってこないと、コンテンツとして成立しづらいじゃないですか。文学って、それとは真逆の世界ですよね。
もっと言えば、普通の人にとっては何の得になるのか、何の役に立っているのか分からないもの。だから、年を重ねると小説を読むことが少なくなる。でもその無駄さというか、非効率さ、不合理さって裏を返せば、文学や映画は一番難しいタイプの創作であるという証明でもあって、そこに面白さを見出しているのかもしれません。
創造の価値を生むのは、対となる批評。
アートや文学、ファッション、グルメ......そういう創造が担う役割は、簡単には自動化できないんじゃないかと思います。漠然と人々の頭の片隅にあった問題を正面に持ってくるとか、心の奥底にうごめいていた今までと違う価値観や物の見方を目に見える形にするっていうのが、アーティストの役割だとすると、人間ではないものが果たすには多くの課題があります。
アメリカのアート史を見ると、すごく力を持ったアーティストが生まれた時代って、同時に対となる批評家・評論家が存在していますよね。ファッションであれば、デザイナーやブランドが存在している一方でパリコレが存在し、グルメなら料理人と同時にミシュランが存在する。つまり、創造する側と批評する側が対にならないと、機能しないものだと思うんです。
つくり出されたものがいかなる問題を提起しているのか、どういう意味で価値があるのかという文脈を与えたり、権威を与えたりする広い意味での批評の機能が、必要不可欠。そう考えると、現状すごく注目されている画像生成AIのような存在は、生成側としては機能していても、批評側を担うのは難しい。自動化を実現するためには、創造側と批評側の対話はもちろん、論争、誹謗中傷といったものまで総合的に汲み取って、どうやればプログラムやソフトウェア、アルゴリズムで表現できるのかという課題を乗り越えないといけない。そこに行き着くまでには、まだまだ長い時間が必要だと思います。
画像生成AI
人が描いた絵と同等の品質を保持して、作品を生成するソフトウェア。「Midjourney」等。アイデアなどを文章として入力することでAIアートを作成する方法や、写真をアーティストが描いたような画風に変換する方法などがある。オークションで画像生成AIによる作品が高額で落札されるなど、ここ数年で大きな話題になっている。
撮影場所:アダムアンドイブ
RELATED ARTICLE関連記事