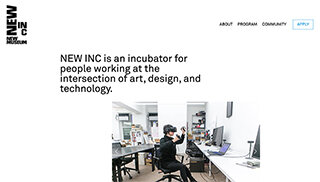INTERVIEW
132
Junya Yamamine / Curator
山峰潤也キュレーター
Junya Yamamine / Curator
再開発で生まれた廃墟をスクワットする【前編】
「良質なカオス」で人と人が出会う。
update_2021.12.15
photo_yoshikuni nakagawa / text_koh degawa
六本木に出現したミックスゾーン。
僕は、いろんなタイプの人が集まったり、出会ったりしてできるエネルギーや創造性を生み出せる場に興味があるんです。企画やディレクションをしている六本木のアートスペース「ANB TOKYO」も、アートの街六本木で、社会におけるミックスゾーンをつくれないか、というコンセプトで生まれました。
ことの始まりは、株式会社アカツキの代表、香田哲朗さんが「アートはいったいどんな求心力を持っているのか」という問いを持っていた時期で、その頃、このビルが定期借家で出てきたんです。そこから六本木にアートビルをつくろうということになり、相談に乗っているうちに本格的に一緒にやっていくことになったんです。
コロナの影響もあり想定外のことに見舞われつつも、オープンして展覧会を開いてみると様々な発見がありました。時勢柄、人と人の交流が少なく行き詰まりがちだった社会の空気を、アートの利害関係を超えた出会いが解いていったんです。展覧会では会社のCEOたちが集まって話したり、アーティスト同士が偶然出会ったり。普段とは異なる関係を構築する場として「ANB Tokyo」が機能するようになりました。
ANB Tokyo
一般財団法人東京アートアクセラレーションが設立したアートコンプレックスビル。意欲的に表現活動と向き合うアーティストのサポート、アートを軸にしたコミュニティの形成、展覧会やトークイベントの企画・運営を行う。株式会社アカツキの代表香田哲朗氏と、山峰潤也氏が代表を務める。
クリエイティブな場をつくるには、ファジーさが不可欠。
「ANB Tokyo」ができる前から、六本木にはすでに老舗のギャラリーが軒を連ねています。国立新美術館や森美術館のようながっちりとした美術館も、タカ・イシイギャラリーや小山登美夫ギャラリーのような力強いギャラリーもある。ただ、その中間にある目的の定まらないファジーな場所が足りていないように感じていました。
以前の六本木周辺には、「SuperDeluxe」や「magical, ARTROOM」のような何だかわからない場所が点在していましたが、こういうある種の"空地"があることで集まってくる人たちがいるし、そこで生まれる熱量やクリエイティビティがある。そういう場をつくりたくて、「ANB Tokyo」を立ち上げたんです。
これは、与えられた環境と予算で展覧会を実施できるようになった僕に対して投げかけられた新しい挑戦でもあります。これまではメディア論が主戦場で、「テクノロジーはどんな影響を社会にもたらすのか」「今のメディア環境で起こりうることは何なのか」といった問いを、展覧会を通じて投げかける仕事をしてきました。でも、そのメッセージを受け取った鑑賞者やボランティアの方から「伝えたいことは痛いほどわかりました。それで、私たちはどうしたら?」という質問が出てきて。そこから、この問いの行方はどうなるのだろうと考え始め、自分で投げてしまった問いを、自分自身も引き受ける必要があると感じたんですね。それで実社会の中で、新しい構造や事業を構築していくことに関心を持ち始めるようになりました。

出会ったことのない人たちが出会い、発火する。
「ANB Tokyo」は異なるコミュニティの人たちや面白い才能を持った人が交わる中から、新しいものが生まれていくことが大事なので、トップダウンの従来的なキュレーションで展覧会をつくるのではなく、何かが生まれる状況そのものをつくることが重要だと思いました。一見、作家同士がごちゃごちゃとやっているように見えるキュレーションも、作家同士や鑑賞者同士を結びつけるミックスゾーンを起こそうとしているもの。出会ったことのない人たちが遭遇し、出会い、発火する。こういった状況を準備しておくと、集まってくる人たちがいて、彼らとそこで生まれる出来事とを結びつけ、両輪で回すことに挑戦しています。
ミックスゾーンをつくることに成功している事例は、海外に多くあります。例えば、ニューヨークにある非営利の文化センター「Pioneer Works」。アートと科学の実験場のようなところで、様々なコラボレーションや事業が生まれているようです。まだ行ったことがないので、いつか行ってみたいですね。同じくニューヨークにある現代美術館の「New Museum of Contemporary Art」には「NEW INC」というインキュベーション施設が併設されていて、これも面白いミックスゾーンではないでしょうか。
Pioneer Works
ニューヨーク市のレッドフックにある非営利の文化センター。アートと科学を通してインスピレーションを与えるコミュニティづくりをすることを目的としている。制作やアイディア交換の場、道具などを提供し、資金の85%は参加無料のプログラムに使われている。
撮影:Taylor Nelson
New Museum of Contemporary Art / NEW INC
1977年にマーシャ・タッカーによって開館したコンテンポラリーアートの美術館。若手作家や革新的な作家の展示を行うことで知られる。2007年に移転、再開館した際の設計は、SANAAとGensler。「NEW INC」は、2014年に新設されたアートインキュベーション施設で、アート、デザイン、テクノロジーに特化したビジネス支援やプログラムを実施している。
https://www.newinc.org/
このような営みを成功させるには、どんな価値が生まれるのか予測しづらい取り組みに対して立てるKPI等の効果測定、評価にも多様さが求められますよね。欧米、西欧にはそのようなミックスゾーンが社会に与える影響を可視化する仕組みや、文化や福祉といったソーシャルセクターのアントレプレナーシップがあるし、富裕層や大企業がアートを支援するフィランソロフィーが根付いている。それらがミックスゾーンの成功の基盤になっているんだと思います。
「テーマを放つ」「人生に寄り添う」「無作為な熱量を信じる」
僕がキュレーションをする時に大切にしている手法は、3つあります。まずは「テーマをしっかり放つ」こと。社会的な状況を理解した上で自分なりの問いを立て、言葉では伝わりづらい、アーティストの個人的な目線や感覚的なことを内包したアートを通して、見る人の感情に届ける。それによって同時代を生きる人が開眼するきっかけをつくること。
次に、アーティストの「人生に寄り添う」こと。大御所であればその人のキャリアを見つめ、その人生が見る人の心の中で"発火"するところを見つけてテーマを引っ張ってきます。若手であれば、作家人生のターニングポイントになるような問いかけをして、作品が出てくるのを待つ。時に語り手のように、時にメンターのように、アーティストの人生に寄り添うのもキュレーターの仕事です。
そして、「生まれてくる熱量を信じる」こと。WIP(=ワークインプログレス)のわらわら、もやもや、もこもこしている状態を受け入れて、何ができるかわからない状態から種が出てくるよう、ファシリテーションをする。そうすることで、出会ったことのない人たちが出会い、発火する瞬間をつくることができる。
例えば、あるアーティストがネオン管を用いた作品を持ってくることがわかると、それを受けて別のアーティストが自分の作品に活かす。そういった交歓の中から生まれる熱量を信じて曖昧な状態を受け入れながら、その中にある魅力を磨いていくことで、これまでと違う面白い展覧会ができるんです。「ANB Tokyo」で行っている展覧会『Encounters in Parallel』も、普段別々の場所でパラレルに制作をしているアーティスト同士が遭遇するという意味を込めてつけたタイトルです。
Encounters in Parallel
ANB Tokyoで2021年11月27日~12月26日の間に行われる企画展。2020年のオープン時に26組のアーティストが集結し行われた企画展『ENCOUNTERS』をアップデートしたもの。4つのフロアを使い11名のアーティストが同じ空間を共有しながら作品を発表する。
会場:ANB TOKYO (東京都港区六本木5-2-4)
会期:2021年11月27日(土)~12月26日(日)
https://6mirai.tokyo-midtown.com/event/encounters_in_parallel/
日本はアート領域でもガラパゴス化していく。
日本ではアートマーケットが育たないと言う人がいます。たしかに、日本のアーティストが世界のアートマーケットで扱われている割合は、数%です。けれど、これでも数年前に比べると劇的に活性化しました。渋谷西武や伊勢丹のような、もともと古い芸術を扱っていたところもどんどん現代アートを扱い、評価されるようになっています。
それでも日本におけるアートマーケットは依然として小さく、昨今は、中国を除くアジアの現代美術の拠点が韓国に移っている感覚はあります。そして、日本はあらゆる領域において「鎖国」の感覚が根強いと感じています。アート領域も例外ではありません。しかし、世界各国がしのぎを削る国際戦に、当然のように世界の一員として挑むという感覚ではなく、日本独自のマーケットの中で何をするかという感覚がいまだに強いのではないでしょうか。韓国は、昔から世界を意識してマーケットを進化させてきました。その成果がアート領域にも表れているんです。
グローバルスタンダードのアートを横文字で「Art」、日本独自のアートを日本語で「アート」とした場合、日本の一般の人にとって「Art」はまだまだ浸透していないと思うんです。反対に、若いうちから海外に出ていくようなアーティストは「Art」を意識している。ですが、日本固有の「アート」が国内で広まっていくと「Art」との乖離が大きくなってガラパゴス化していくのだと思います。日本のポピュリズムやマーケットの価値観に偏った「アート」が大きくなっていくと、世界的に通用する分脈で勝負したいアーティストにとっては、日本が非常に難しい環境になってきます。ですが、そこで日本の状況に沿っていくと国際的な動向から外れた存在になってしまうので、若手アーティストはこういった日本独自の「アート」観に踊らされないことが重要で、海外に出てみるというのもひとつの手段かもしれません。
撮影場所:ANB TOKYO『Encounters in Parallel』(開催中〜2021年12月26日)
RELATED ARTICLE関連記事