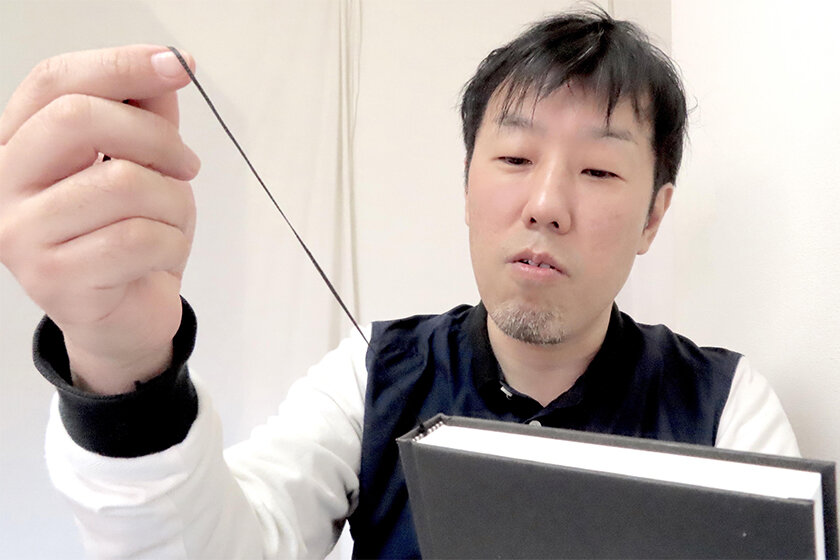
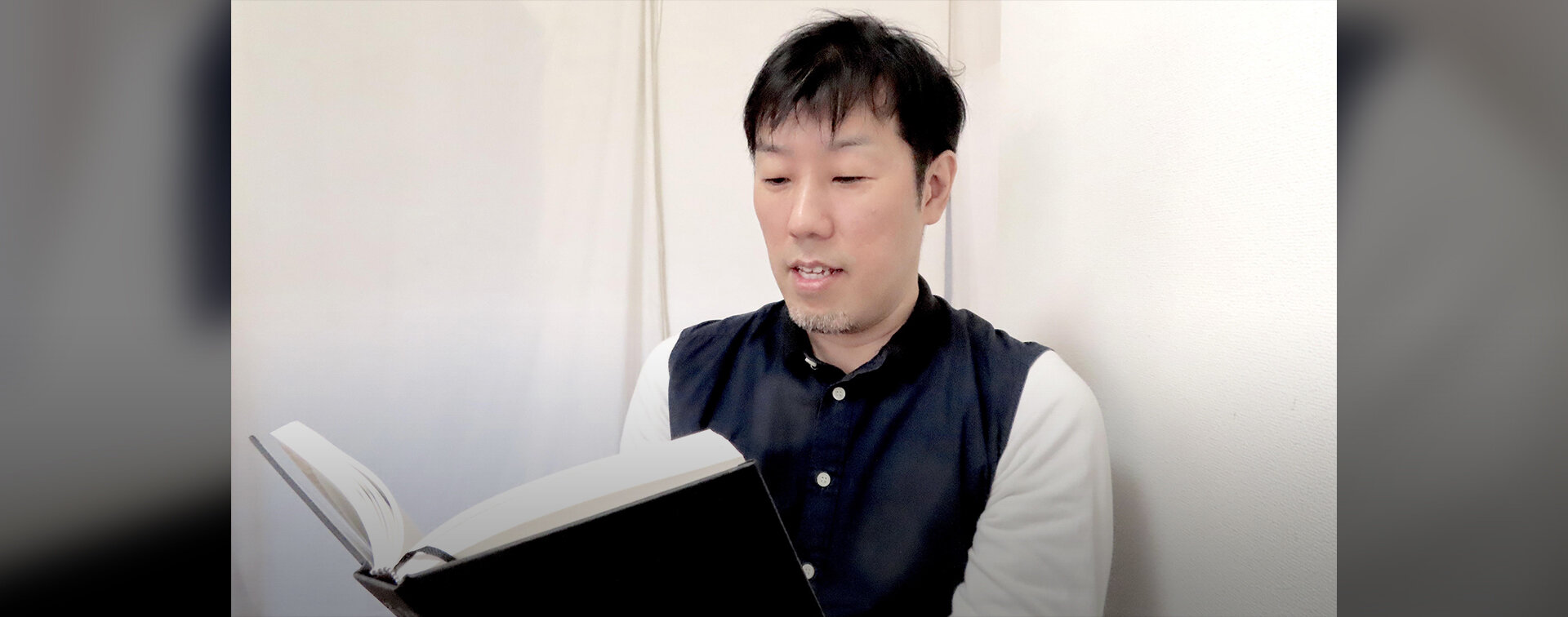
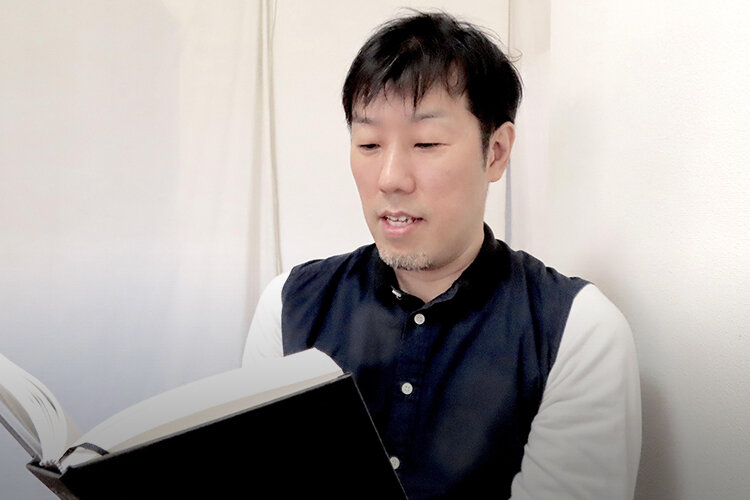
INTERVIEW
125
Takahiro Iwasaki / Artist
岩崎貴宏美術家
Takahiro Iwasaki / Artist
『都市を表象する“日用品”のありかを探る』【前編】
土地に根付くアートから、マクロな都市空間が見えてくる。
- JP / EN
update_2021.03.03
text_ikuko hyodo
広島の"原爆体験"を通じて得た、都市を俯瞰する視点。
僕が作品制作を通じて都市の風景を扱うようになったのは、故郷であり活動拠点でもある広島の歴史というのがすごく影響していて。広島は、今から76年前に原子爆弾、つまりミクロなウラン原子が上空500mで炸裂して、マクロな都市だけでなく、郷土の歴史という大きな時間軸も一瞬で破壊し尽くされてしまった。自分たちはそういう街で生まれ育ったわけです。それはたとえば「エヴァンゲリオン」のセカンドインパクト後の世界や、「AKIRA」で言えば東京が破壊された後の"ネオ東京" に生きているようなもの。要するに、自分たちが生まれる以前に巨大なカタストロフがあった都市に生きているんですね。そういうわけで、都市に対してジオラマ感というか、一瞬で消え去るようなもろい空間感が僕の中にあるんです。それは高度経済成長期以降、スクラップ&ビルドを繰り返している都市すべてにおいてもそうで、やっぱりもろさや移ろいやすさを感じてしまいます。
小学生の頃は、飛行機が上空を通るのが怖かったんです。また原子爆弾を落とされると思ってしまうから。僕だけでなく、同級生も似たようなことを言うんですけど。広島の学校に通った子どもは平和教育を受けているので、8月6日の8時15分、上空をブーンと飛んでいる飛行機から原子爆弾が落ちてくる様子を、アニメやドラマ、小説などで何度も何度も刷り込まれるんですよ。真っ青な空に銀色の機体がキラッと光って、次の瞬間、真っ白になるっていうイメージを。僕が子どもの時は、広島空港が当時まだ広島市内にあって、小学校の上空を飛行機がしょっちゅう通っていたんですね。それがすごく嫌で、「あ、次の瞬間消えてしまうかも」っていう恐怖心をリアルに抱いていました。そんなこともあって、上空からの視点というか、都市を俯瞰するような視点を疑似体験している。トラウマってほどでもないかもしれないけれど、子どもの頃にそういう視点を否応なしに持たされたわけです。都市のフラジャリティに対する恐怖心は、そういった体験にも源泉があるのだと思っています。
だから、大学の古美術研究で京都に行った時は衝撃でした。何百年も残っている建物を目の当たりにしながら、歴史や文化のにおいをはじめて吸って、「え、こんな世界があるのか」と。僕が留学したスコットランドのエディンバラも500年前から残っている都市で、街自体が世界遺産に登録されているのですが、その風景もやはり衝撃で。自分の生まれ育った街がいかにプラモデルみたいなものだったのかを突きつけられました。
都市を表象する日用品というマテリアル。
「アウト・オブ・ディスオーダー」シリーズのような、歯ブラシやタオルなどの日用品を作品に用いることが多いのですが、これもまた生まれ育った広島と関係しています。僕が中学生の時に広島市現代美術館が開館したのですが、それ以前は美術館に行くといったら広島平和記念資料館なんですよ。そこに展示してあるものの多くは日用品なんです。たとえば、ボロボロになった服や焼け焦げたお弁当箱のような、都市が破壊され尽くして残ったものです。資料館ではそういった日用品が、都市全体を表象させるものになっていて。あとは、壁に黒い雨が染み込んで垂れている光景とか、家が燃えてできた煤が雨と混ざって黒いラインを落としている光景とか。そういう日常的なものが特殊性を持ち得ていることについて、当時はかなり気になっていました。
アウト・オブ・ディスオーダー
タオルの繊維、ブラシの毛などの日用品を素材にして、鉄塔や架線、鉄骨といった巨大な構造物をジオラマサイズの風景に見立てる、岩崎さんの代表的なシリーズ。
アウト・オブ・ディスオーダー(コニーアイランド)
2012
©Takahiro Iwasaki, Courtesy of ANOMALY
広島市現代美術館
日本初の公立現代美術館として1989年に開館。企画展の他、約16,000点以上の所蔵作品の中からテーマごとに作品を紹介するコレクション展を開催。建物は黒川紀章氏が設計。現在は改修工事に伴う長期休館中で、リニューアルオープンは2023年3月の予定。
作品に日用品をよく使うようになったのは、エディンバラに留学してからなのですが、当時お金がなかったという理由もあって。本当に貧乏で、マテリアルを買えなかったんです。「画用紙が200円もするんだ。だったらジャムを買えるな」って、結局ジャムを買っちゃう(笑)。そうすると家にある広告の紙や、道に落ちてる輪ゴム、タバコの箱なんかで作品をつくろうってことになって、よくよく考えれば、タバコの箱も解体すれば画用紙じゃん、と思ったりして。
うちは父親が自営業でケーキ屋をやっていて、店の前に洋服屋があったんです。洋服屋って厚紙が結構出るんですけど、母親が「これで何かつくりなさい」と大量にもらってきてくれて。ずっとひとりでロボットとかをつくっていたんですが、中学生の時にそれを友だちにはじめて見せたら、「材料を買わずに、そんな汚いものをつくってるの?」と言われてショックを受けて、それまでつくったものをその時点で全部捨てちゃったんです。大学ではデザインを専攻したこともあって、「作品はきれいにつくるもの」と学んだのですが、エディンバラに留学したら、向こうの人たちはアバウトだから、何かをつくるにしてもセロテープや糊がはみ出していてもまったく気にしない。それを見て、そういえば自分も小、中学校くらいまでは、こんなふうに好き勝手にロボットをつくってたのに、どうしてやめちゃったんだろう、と羨ましく思って。その体験もきっかけになって、また日用品を使うものづくりに戻っていったんです。
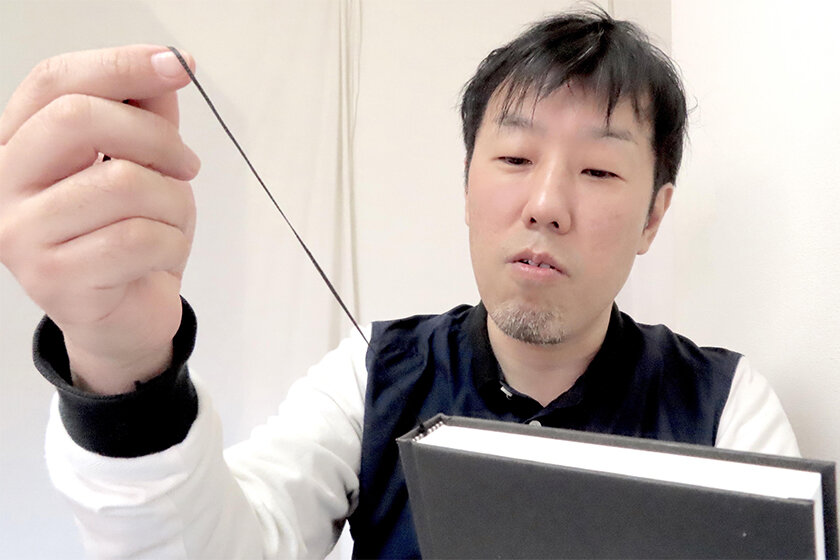
生まれ育った土地への誇りが独自性を生む。
広島を活動の拠点にしている理由には、経済的なことや自分のアイデンティティなどいくつかの側面があります。もちろん東京のような大都市に出ていきたい気持ちもあったのですが、東京は1日生きていくのに結構なお金を稼がないといけない。であれば、極力お金のかからない場所で、ゴミを拾って楽しく作品をつくれないかなっていう。だからお金のために働かないぞっていう意志を持った時、ランニングコストが低い場所として、生まれ育った広島が重要なポイントになったんです。
あとはスコットランドの首都であるエディンバラの人たちって、大抵イングランドが好きではないんですよね(笑)。なんでこの人たちはロンドンに出ないんだろうって最初は思ったんですけど、「ロンドンなんか全然興味ねーし、俺たちには俺たちの歴史があって、アートがあるから」って感じで、スコティッシュ・アーティストという故郷に誇りを持っているんです。その姿を見て、大都市に出ていくよりは、生まれ育ったところの文化を自分たちがどう継承して、それを次に繋げていくのかが大事だと思いました。住むところを東京にした時点で、周りの人と同じモチーフや土俵で争わなくちゃいけなくなるけど、プロセス自体に他の人と何かしら変わったところがあれば、生まれてくるものも自ずと人とは違うものになるはず。そもそもの前提を変えることによって、必然的にある種の独自性が生まれるのかな、と。
とはいえ、東京などの大都市は才能が溢れ返っている場所でもあるので、羨ましさもずっとあります。ただそれも諸刃の剣で、才能のある人たちに触発されるのは大きいポイントと言えるけど、同時に才能の消費も早いからすぐに新しいものを求められて飽きられるか、もしくはすごい人と出会ってかなわないと感じて、諦めてしまうようなリスクもある街だとは思います。だから僕としては、たまに刺激をもらいに行くのが一番いい距離感ですね。
※画像はオンラインインタビューで撮影した画像を使用しています。
RELATED ARTICLE関連記事





























