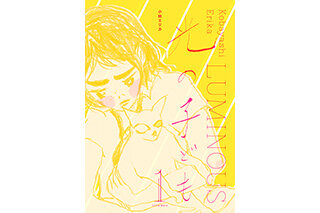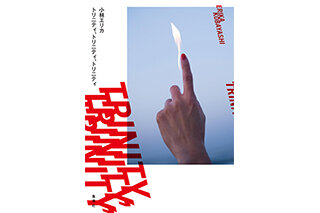INTERVIEW
124
Erika Kobayashi / Novelist / Manga artist
小林エリカ作家 / 漫画家
Erika Kobayashi / Novelist / Manga artist
『都市に潜む、歴史の痕跡を探索する』【前編】
“目に見えないもの”は、半径1mにある。
update_2021.02.10
photo_yoshikuni nakagawa / text_akiko miyaura
救いのある、安心できる場所。
六本木は大人の街という印象で、若い頃は来るたびに緊張していました。ここ「文喫」ができる前は、同じ場所に青山ブックセンター六本木店があって、そこだけは緊張せずにいられる場所だったんです。残念ながら2018年に閉店してしまいましたが、その後「文喫」という本にまつわる場所ができたことは私にとって大きな救いであり、今も安心して六本木に来られる理由のひとつになっています。
文喫
「本と出会うための本屋」として、2018年にオープン。文化を喫する入場料のある本屋であり、人文科学や自然科学からデザイン・アートまで約3万冊の書籍を販売している。一人で本と向き合うための閲覧室や、複数人で利用可能な研究室、小腹を満たすことができる喫茶室を併設。エントランスでは珍しい雑誌を販売する他、定期的に企画展を開催している。
大人になってからは、森美術館や国立新美術館で展示をさせてもらったり、Yutaka Kikutake Galleryが数年前から私のギャラリーになったりというご縁もあって、頻繁に来る街になりました。六本木で新しい展覧会が開けば必ず足を運んでいますし、「文喫」をはじめステキな本屋さんと美術館がたくさんあるので、はしごをすることもあります。
Yutaka Kikutake Gallery
2015年、オーナーの菊竹寛の手によって六本木に開廊。国内外のアーティストとともに、多様化する現代美術の展覧会や時代を見据えた活動を展開している。絵画や写真、彫刻、映像など同時代に制作される作品を紹介するとともに、アーティストトークの開催や展覧会カタログ、アーティストブックの出版など多角的にアートを支えている。写真は、小林さんの個展『野鳥の森 1F』(2019年)時のもの。
書けば、死なずに生きられる。
本との出会いは、私にとっても大きなもの。10歳の時にアンネ・フランクの『アンネの日記』に出会ったことが、私の大きなテーマ"見えないもの"を意識したきっかけでした。「わたしの望みは、死んでからもなお生きつづけること!」(※)という一節に、「書けば、死なずに生きられるんだ」と子どもながらに感動したのを覚えています。以来、大人になったら、作家かジャーナリストになることを夢見るようになりました。
大人になった今も、ふとアンネ・フランクはいないけれど、彼女が書いたものが読めるという事実に深く感動するんです。一方では"おばあさんになったアンネ・フランク"の文章を読めないという現実も、私に大きな影響を与えています。ひとつのきっかけとなったのが、30歳くらいの頃に目にした自分の父親の日記でした。それは第二次世界大戦中、当時16、17歳だった父が書いた日記だったのですが、それを書いたのが今目の前にいる80歳の父親というのも不思議な気分でした。それにくわえて父がアンネ・フランクと同じ年の生まれ(1929年)だと知り、さらに衝撃を受けたんです。アンネが生きていたら、80歳のおばあさんになっていたんだ、と。
以来、誰かが生きた痕跡、日記には書かれなかった一瞬一瞬みたいなものに思いを馳せるようになりました。もっと言えば、日記を書くことができなかった誰かの人生にも、同じように大切な瞬間があったはず。だとするなら、今ここに生きている私が、消えてしまった誰かの一瞬や生きた痕跡に気づき、どうすくいあげて紙の上に書き留めるのか。そう考えはじめてからずっと、"目に見えないもの"が私のテーマになっています。
※『アンネの日記 増補新訂版(文春文庫)』著:アンネ・フランク、訳:深町眞理子 より

西暦3503年まで残り続ける、見えない痕跡。
私のつくるものには、"放射能"がよく登場します。みなさんと同じように東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の事故で、より身近なものになったのは確かですが、実はそのずっと前から"放射能"と呼ばれるものの歴史について興味を持ち、調べていたんです。そんな中、放射性ラジウムの発見者であり、ノーベル化学賞を2度受賞したマリ・キュリーの実験ノートの存在を知りました。探してみると、実は日本の明星大学の図書館にあることがわかったんです。見た目は布貼りのかわいらしいノートですが、表紙にガイガーカウンターをかざすと、かすかに反応する。聞くとマリ・キュリーが素手で放射線量の高い物質を触っていたため、指紋がついた部分は今も線量が上がるのだそうです。
マリ・キュリーがはじめてラジウムを手に持ったのが、今から120年近く前の1902年。放射性物質の半減期が1601年と言われているので、西暦3503年になってもノートについた彼女の指紋は残り続けることになります。その時、皮肉なことでもあるけれど、ふとアンネ・フランクの「わたしの望みは、死んでからもなお生きつづけること」という言葉に繋がった気がして。マリ・キュリーという名前を未来の人は覚えていないかもしれないけれど、彼女の生きた痕跡は残る。そう考えたら、"放射能"や原子力という問題を良いか悪いか、賛成か反対かではなく、それらを超えたところで捉えて書くことが必要かもしれないと思ったんです。それが私の著書『光の子ども』であり、これまで書き続けてきたシリーズやインスタレーションです。
『光の子ども』
今回のインタビューの中でも登場した、科学者マリ・キュリー。彼女が発見し、「わが子」と呼んだ放射性物質の歴史を、過去にタイムスリップをした光少年と、ネコのエルヴァンの目を通じて紐解いていく。"放射能"はいつ、どこから、どうやって、ここに来たのか。小林さんがコミックとして描いた、史実とフィクションを交えた物語。
分からない、という前提からはじめる。
また、父の日記は、もうひとつ私に考えるきっかけを与えてくれました。自分にとって父親は常に父親で、大人だけれど、日記の中にいるのは今の私よりもずっと若く、青春に悩む16、17歳の少年。何十年と一緒にいたはずなのに、その向こうには語りえないこと、知りえないことが広がっているんだと、気づかされたんです。分かりえないって、すごく絶望的に思えるじゃないですか。でも、私は分かったつもりになっていたことの方が悲しくて。
分かったつもり、は日常にも転がっているもの。私自身はじめて東京電力福島第一原子力発電所の構内に入らせてもらった時に、あらためて気づかされたことがあります。「"放射能"は見えないものだ」と書き続けてきたにも関わらず、自分が思い浮かべていたのは転がった瓦礫や生い茂った森といった目に見えるイメージだったんです。でも、実際の構内には草木などなくて、一面銀色のモルタルに覆われたSF映画のような光景でした。しかも、建物の中にはローソンがあって、うちの近所にある店舗と何ら変わりない。それを見た時、これまで自分は、"放射能"というもので、汚染された場所というものを、まるで自分とは関係のない別世界のように思い描いていたことに気づいたんです。
そしてそこから、分かったつもりではなく、分からないながらもどう想像するか。見えないものを見えるようにするのではなく、見えないものを見えないまま、どう伝えていけるのか。はじめてそんなことを考えて制作したのが、最新作の『トリニティ、トリニティ、トリニティ』や、国立新美術館の展示(『話しているのは誰? 現代美術に潜む文学』)でした。見えない、分からないという前提ではじめれば、その先に希望があるのではないかと思ったんです。
『トリニティ、トリニティ、トリニティ』
小林さんの最新作。舞台は2020年夏、オリンピックに沸く東京。主人公とその母、娘、妹。その日常は、高齢となった母の入院で少しずつ変化していく。同じ頃、街にはトリニティと呼ばれる不気味な症状に取り憑かれた老人たちが現れ、予想外の行動を起こし始める......。"目にみえざるもの"の怒りを背負った者たちが立ちあがる、ノンストップ近未来長編。
100年後の未来を握る、"選択"の切実さ。
今は世界中が、目に見えないコロナウイルスと向き合っている最中。きっと、否が応でも見えないものに目が向くと思うんです。できることなら、怖いものは見たくないし、考えたくない。だから、分かったつもりで安心したいという気持ちも理解できるんです。それでも、やっぱり見えるものがすべてじゃないということの当たり前さに、細々と気づける自分でありたいな、と。もうひとつ感じるのは、立場の弱い人に何もかもを押しつけてやり過ごそうとする、人間の目に見えないものへの対峙の仕方。それは、放射性物質が降った事故の時から、さほど変わっていないのだと実感します。
ただ、私はこの世界に絶望はしていないんです。たとえば、エックス線や放射線が発見されたのが100年ちょっと前。当時の歴史を調べていると、たった100年前なのに女性には選挙権すらありませんでした。でも、100年でこんなに変わったのだと考えると、ここから先の100年で社会も人ももっと変われるはずだと希望が湧く。作品を書きながら、そんなことをしみじみ思ったりしています。
100年後を変えるためには、選択が大事だと思います。以前、『アンネの日記』と父の日記を手に、アンネの足取りを死から生へ向かって辿り、自分自身も日記を書き記す『親愛なるキティーたちへ』という作品をつくりました。その時にアンネが生涯を終えたベルゲン・ベルゼン強制収容所を訪れ、「ここがあと1週間早く解放されていたら」アムステルダムの《隠れ家》を訪れ、「あと数日の間、アンネがいたアムステルダムの隠れ家を密告する人がいなかったら」と、ひとつひとつの場所を訪れるごとに、彼女が死なずに済むための理由を想像したんです。そうして、アンネが生まれたフランク・フルト・アム・マインへ辿り着いた時、「もしもあの時、誰もナチ・ドイツに投票しなかったなら」と思ったんです。
その時、切実に感じたのは一人ひとりが誰かの命を握っているということ。そして、自分が取る選択によって10年後の誰かを生かしも殺しもするんだということでした。結論は賛成であろうと反対であろうと、どちらでもいいと思うんです。大事なのは自分が選んだことが10年、20年先、100年先までも大きく影響すると知ること。目先のことにとらわれず、未来を考えて選択できる人でありたいというのは、私自身が強く思っていることでもあります。
(撮影協力:文喫)
RELATED ARTICLE関連記事