


INTERVIEW
123
Shin Sobue / photo_yoshikuni nakagawa / text_tami okano
祖父江 慎デザイナー
Shin Sobue / photo_yoshikuni nakagawa / text_tami okano
『経済と直結しないアートが育つ、意味のない場所をつくる』【後編】
伝えあい、関わりあい、そして「うまくいかない」喜びを求めて。
update_2020.11.25
photo_yoshikuni nakagawa / text_tami okano
それぞれが、それぞれのままで面白い。
トランスレーションズ展では会場のサインもつくりました。サインって標識だから、普通はわかりにくいと困るものなんだけれど、でも、今回は「わかりあえないピクトグラム」でサイン計画をしてもいいんじゃないかと。
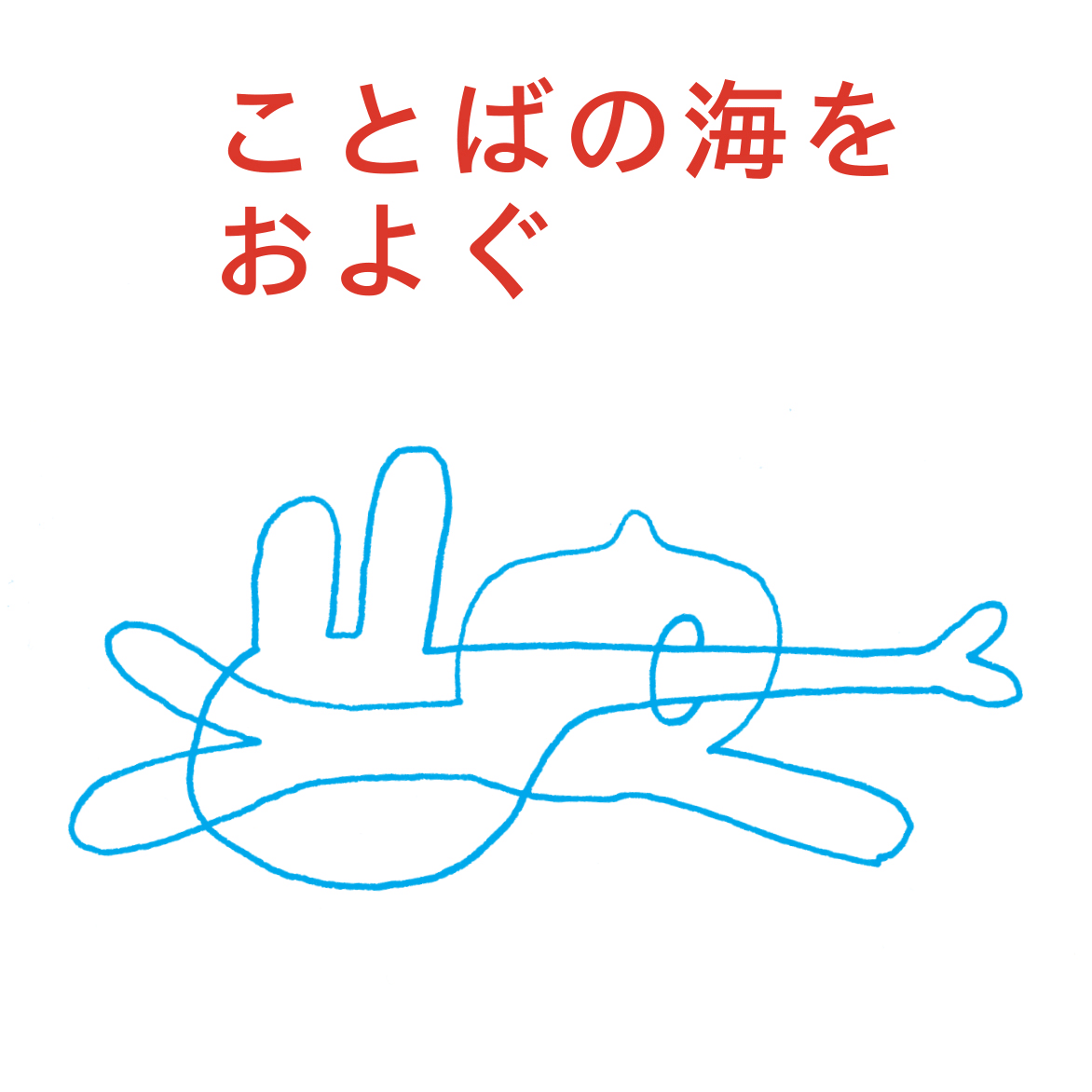
「トランスレーションズ展」ピクトグラム
会場の各セクションのテーマを表したサインを祖父江さんが手描きで制作。2つのキャラクターの関係性によって、絵柄や受ける印象が変化する可変的なデザインとなっている。
そもそもサインをつくろうと考えたのは、出展作品数が多く、それらを構造化するものがないと記憶に残らないし、探しにくいだろうな、と思ったのが始まりです。物語を感じるような章立てがあることによって、来場者は展示作品と関わりやすくなる。いわゆる潤滑油的なものですね。展覧会のディレクター、ドミニク・チェンさんと企画協力の塚田有那さんに相談し、その潤滑油となる「まとまりをもった言葉」を用意してもらいました。何かを固定してしまうような言葉ではなく、動いていく言葉がいいねとお話しして、「伝えかたをさぐる」とか「ことばの海を泳ぐ」とか、素敵な文章をたくさん出していただきました。その動きを表しているんだか、いないんだか、キューピーちゃんとウサギちゃんがくっついたり、お互いの中に入り込んだり、いろいろな関係をもっているという。勝手な勘違いピクトグラムです。
展覧会の会場にはいろいろな作品が置いてあって、その作品は、正確に伝えるために開発されようとしているものかもしれないけれど、でも結果的には、"勘違い"かもしれないデザインが作品の間にあることによって発生する何か、喜びのある空間とか楽しい時間とか、そっちの方が大事なんだ、という感じで今回僕はこの展覧会に関わっています。やっぱり人生で大事なことって、ちがうそれぞれが、それぞれのままでも豊かに関わり合うのも大切だと思いたいです。
デザインから遠そうな状態を、デザインとして用意する。
それともうひとつ、今回の展覧会に関わるにあたり思ったことは、デザインの先生的な視点ではなく、「デザインなんて、あんまり好きじゃないぜ」「なにそれ、わかんないよ」という人たちに向けて、「デザインから遠そうな状態」を、デザインとして用意したいな、と。だから、ピクトグラムはヘロヘロの手描きで描かせていただきました。自分で言うのもなんですが、上手い絵でもなんでもない(笑)。いいとはいえない。でも、悪いともいえないし、ちょっと、くすぐられるでしょ? どうかなー、採用されるかなー、と思ってドキドキしながら館長の佐藤卓さんに見せたら、いいね! と言っていただけたんでホっとしましたよ。
21_21 DESIGN SIGHTの活動を僕はいつも感心して見ているんです。21_21がやっていることって、デザイン教育でもあると思うんですが、デザイン教育って、ともすればお勉強っぽくなる危険性もあるし、難しい。でも、そうならないような試みをずっと続けていますよね。今回の展示では最初に、ドミニクさんの映像による挨拶があるんですけど、それがすでに笑えちゃうところがいい。詳しくは観ていただければ、ですが、ドミニクさん、ちょっとなに言ってるか、よくわかんないよ! って、笑いにつながるのも嬉しかったですね。どんなテーマを扱うにしても、あまり人を深刻にさせないほうがいい。
いや、それにしても、本当にわかりあえなさをわかりあうことほど、大事なことはないです。「わかりあう」って、相手を自分や社会の都合に合うように変換させることじゃない。相手の状態が悪くても、お互いに気持ちよく過ごせること。いろんな人がいるけれど、その「いろいろ」を無理に同じ状態にもっていくんじゃなくて、みんながバラバラのまま共存する豊かさ。そのヒントがこのトランスレーションズ展にはあるんじゃないかと僕は考えています。

裏通りに隠れられる場所がある街。
街を歩いていて気になるのは、人の流れ方、動線です。デザイナーですけど、街の看板のデザインとか、そういうのはぜんぜんどうでもよくて、知らない街に行っても、とにかく動線が気になります。なぜか。それは、人の動きを見ると、どこで隠れタバコが吸えるのかがわかるから。......っていうのは「おい、こら!」なので置いておいても、メインではない裏通りがどのようになっているかには興味があります。そこに犯罪のような危険に晒されることのない「隠れ処」があるか否かで街の面白さは変わってくる。
僕は20年くらい前に六本木に住んでいたことがあるのですが、東京でも特にこの辺りの変化は早いですよね。他の街なら100年くらいかかるような変化も、10年くらいだったんじゃないかと思うスピードです。まあ、変わっていくことはいいんだけど、個人的な希望としては、あまりスケスケになりすぎずに、弱い人とか、イジメられっ子が監視から隠れられるような場所を残しておいてほしいですね。あと、都市というのはたいてい、人間のために設計されているんですけど、人間じゃない生き物がどうやってこの六本木で生息しているのかというのも気になります。カエルとか。僕は、大変なカエル好きで、友だちだから。カエルとは。
街に必要なのは、「意味のない場所」です。それをなんとか確保したい。公園もある意味では意味のない場所だし、その意味のなさが意味を持つのかもしれないけど、目的が明確に決まっているわけではなく、なんとなくあるような場所。わりとゆるい目的のための施設やら建物ができるといいな。
経済と直結しないアートが育つ、意味のない場所。
ただ......なんにせよ、六本木は地代が高い。土地が高いから、経済と直結しないものが成り立ちにくい。目的をもたない「意味のない場所」を確保したいと思っても、そんなの土地がもったいないよ、ってなるでしょ。アートも都市であればあるほど、資本主義的なアートしか育たない。キャラクターものやポップアートといった、お金とセットになった「儲かるアート」がどうしても中心になってきてしまう。ただ、世界の動向で考えると、最近は少しずつ「お金と切り離したアート」に注目が集まってきているし、SNSとかでこれからはもう、東京にいる必要がない社会になっていくということを考えれば、これまでとは違う、経済と直結しないアートが育つような「意味のない場所」づくりに力を入れてほしいなと思います。
意味のない場所、つまりそれは無駄な場所とも言えるけど、21_21 DESIGN SIGHTもある意味、無駄だよね。経済にもあんまり直結してないし(笑)。素晴らしいですよ。こういう、儲からなくてもなんとか維持できる場所が増えてほしいです。昔から、愛と芸術っていうものが絶対的に良さげなもので、内容はどうであれ、芸術だー! 愛だー! っていえばなんとかなったんだけど、悲しいのは、デザインの認知度が高まったといったって、デザインだー! っていったところで、デザインに対するお任せ度は低いから、だからなんだよ、って言われてしまう。
かつてのオリンピックのエンブレム問題しかり、デザインが多くの人から監視されるようになったのは関心を持たれるという意味ではいいことだけど、まだまだ、勘違いが多すぎるよね。たとえば、デザインは多数決で決めたものがいいものだっていう勘違いというか、誤解。話しが元に戻っちゃうけど、デザインは説明ではないから。忘れていたことに気づかせてくれたりとか、見慣れてしまっていたものをもう一度ちゃんと見るきっかけになったりとか。簡単にはわかりあえないものの方が、いいんです。
取材を終えて......
取材時の祖父江さんの印象を一言で言うなら、よく動くロックンローラー。踊りながら登場し、「60歳を過ぎたのにまだまだ四十肩〜!」と肩をかばいながらも、取材後もまた踊りながら去っていきました。現場を楽しい雰囲気で盛り上げながらも、語る言葉にはデザインへの真摯な思いと優しさが溢れていて、何度も何度も噛み砕いて聞き直したい、哲学の授業のようでもありました。ちなみに、「みんなさ、身体の中を、右から左に風が通り抜けることってあるでしょ」と祖父江さん。それがワクワクしている状態で、デザインの作用なのだと知りました。楽しかった!(text_tami okano)
RELATED ARTICLE関連記事




























