


INTERVIEW
106
HIDEYUKI NAKAYAMA / Architect
中山英之建築家
HIDEYUKI NAKAYAMA / Architect
『ジャンルが混ざり合う線引きのない街に』【後編】
違う目線を持つことで当たり前だった地図が変わる。
- JP / EN
update_2019.07.10
photo_yoshikuni nakagawa / text_ikuko hyodo
地上からほんの少し浮いている木箱のような家や、道路を挟んで地下でつながっている2軒の家。中山英之さんの建築は、こちらの想像を軽々と超えて、空間に思わぬ表情を生み出します。TOTOギャラリー・間で開催している「中山英之展 , and then」もまたしかり。展覧会の組み立て方や、建築やアートなどとの向き合い方、そして街の捉え方などから、中山さんのてがけるものが人を魅了する理由を探ります。
建築以外のすばらしいものたちが、新しい世界へと連れていってくれる。
僕は高校時代、成績はでたらめ、取り立ててのめりこむようなものもない人間でして(笑)。今も大概ですが、まあそれでも、あるときふと入ってみたギャラリーで建築というものに出合ったことで、そこから自分にとっての世界がひとつ始まりました。建築そのものへの興味もそうですが、何より大きかったのは予備校や大学など行く先々で出会った人々から受ける影響です。彼らの話は、高校の教室では聞いたこともない固有名詞や知らない言葉であふれていて、すごく憧れました。それ以来、自分がまったく知らない映画のタイトルや、アーティストやミュージシャン、ファッションデザイナーの名前をこっそりメモしては、ひとりで映画館やギャラリーに通う毎日。新しい何かを見るとそれについて書かれた文章や批評も気になるようになって、世の中には小説や文学とは違う種類の言葉があることも知りました。
このとき出会った言葉たちは、僕にとってとても大切なものです。建築に興味を持ったことをきっかけに、映画監督や小説家やファッションデザイナーのような、ほかの分野の人々と直接お話をするような機会でも彼らとちゃんと話をすることのできる言葉を持てた。別の分野の言葉を知ると、また建築について考えることが広がっていく。
「CINE間」のロビーには、そうした過程で出合った自分にとって大切な言葉や本も、模型や図面の間に置かれています。たとえば、映画監督のフランソワ・トリュフォーがあのアルフレッド・ヒッチコックにインタビューをした『定本 映画術 ヒッチコック・トリュフォー』。映画のプロフェッショナルが、同業者の、しかも神様のような存在である監督から創作の秘密を聞き出すなんて、これ以上の教科書はありません。建築の世界では、磯崎新さんが例外的にそういう存在ですが、建築家は基本的に自分の話を聞いてほしい人たちばかりだから、同業者に話を聞くなんてまずやらない(笑)。映画監督もそこは似ていると思うのですが、トリュフォーみたいな人が稀にいて、同業者への憧れを隠さずに、しかもそれを文章にしてくれた。
そんなふうに、それぞれのジャンルのプロたちが、その分野の深淵を分かりやすく解き明かすような本が僕は大好きです。最近ではホンマタカシさんの『たのしい写真』とか。そういう本に出合うことは、もしかしたら僕にとっては建築について解説された本よりもずっと、頭の中の考えを遠くまで運んでくれるし、またひとつ世界を新しく開かせてくれる。映画を観たりファッションにときめいたりしながら、そこから新鮮なものの考え方や世界の見方を知ることは、今となっては、僕にとって建築を考え続けるために欠かすことのできないものになっています。
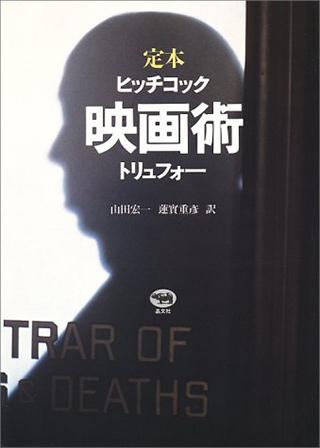
『定本 映画術 ヒッチコック・トリュフォー』
フランスの映画監督フランソワ・トリュフォーによる、サスペンス映画の巨匠アルフレッド・ヒッチコックへの50時間にもおよぶインタビューを網羅した書籍。膨大な写真とともに、ヒッチコックのテクニックや映画理論を徹底的に解説している。世界各国で翻訳されている、映画づくりのバイブル。
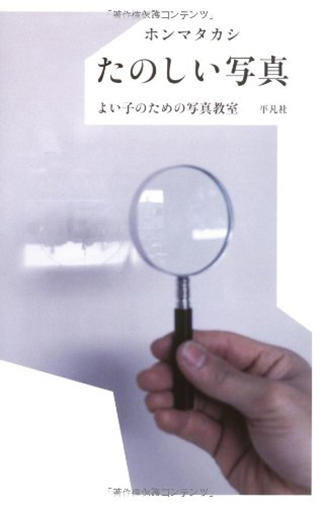
『たのしい写真―よい子のための写真教室』
現代写真の第一人者である写真家・ホンマタカシが、写真についてやさしく解説。写真の歴史から撮影のハウツーまで学べるとともに、写真家本人の思考を辿ることができる教科書的1冊。その後、シリーズ化され3冊目まで刊行されている。
何もないところに都市をつくる。
そんなことを言っておきながら、本音を言うと、ほかの建築家の仕事はできればあまり見たくないんです。だから建築を見に行くような旅をしたことがなくて、どこかの都市に行ったとしても建築を見ないで帰ってきてしまう。絶望するのが怖いんでしょうね。実はコルビュジエすらろくに見たことがありません。
そんな出不精なのですが、以前ラスベガスにひとりで行かなければいけないことがあって。砂漠の真ん中にあんな人工的な都市が存在して、しかもほかの都市とはルールがまったく違うのが面白かった。伝統や歴史なんて関係なく、月に都市をつくってしまうような感じですよね。世界中の都市が同じように見えてしまう時代に、一種異様なオリジナリティがある。だけどそれらはある意味フェイクの寄せ集めだから、部品ひとつひとつはちっともオリジナルじゃない。その不思議さがなぜかずっと気になっていて。アメリカのイベントのバーニングマンとか、バンクシーのディズマランドなら行ってみたいと思うのも、もしかしたら同じなのかな。自分でもまだよくわからないのですが、何もないところから世界をひとつ考えてみるようなことに、なぜだか今興味があります。

空間を読み替えると、都市の別の表情が見える。
東京藝術大学で准教授をしているのですが、音楽と美術の学部はあっても、美容やファッションを目指す人たちの学ぶ場所がない。僕は街で髪型やファッションを見るのも大好きなので、そういう人たちがどんな勉強をしているのか、すごく知りたいんです。だけど大学と専門学校というふうにそれぞれはっきり分かれてしまっているので、互いにすごく興味を持っているはずなのに、一緒に何かを考えたりする場面がない。あるとしても、たとえばブティックや美容院を設計するみたいな形です。六本木という場所には、なんだかそういう壁を越えた混じり合いを予感をさせる何かがあるような気がします。
そのために空間としてできることがあるとするなら、それはもしかしたら建築の形はしていないかもしれません。たとえば原宿には昔、ホコ天がありましたよね。銀座は今もやっているけれど、ふだん圧倒的に空間を支配している車がただいなくなるだけで、ありとあらゆる出来事が勝手に起こる場が生まれる。そういうことって、建築家のデザインしたかっこいい特設ステージなんかよりずっと自由で魅力的です。六本木はいろんな種類の交通機関が高架から地下まで複雑に交差しながら集まっている場所ですが、そんな空間本来の一義的な意味を、一時ただ忘れて見つめなおしてみるような瞬間が生み出せたなら、形は今のままでも、街まるごとを読み替えてしまうようなことができるかもしれない。そういう場所には、素敵な髪形やファッションがきっと似合うと思います。
ミツバチの視点から街を見つめてみる。
ファッションは「衣」、建築は「住」だからというわけではないけれど、mitosaya 薬草園蒸留所の仕事を通じて、最近「食」にも興味を持つようになりました。とはいえお酒って、生きていくうえで絶対に必要なものではないし、「食」と言ってもそんなに切実な話ではなくて。あとその場所でミツバチを飼い養蜂を始めたのですよね。これまで植物やペットに関心がなかったのですが、今、僕もミツバチを飼ってみたい。ミツバチは3キロも飛べるらしいんですけど、たとえば六本木で飼ったとしたら、新宿御苑や明治神宮あたりまで飛んで行けるわけです。街を歩きながらハチの行動範囲を想像してみると、自分の中の地図が変わってきますよね。
一義的な意味がなくなると、都市が変わるという話をしましたが、ハチは僕らと違う感覚でこの環境を捉えていて、彼らが組み立てる世界は僕らの世界とはまったく異なります。自分が持っていない目線になってみると、違う世界が現れる。そういった意味での食や第一次産業に、この頃興味を持つようになりました。

mitosaya 薬草園蒸留所
2015年末に閉園した千葉県大多喜町にある薬草園の跡地を引き継ぎ、ボタニカル・ブランデーの蒸留所を立ち上げるプロジェクトが2017年よりスタート。蒸留酒の原料となるハーブなどの植物を育てるとともに、園内に生態系をつくるべく、2018年より養蜂も手がける。中山さんは、蒸留施設などの設計を担当。
取材を終えて......
建築は難しい。漠然とそんなイメージがあっても、中山さんの個展を見て、さらにはお話をうかがうと、建築とほんの少し仲良くなれたような気になってしまいます。ヒッチコックの映画のように、なんとなく見た人から通まで楽しめるいろんなしかけがそこにはあるのでしょう。取材のときに着ていた牛がプリントされたTシャツも、人を楽しませたいというちょっとしたしかけ。最後にお話ししてくれた、第一次産業にちなんでのチョイスだったようです。「居心地の良いインパクト」は、中山さんのつくるものにも人柄にも表れていました。(text_ikuko hyodo)
RELATED ARTICLE関連記事



























