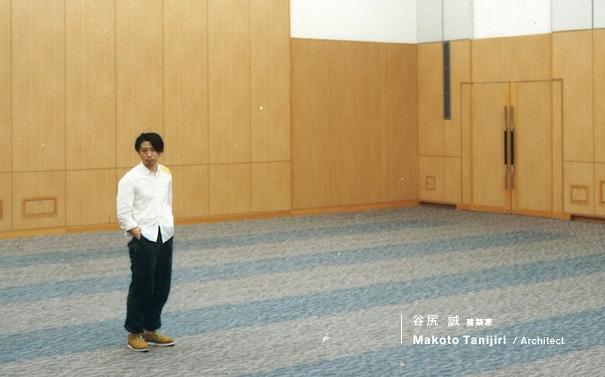
05 谷尻誠 (建築家)
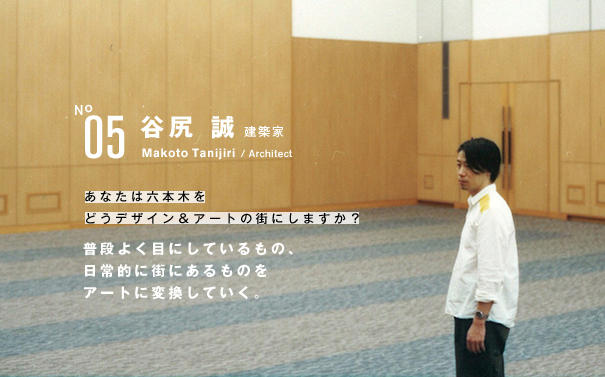
住宅から商業施設、展覧会の会場構成など、幅広い分野の空間デザインを手掛ける建築家の谷尻誠さん。その谷尻さんが、本拠地・広島のみならず、東京、そして海外でも活躍するきっかけになったと語るのが、2008年と2009年に行った「DESIGNTIDE TOKYO」の会場構成だ。場所はここ〈東京ミッドタウン・ホール〉。久しぶりにホールを訪れた谷尻さんは懐かしそうに周囲を見渡し、自身が新しい一歩を踏み出したこの場所で、六本木の未来を考えます。
既にあるものをアートに変換する。
ある限られた期間だけではなく、もっと日常的に、六本木をデザインとアートの街にしていく。それなら僕は、既にあるものをアートに変えたい。アートって、美術館のような見るべき場所に行かないと見られない、というイメージがありますよね。でも僕は、街を歩いているだけで「いつの間にか見ているもの」がアートになっているほうが、面白いんじゃないかと思うんです。
気づくと、ここにもある、あそこにもある、というように、だんだん増えて繋がっていく。そうすると、見る側の視点が変わり始める。アートはどこ? と探し始めることで、アンテナの張り方も変わる。その視点や感覚の変化が、本来アートの効果だと思いますし、信号機だったり雑居ビルだったり、普段よく目にしているものが全く違う現れ方になることで、街が変わっていけばいいな、と思います。
滝で車を止め、ビルに服を着せる。
具体的には、たとえば、横断歩道なんてどうでしょう。人が道を渡るときだけ、ダーっと両側に滝ができる。海を割ったモーゼみたいな気分で渡れる(笑)。つまり、人が通るために車を一時的に止める方法は、信号機だけではない、ということに気づけば、いろんなことが考えられる気がするんです。
建物に服を着せる、というのも以前からやりたいと思っていることのひとつです。古いテーブルにレースのテーブルクロスかけ、新しいものに転換するのと同じで、古いビルにレースの服を着せてあげると、それ自体が新しい価値を持ち、作品化しますよね。ビルの壁を塗るとなると、その場で何日も作業するための足場が必要になりますが、服なら別の場所で作れるし、脱ぐこともできる。「DESIGNTIDE TOKYO 2008」でも「布の建築」をテーマにしましたが、日本のファブリックのテクノロジーは世界の最先端をいっているので、もっと面白い使い方が出来るんじゃないかな。

『DESIGNTIDE TOKYO』
インテリア、プロダクト、建築、グラフィックにテキスタイル、ファッションなど様々なジャンルから集まったクリエイターのデザイン活動を発表するためのエキシビジョン。画像は谷尻さんが会場構成を担当した DESIGNTIDE TOKYO 2008 年、2009年の様子(会場:東京ミッドタウン・ホール)。
あのリッツがギャラリーに!?
期間限定のイベントでデザインとアートの街をアピールするのであれば、六本木の〈ザ・リッツ・カールトン東京〉(以下リッツ)の部屋を、ギャラリーにしてみたいですね。ホテルの部屋は昼間空いているのだから、その時間に作品を飾って、部屋の数だけ小さなギャラリーがあるという考え方で開放する。普段リッツに入れる機会は少ないけれど、ギャラリーであれば入りやすいし、泊まる人はアートと一緒に長い時間を過ごすことができる。
絵を飾るとそこをギャラリーと呼び始めるわけで、ホテルなのかギャラリーなのか、その両方である、という状態があってもいい。平面の作品だけではなく、ベッドや寝具が作品になっていてもいいし、そういう状況自体が何だか楽しそうですよね。
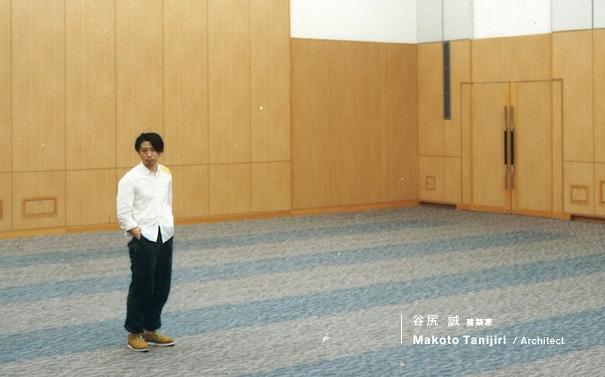
違和感が視点を変えるきっかけになる。
大事なのは、違和感。アートには特に、いい意味で違和感が必要なんじゃないかな。僕らは常識の中で生きていて、たとえば、水の入ったペットボトルを見れば、その重さを想像できる。普通はこのくらい、という常識がある。でも、パッと持ったときに、すっごい軽かったら、思わず手が上がってしまう。予想と重さが違うから。逆にすっごく重かったらビックリして手が下がる。それって違和感じゃないですか。常識が介在しているところに違和感が発生する。違和感が驚きを生み、その驚きが、視点を変えるきかっけになる。
何の前提もないところで凄いことが起きていても、凄いかどうか判断できないんですよね。だから、何かしらの前提条件があるところで、その前提をもう一度見直すことができたら一番面白いし、意味があるんじゃないかと思います。
問いを立て、その問いを見失わずに作る。
前提を見直すということは、僕の建築に対するスタンスでもあります。設計はいつも、普通だと言われたり思われたりしていることを、もう一度「問う」ことから始まります。何でここをリビングって呼んでいるんだろう、リビングを決定づけているものは何だろう、とずっと「問い」を立てていく感じですね。そうやって考えていくと、リビングじゃないところにリビングができる。
単純に、いつもと違う使い方ができると新鮮ですよね。そこに、常識ではやっちゃダメ感が介在していると、さらにワクワクする。たとえば、銭湯でライブとかしてみたいじゃないですか。ライブハウスを作ってください、と言われると、僕らはやっぱり、今までの「ライブハウスらしいもの」を作ってしまう。でも、人が歌を歌ったら、風呂だってライブハウスになるわけで、ライブハウスの何がライブハウスであることを決定づけているのか。その「問い」を見失わなければ、今までにない全く新しいライブハウスを作ることができる。
広島で始めた「THINK」の意味。
広島の事務所の上にギャラリースペースを設け、昨年からそこで「THINK」という活動を始めました。トークイベントを開催したり、一夜限りのスナックを営んでみたり。この「THINK」はまさに、「何がそのものを決定づけているのか」を発見するための実験の場です。僕は、それを発見することが、デザインの本質だと思うんです。

『THINK』
ゲストを招いてのトークショーと、その時々のゲストに関連する企画を行う「THINK」。日頃展示会や講演会などが東京と比べて少ない広島で、毎月一回、国内外で活躍するクリエイターの活動内容や発想の原点、物事の生まれる背景について語り合う企画。
昨年静岡で、居酒屋をカフェにリノベーションするという仕事をしました。その時も何が居酒屋らしさやカフェらしさを成しているのかを、とことん考えました。そのうえで手を入れていくと、必ずしもハードを変える必要はなく、中側の使われ方だったり、置いてあるものだったり、ソフトの重要な部分を抽出し、整理して元に戻すだけで充分新しい空間になった。
六本木の街も、たとえハードはそのままでも、ソフトの面白い部分を一度バラバラに抽出し、整理して戻していくだけで随分変わると思います。
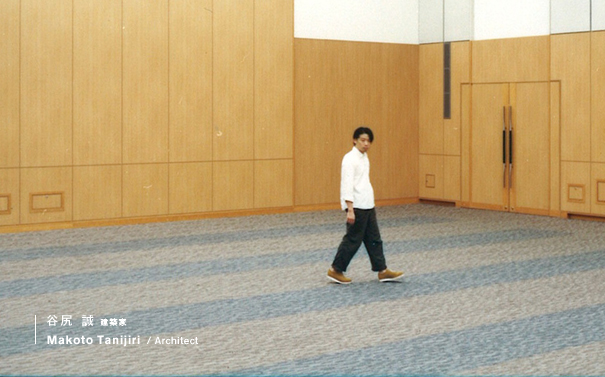
何があるかよりも、何が起きたのか。
僕は広島の中心部から車で1時間ほど離れた、三次という街で育ちました。家のすぐ近くに河原があって、部活から帰ったら釣り竿を持って川に出かけ、河原の石を集めて竿を立てたら、あとはもう、ただひたすら、ボーっとしてた。日が暮れてきたら竿の先に鈴をつけ、その鈴が鳴ると引き上げる。そんな日々。だから、川がある街はわりと好きかもしれないですね。
でも、街にどんな要素があるのかよりも、そこで誰に会うか、何を食べるかのほうが街の魅力として大きい気がします。僕、建築家ですけど、建築的要素だけではその街を何度も訪れたいとは思わない。人との出会いがあり、その人がいる街だから行く、というほうが自然ですよね。そこに何があるかより、「そこで何が起きたか」の方が大切だと思います。
街は人が迎えてくれるのが一番いい。
結局、街って、人が迎えてくれるのが一番いいと思うんです。この街へようこそ、って迎え入れてくれる人が魅力的であることが、一番の価値ではないでしょうか。
僕は仕事も広島を拠点に始めたので、東京はよく分からなかったし、六本木というと、ギラギラしたイメージだったんですね。お金もちの人が行くお店ばかりで近寄りがたい街なのかと思っていた。でも実際に来てみると、僕らでも入れる気軽なお店もあるし、古くから住んでいる人がこんなところもあるよ、あんなのもあるよ、と教えてくれたりする。街の中にいる人にとっては当たり前にあるものも、外から新しく来た人にとっては新鮮なので、もっと六本木の人に六本木のことを教えてもらいたいと思いますね。
一番関心があるのは人。自分を超えていくために。
建築家として今一番関心のあることも「人」です。仕事をいくつも経験すると、自分の力量もわかってくるし、自分が支配できる出来事の中だけで物事を進めている限りは、何をすると何ができる、ということもだいたい見えてくる。そうなると、自分が作ったものに感動できなくなってくるんですね。僕はそれが嫌なんです。自分が作ったものに、感動し続けたいんです。
人に興味があるというのは、つまり、自分超えに興味があるんでしょうね。人と人が出会うことで科学反応が起き、思ってもみなかった可能性に気づいたり、予期せぬ方向にアイディアが成長したり。いろんな人と「思考のトレード」をすることで、自分の仕事が自分を超えていくことができる。
もっと何かできるんじゃないか、もっと良くなるためにはどうすればいいかと僕は絶対に思い続けるので、ものづくりの可能性として、自分にないものを持っている自分以外の「人」のことが、やっぱり一番気になります。
取材を終えて......
「建物に洋服を着させる」「横断歩道を人が渡ると両側に滝ができる」など、実現したら世界的に有名な街になりそうなアイデア満載だったのですが、特に感得したのは既に刷り込まれている常識や概念を疑う、というお話でした。例えばこの六本木未来会議というサイトを文字を使わず表現したら......など、発想のスイッチは無限にあるということですね。(edit_rhino)
RELATED ARTICLE関連記事



























